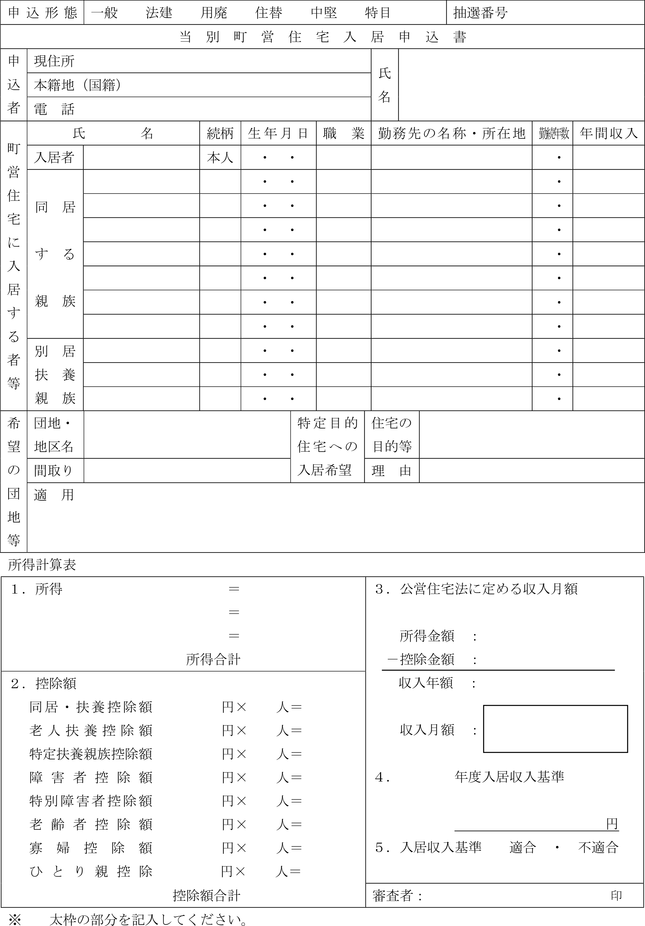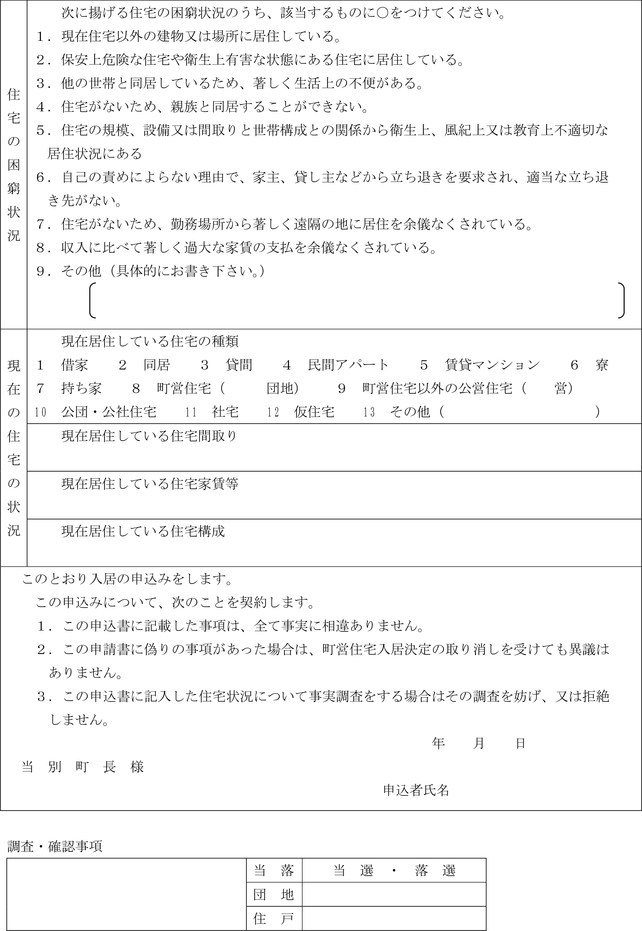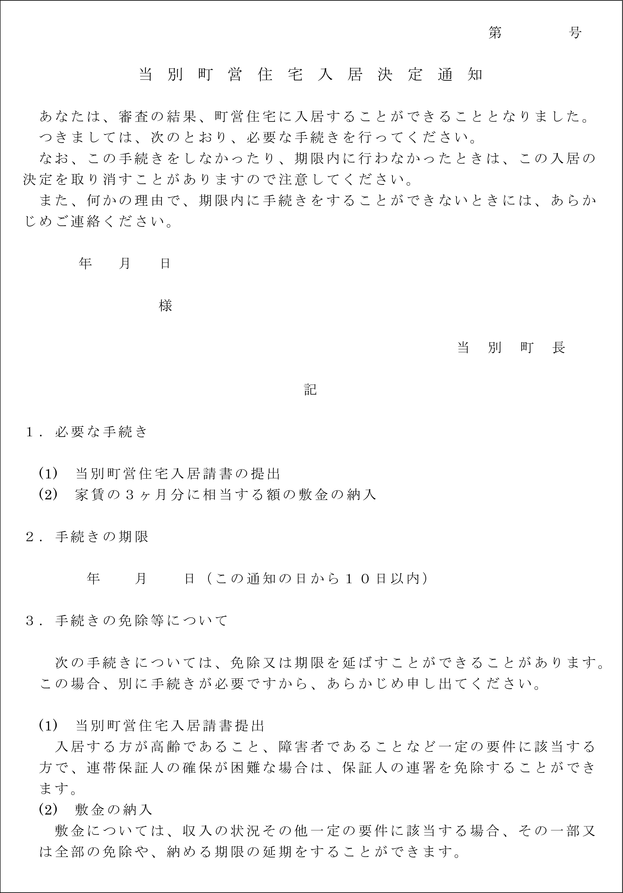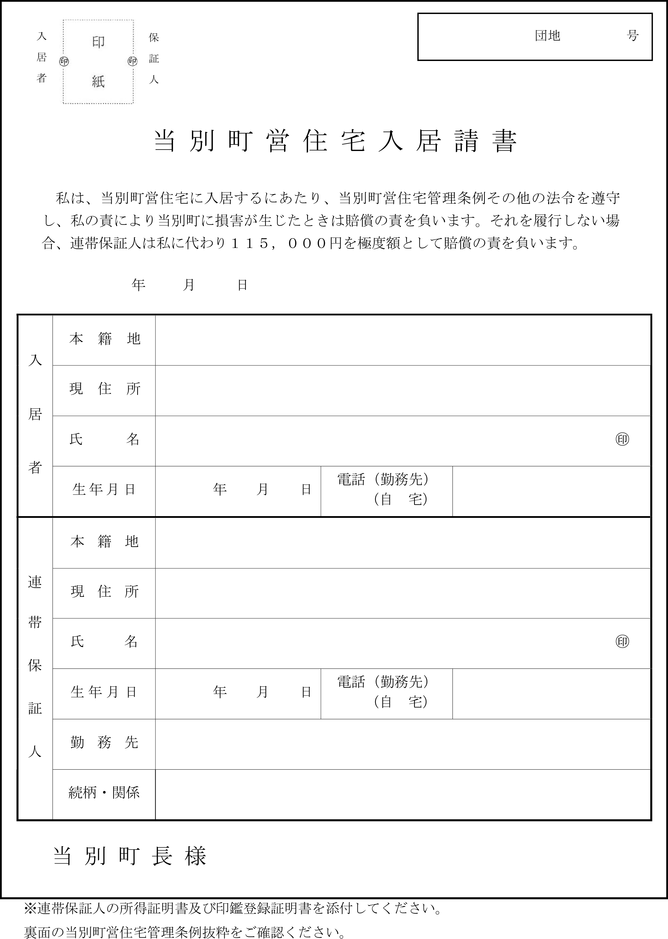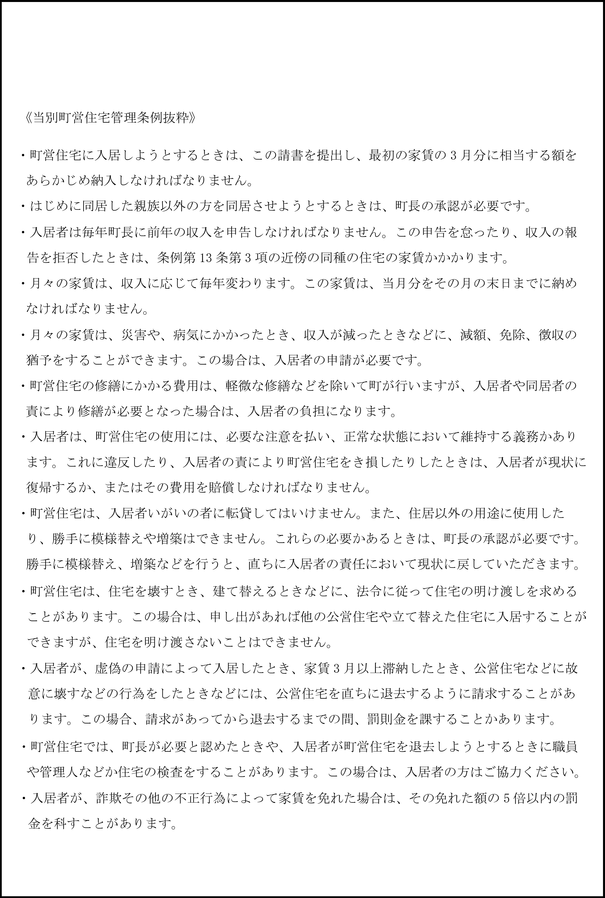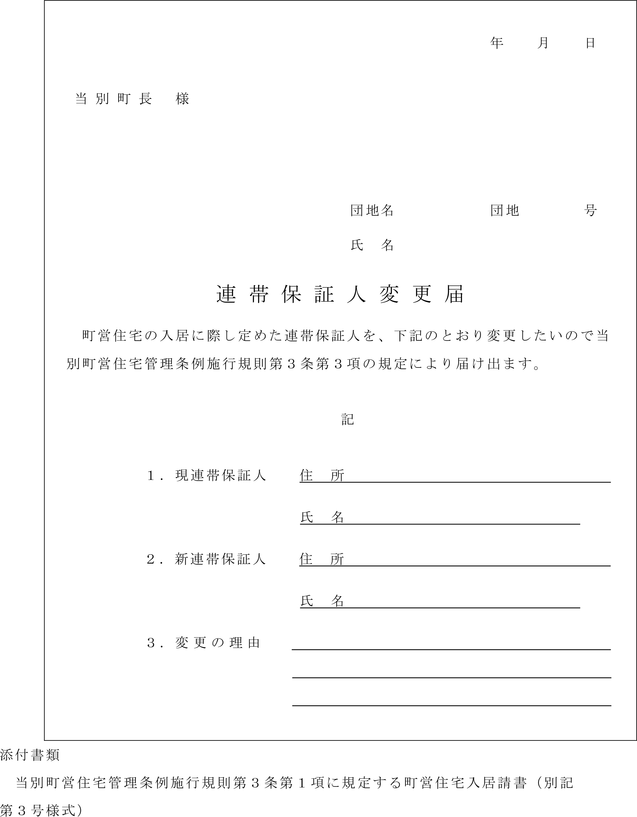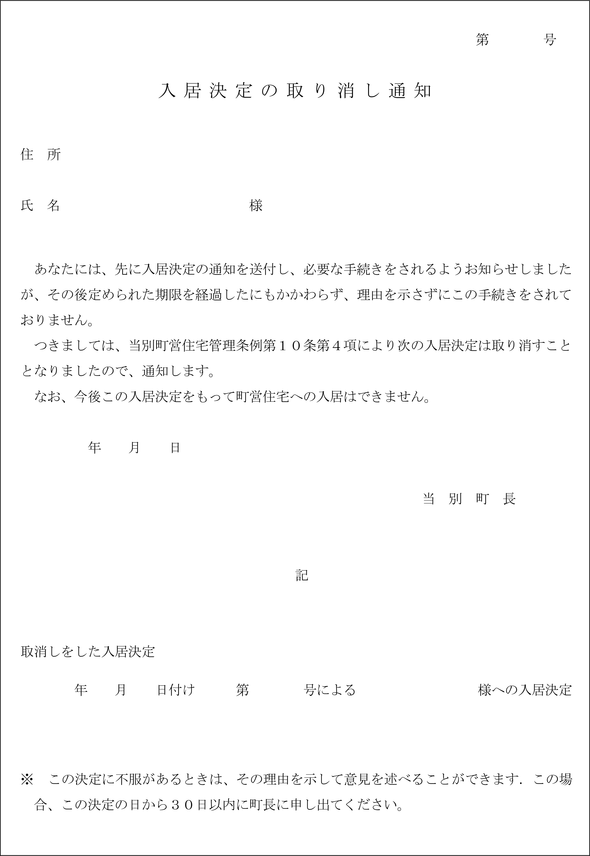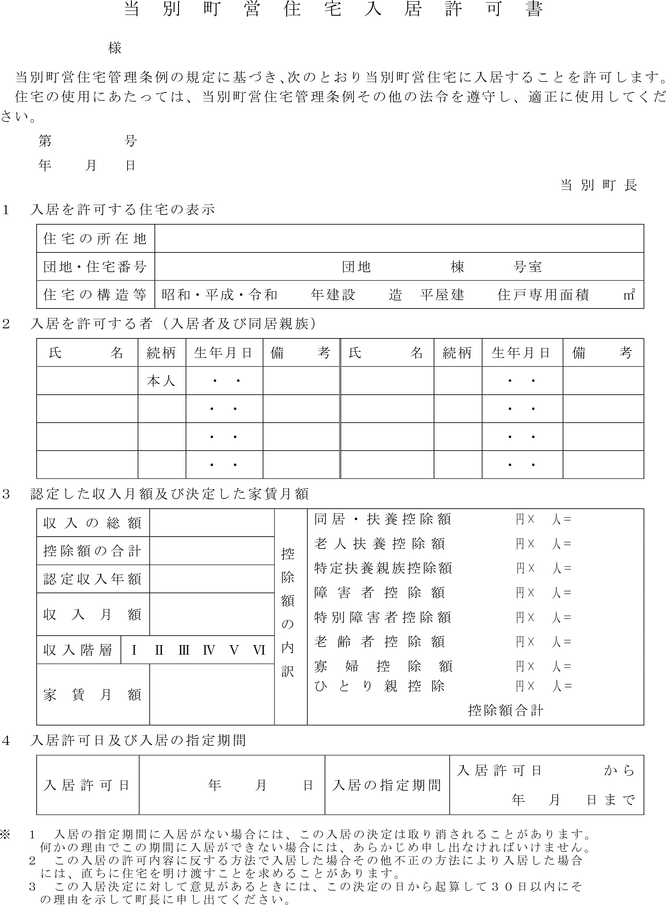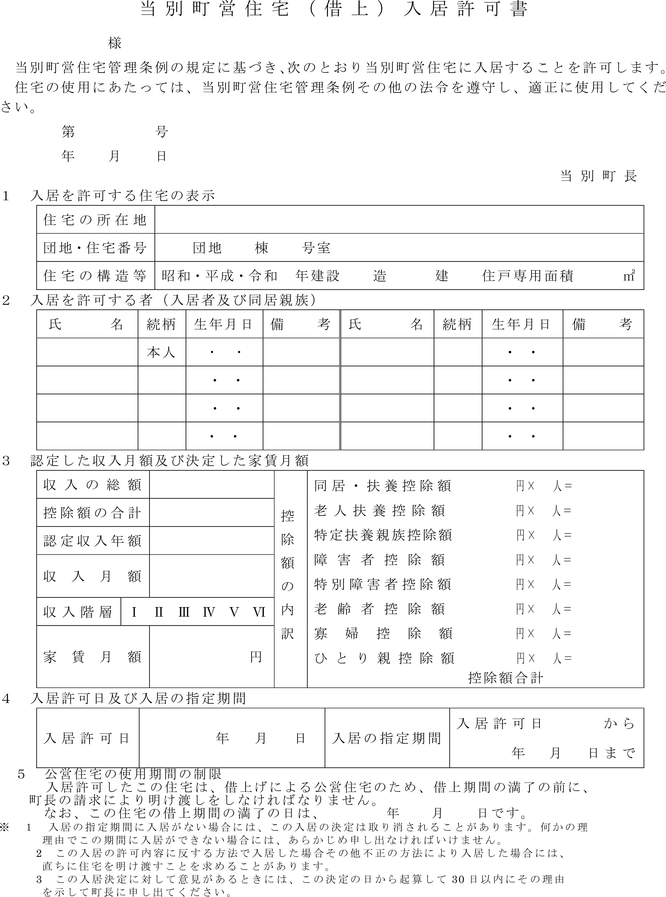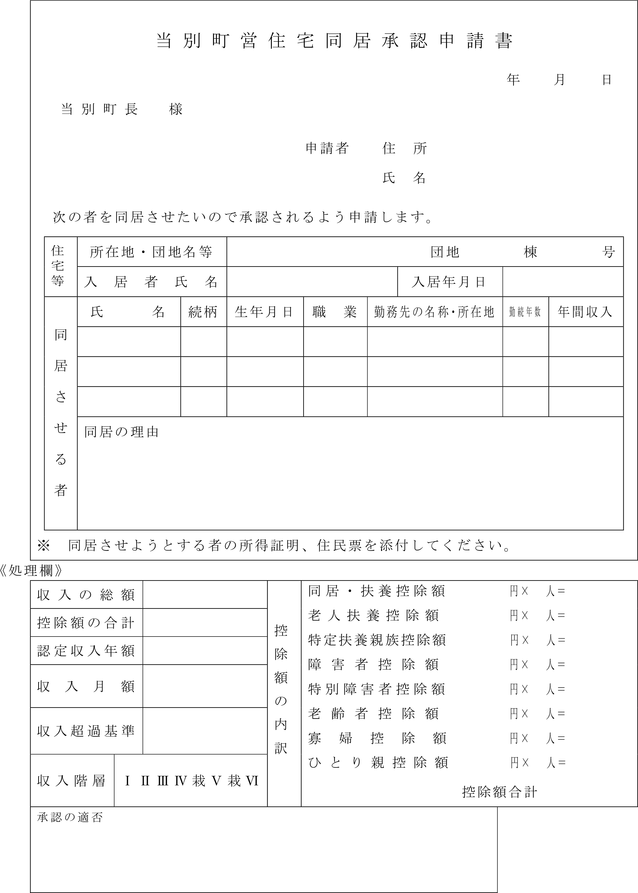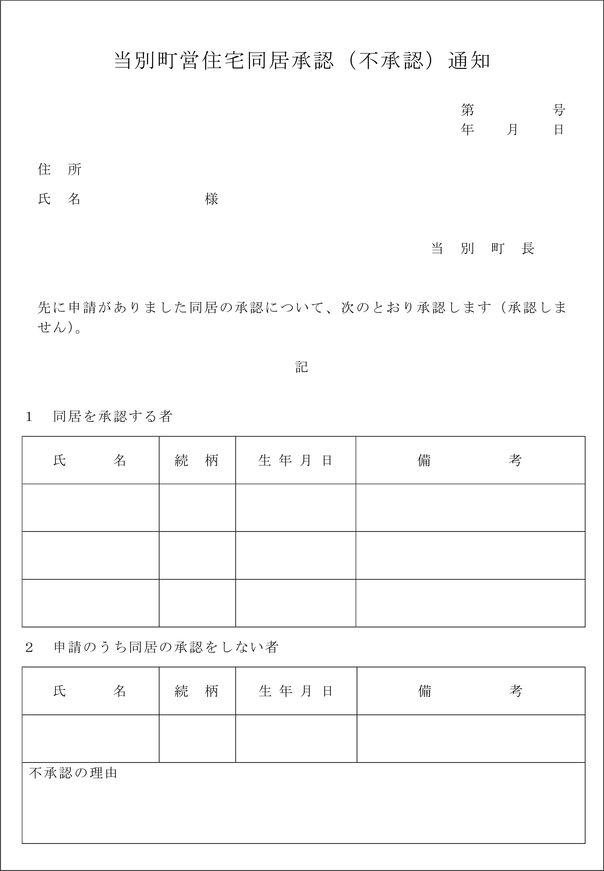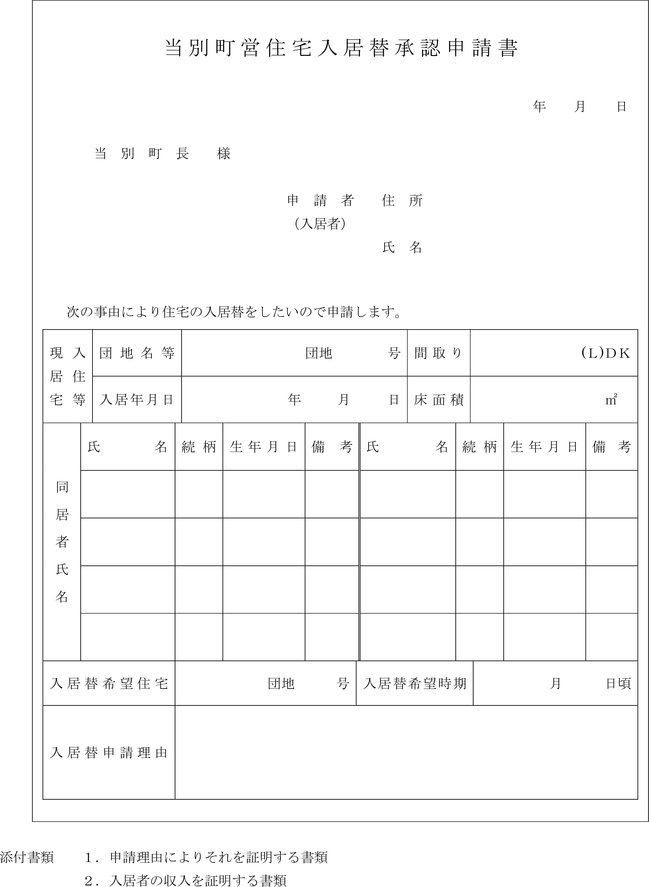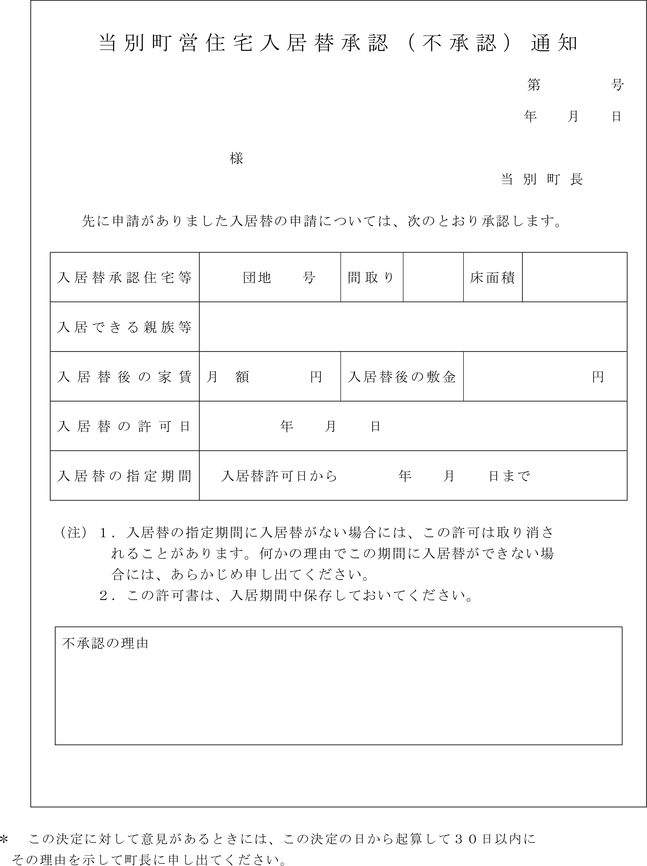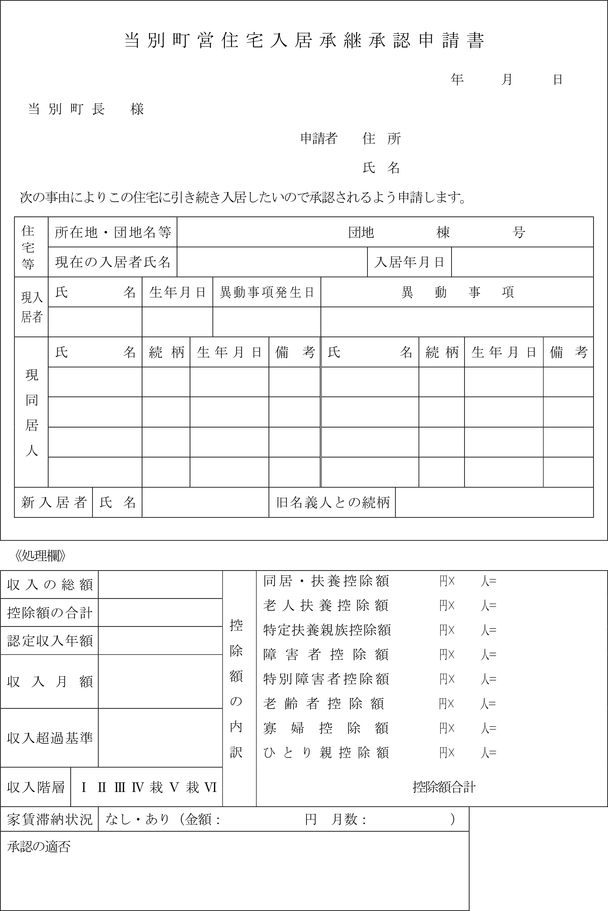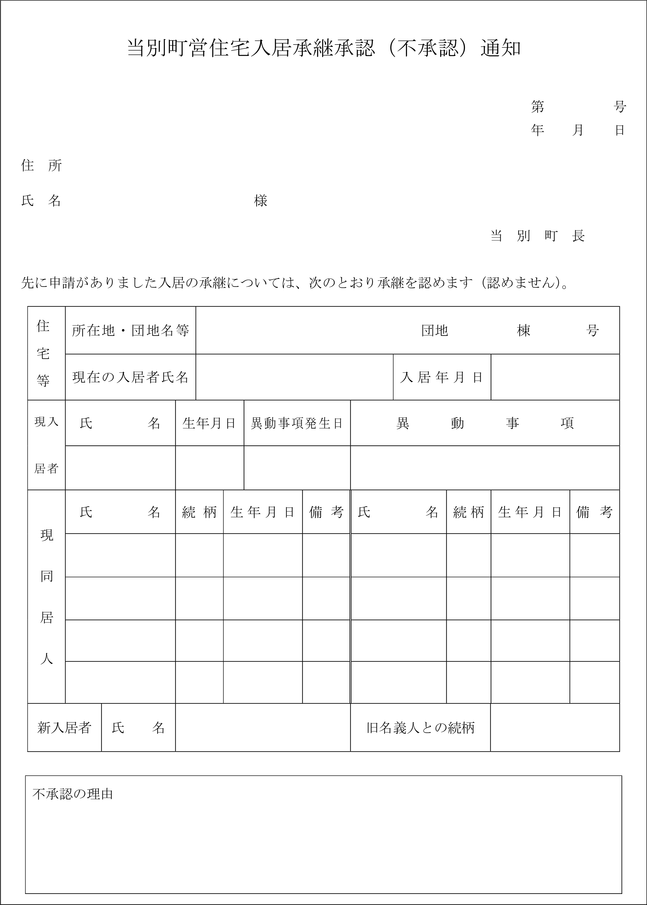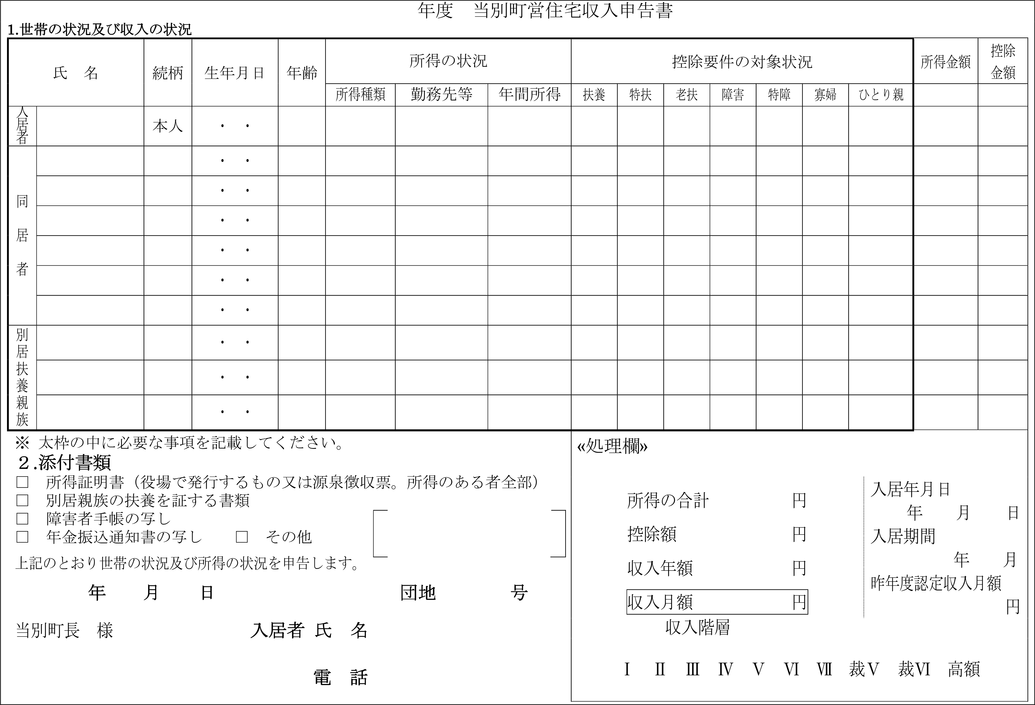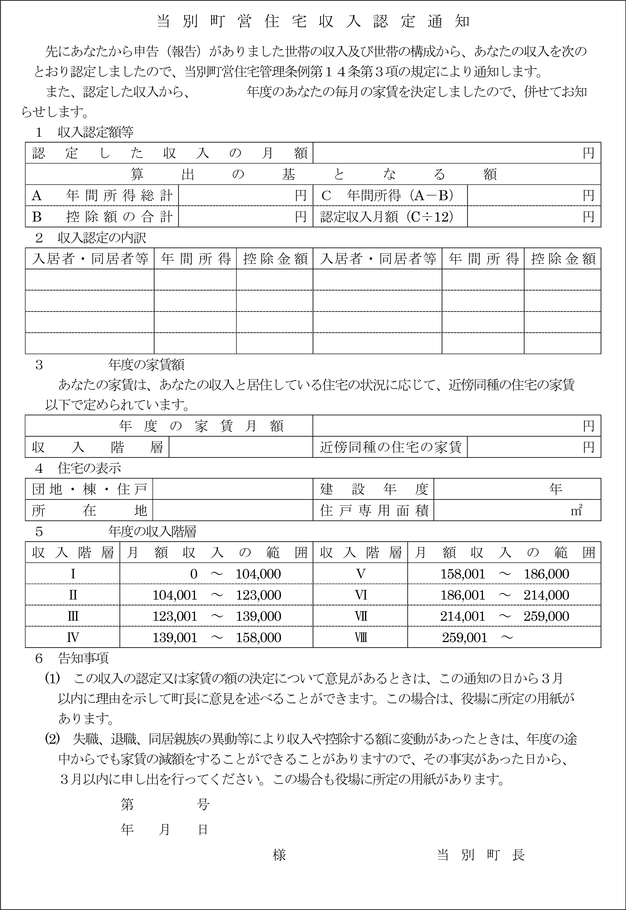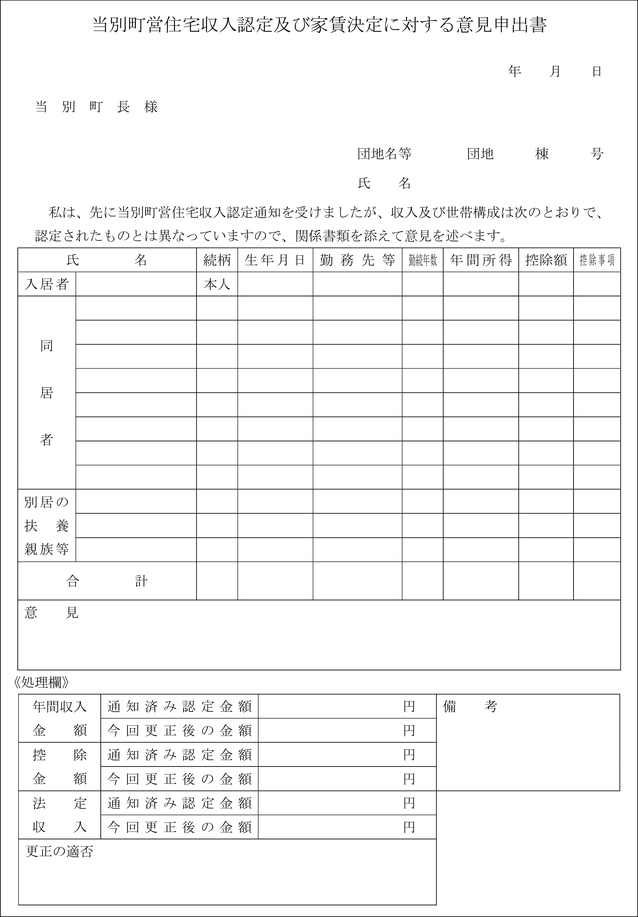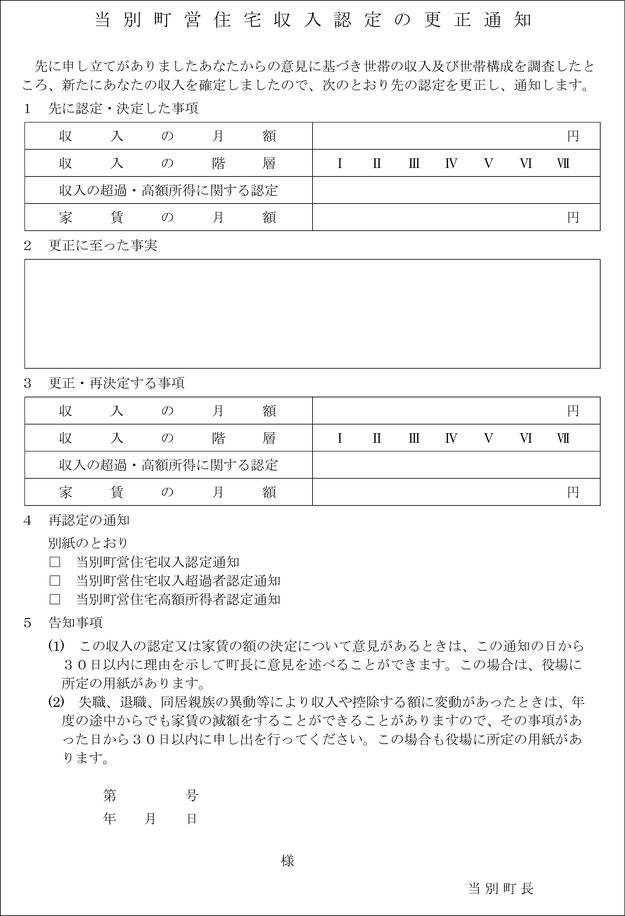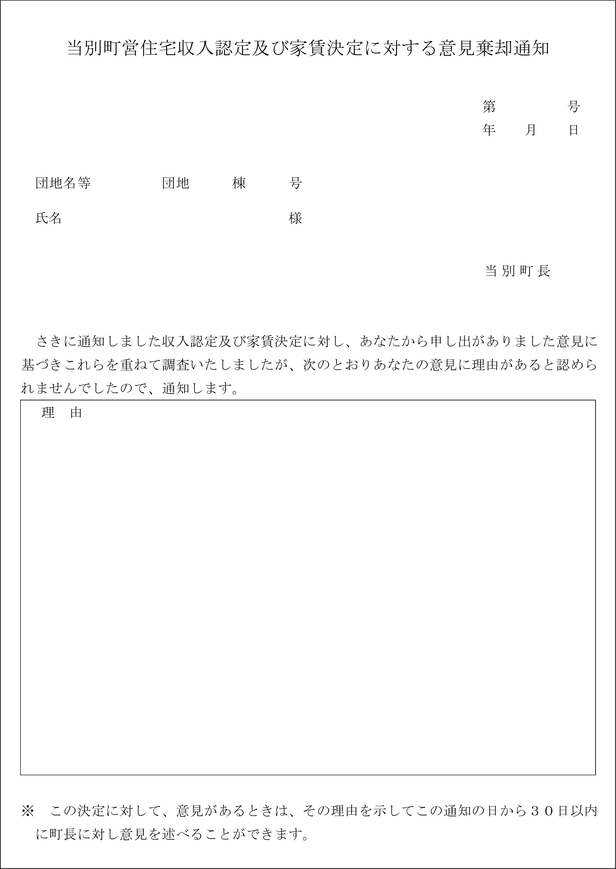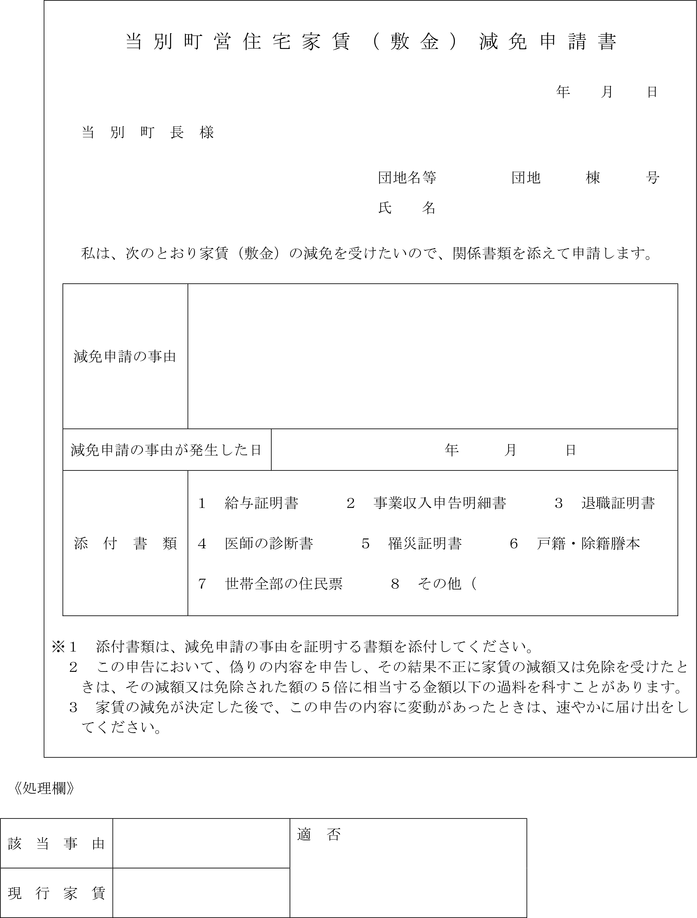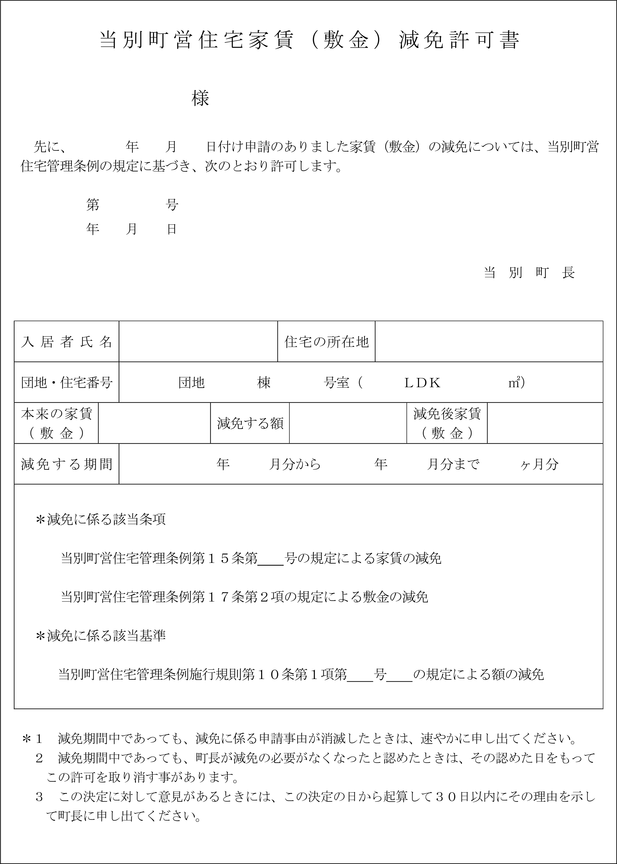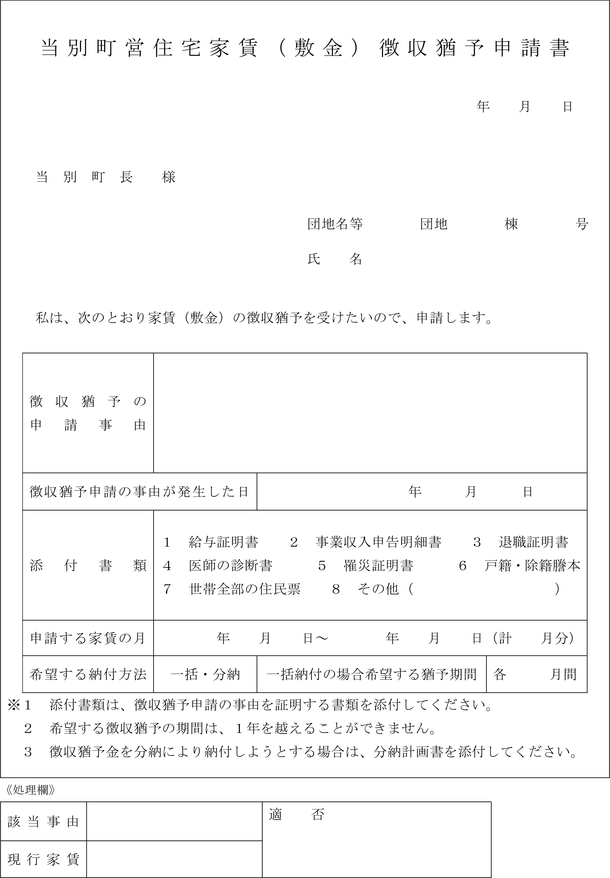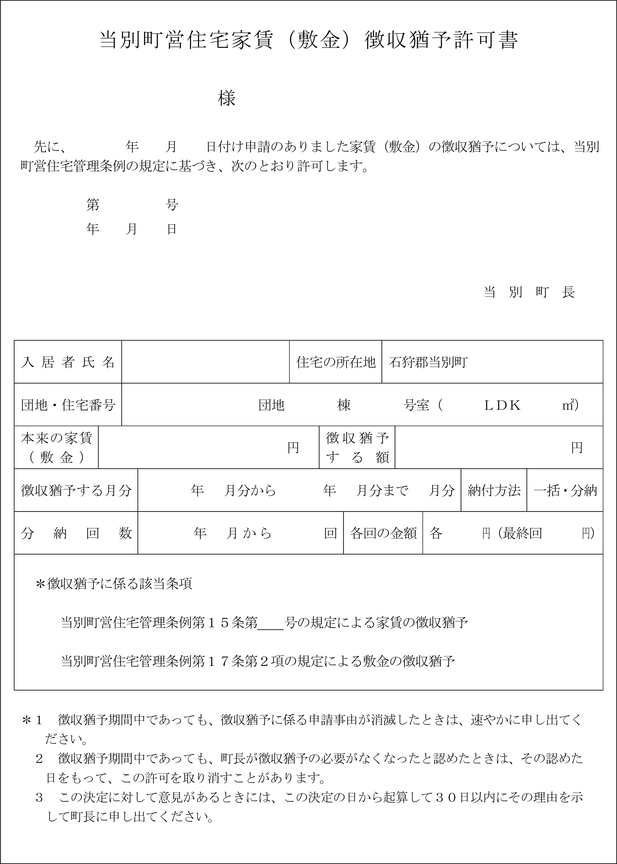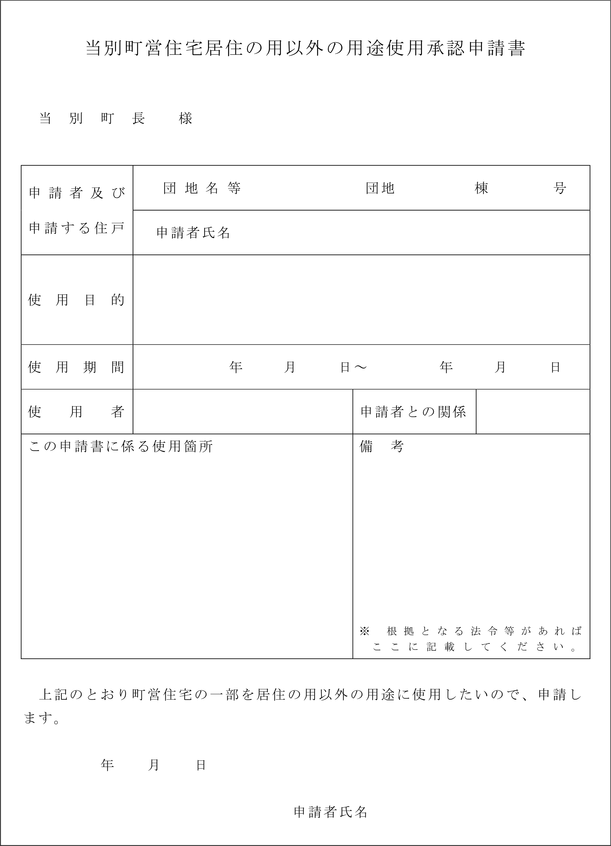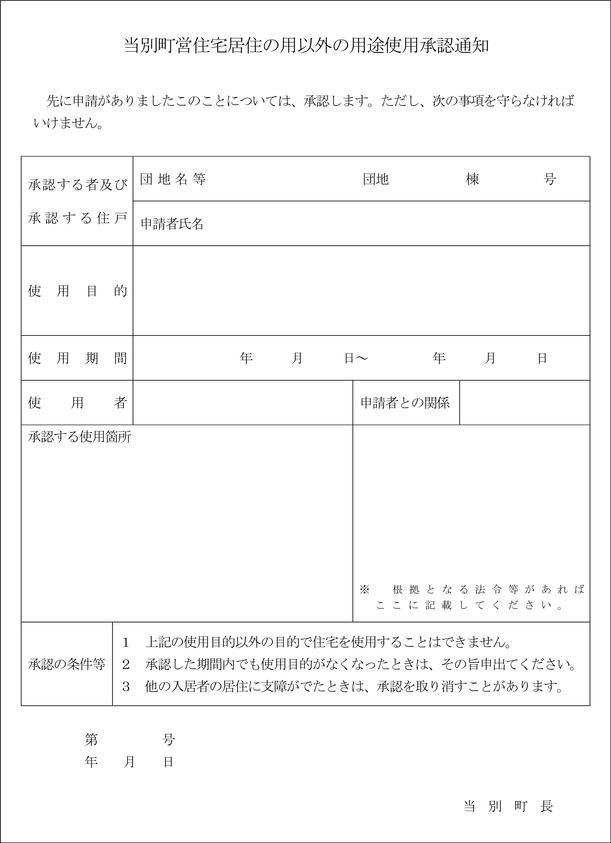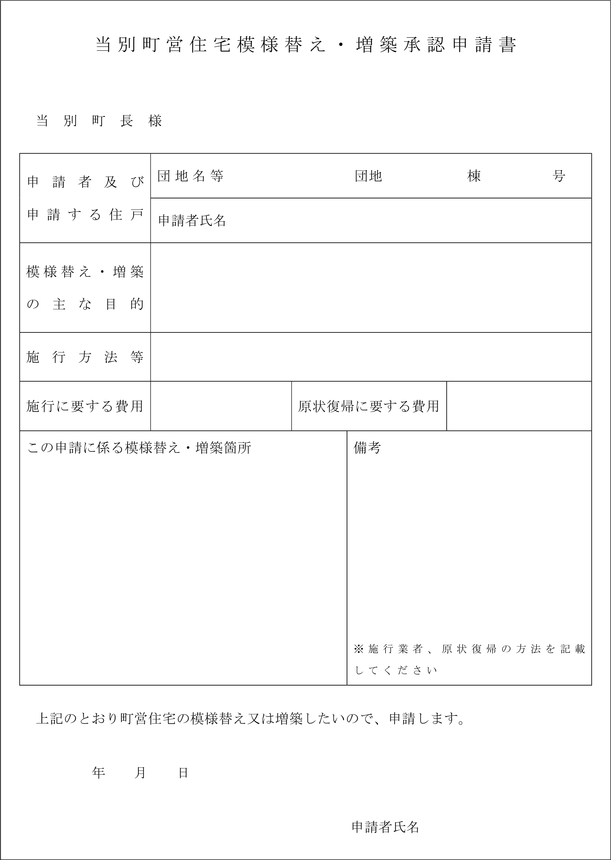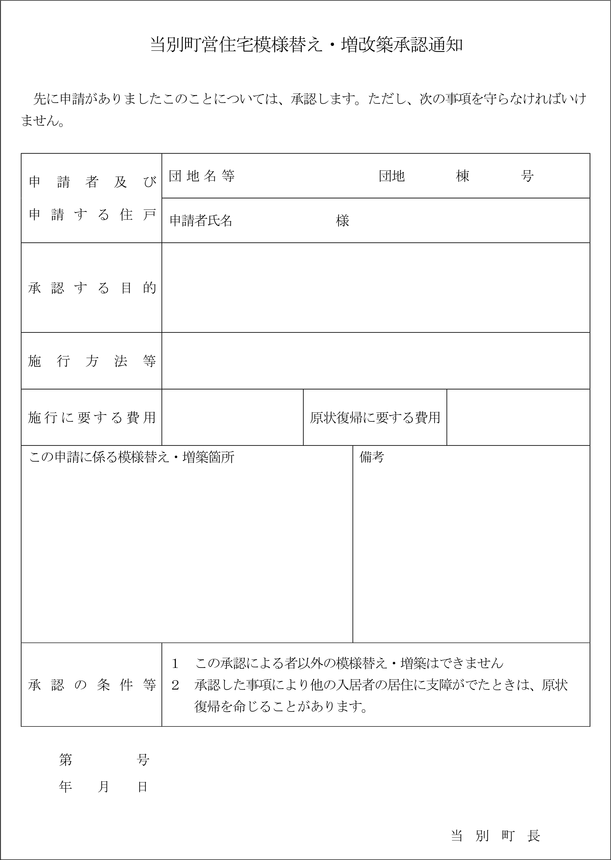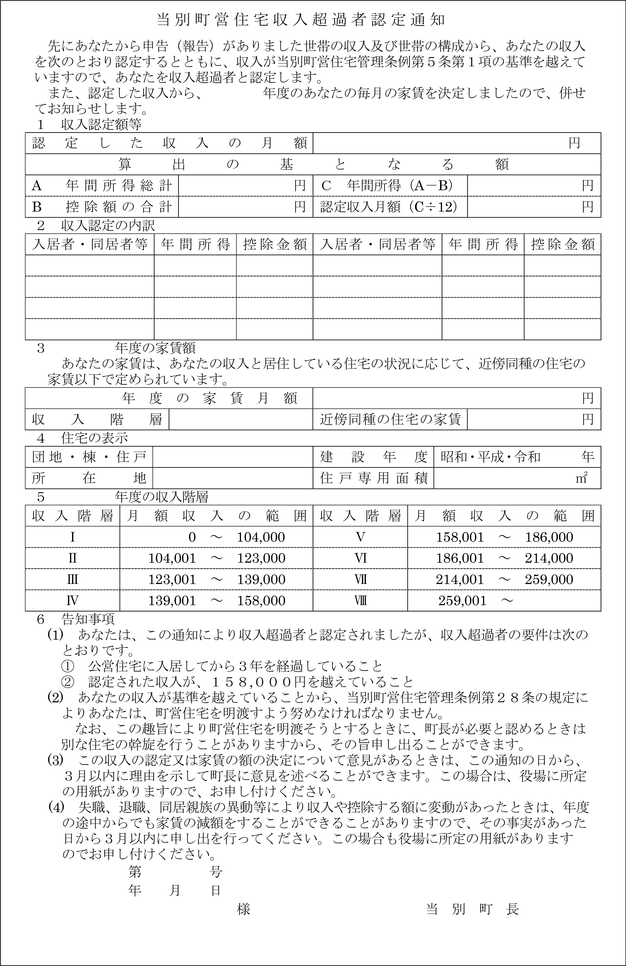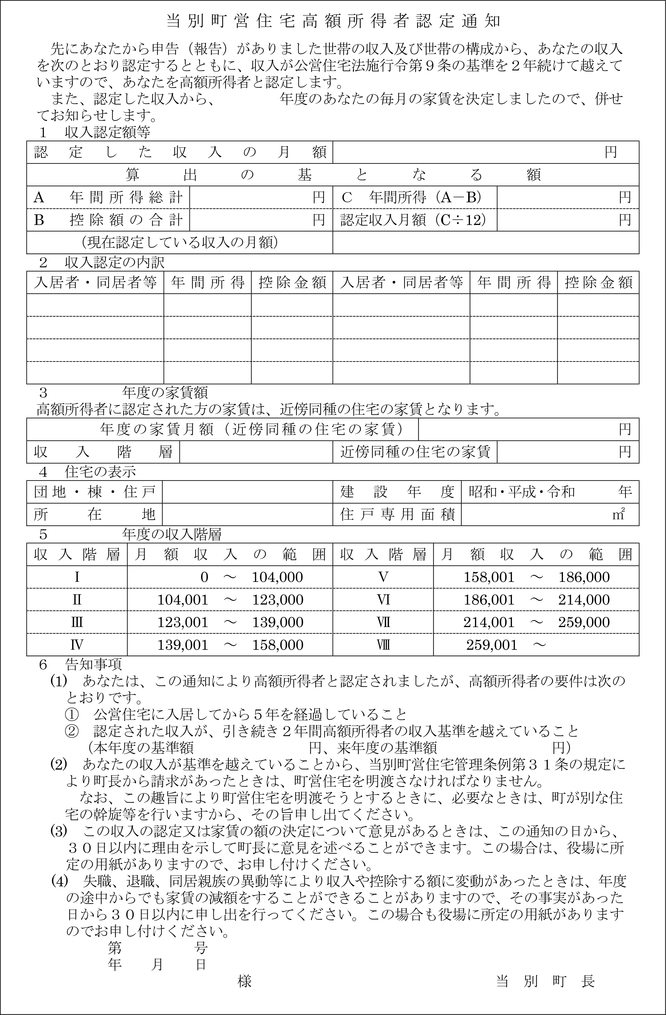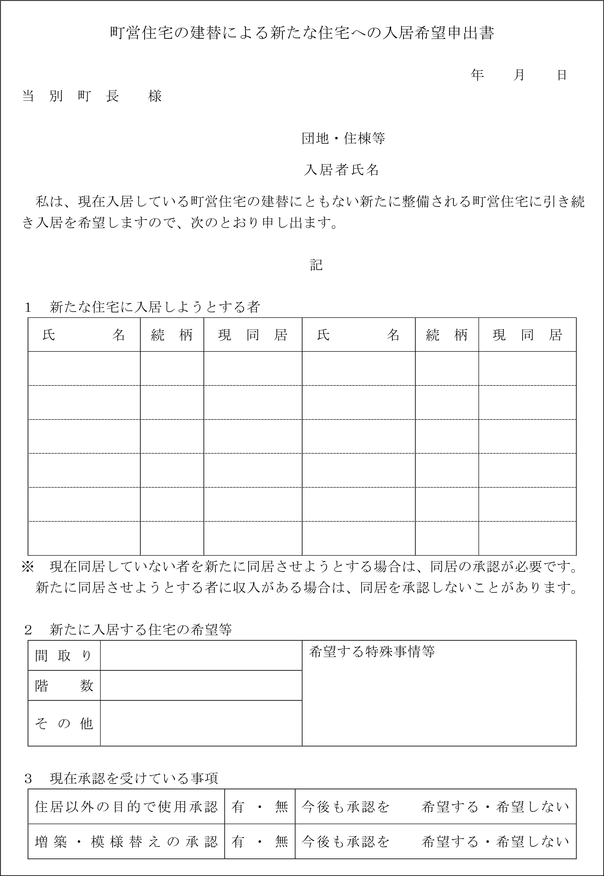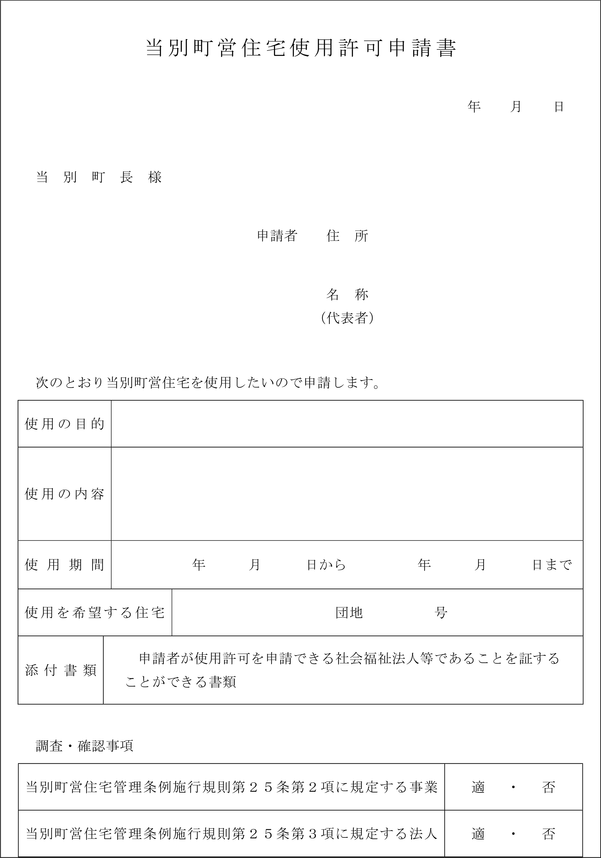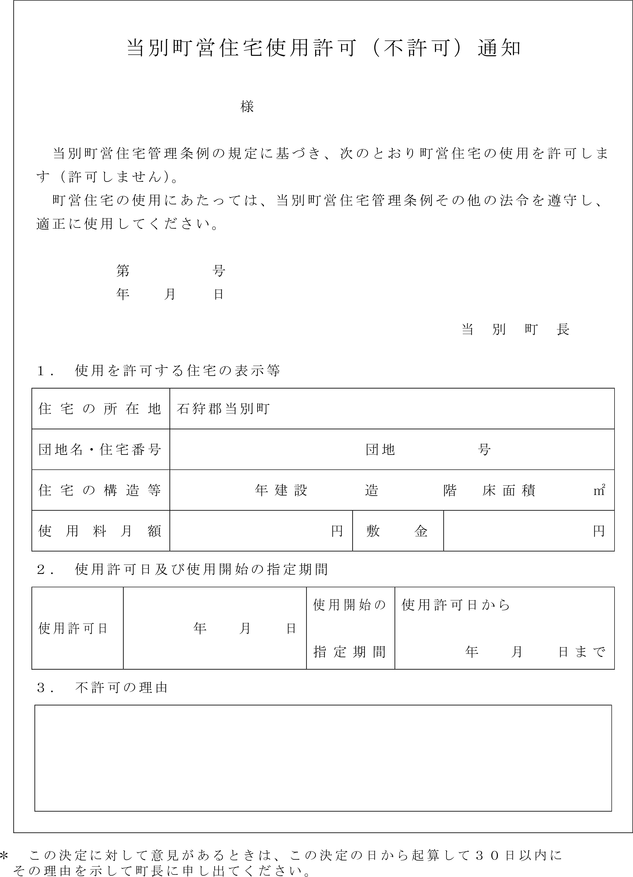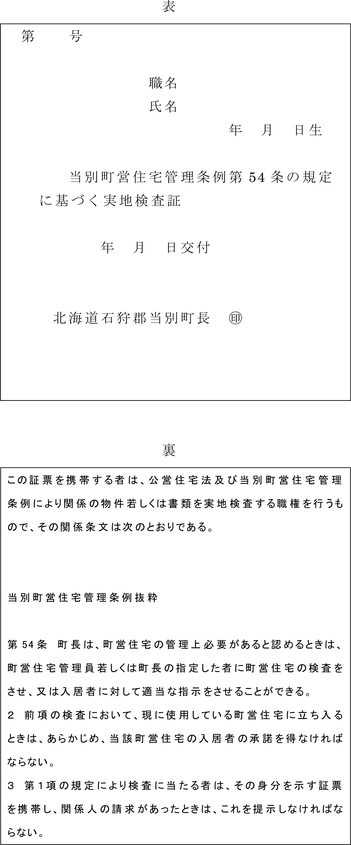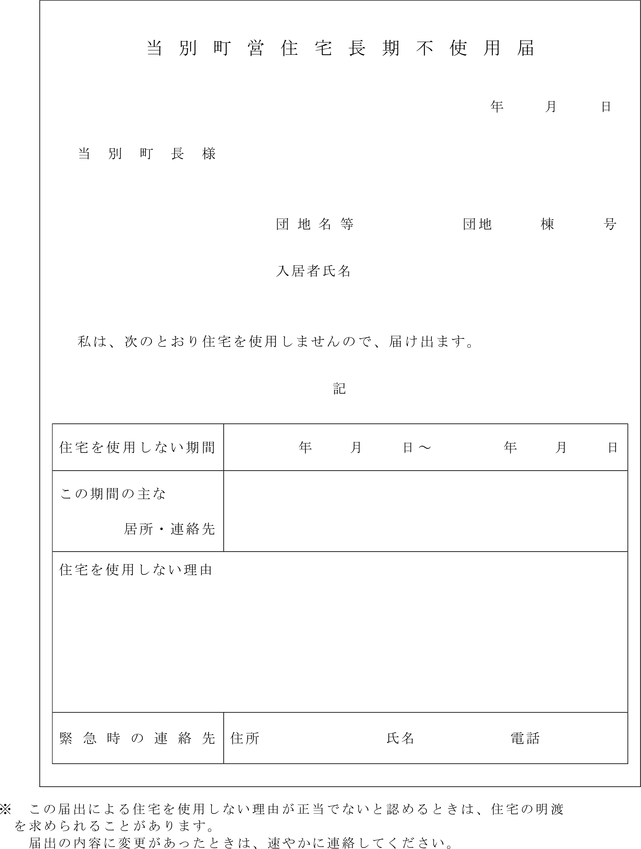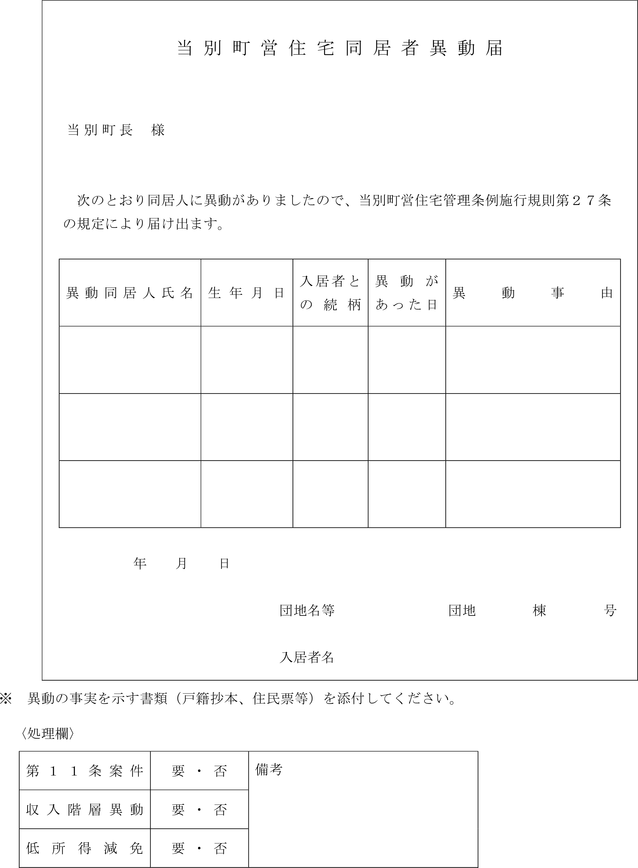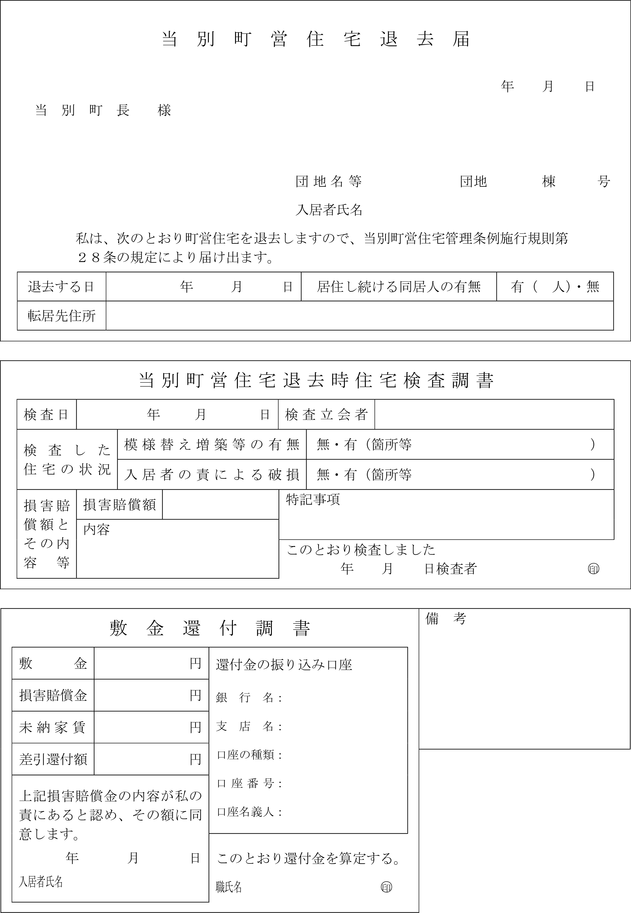○当別町営住宅管理条例施行規則
平成9年7月1日規則第11号
当別町営住宅管理条例施行規則
当別町営住宅管理条例施行規則(昭和56年当別町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに当別町営住宅管理条例(昭和55年当別町条例第16号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
(入居の申込み及び決定)
第2条 条例第7条第1項に定める入居の申込みは、当別町営住宅入居申込書(
別記第1号様式)で行わなければならない。
2 前項の規定による申込みの際次の各号に係る事由を証明する書類を添付しなければならない。
(1) 住民票謄本又はそれらに類する証明書
(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 納税証明書
(4) 申込者に、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情による場合は、勤務先の扶養証明あるいは住民票謄本等の証明書
(5) 申込者に婚姻の予約者がある場合については、当事者双方及び成年の証人2人以上の署名した婚約証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
3 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、当別町営住宅入居決定通知(
別記第2号様式)により行うものとする。
(入居の手続)
第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、当別町営住宅入居請書(
別記第3号様式)によるものとする。
2 前項の規定による請書に連署する保証人は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 本町に引き続き1年以上居住している者。ただし、町営住宅に居住している者を除く。
(2) 独立の生計を営む者で、入居者と同程度以上の収入を有する者
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でない者
3 前項各号の要件を具備する保証人がいない場合には、石狩振興局管内及び本町に隣接する同一市町村に一年以上居住する者で前項第2号及び第3号の要件を具備する当該入居者の民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族が、これに替わることができる。
4 入居者は、前2項の規定による保証人が死亡したとき、又は前2項に定める条件を具備しなくなったときは、速やかに新たな保証人を選定し、連帯保証人変更届(
別記第4号様式)により町長に届け出なければならない。
5 条例第10条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、入居決定の取り消し通知(
別記第5号様式)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。
6 条例第10条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、当別町営住宅入居許可書(
別記第6号様式)により通知するものとする。ただし、入居させようとする住宅が借上に係る町営住宅であるときは、当別町営住宅(借上)入居許可書(
別記第7号様式)により通知するものとする。
7 第2項から第4項までの規定による連帯保証人の負担は、極度額を115,000円とする。
8 条例第10条第3項の規定により連帯保証人を立てることを免除することができる者は、法人(保証会社等の法人で町長が認める者に限る。)による保証を受けている者でなければならない。この場合において、毎年度条例第14条第1項の規定による収入申告の際には、当該法人との保証を受けていることの分かる書類を提出するものとする。
(同居の承認)
第4条 入居者は、条例第11条の規定により町長の承認を得ようとするときは、当別町営住宅同居承認申請書(
別記第8号様式)により申請しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第11条の規定による承認をすることができない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が条例第40条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 町長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第11条の規定による承認をすることができる。
4 町長は、入居者から第1項の規定による申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、当別町営住宅同居承認(不承認)通知(
別記第9号様式)により当該入居者に通知するものとする。
(入居替の承認)
第5条 入居者は、条例第4条第7号の規定により町長の承認を得ようとするときは、当別町営住宅入居替承認申請書(
別記第10号様式)により申請しなければならない。ただし、当該入居者が条例第40条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合においては、条例第4条第7号の規定による承認をすることができない。
2 町長は、入居者から第1項の規定による申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、当別町営住宅入居替承認(不承認)通知(
別記第11号様式)により当該入居者に通知するものとする。
(入居の承継の承認)
第6条 条例第12条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、当別町営住宅入居承継承認申請書(
別記第12号様式)により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第12条の規定による承認をすることができない。
(1) 当該承認を得ようとする者が、入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入が条例第27条第2項に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者が、条例第40条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であった場合
3 第4条第3項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
4 町長は、町営住宅の同居者から第1項の規定による申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、当別町営住宅入居承継承認(不承認)通知(
別記第13号様式)により当該町営住宅の同居者に通知するものとする。
(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)
第7条 条例第14条第2項に規定する町長が定める係数は、1から町営住宅の付帯設備の状況を勘案し、0から0.3の範囲内で町長が定める数値を減じたものとする。
(収入申告の方法)
第8条 入居者は、条例第14条第1項に定める収入の申告は、当別町営住宅収入申告書(
別記第14号様式)により行うものとする。
(収入の認定及び更正)
第9条 町長は、条例第14条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、当別町営住宅収入認定通知(
別記第15号様式)により当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。
2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して、当別町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見申出書(
別記第16号様式)により意見を述べなければならない。
3 町長は、入居者から前項の規定による意見申出書を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、当別町営住宅収入認定の更正通知(
別記第17号様式)により当該入居者に通知し、又は当該意見に理由がないと認めるときは、当別町営住宅収入認定及び家賃決定に対する意見棄却通知(
別記第18号様式)により理由を示し当該入居者に通知するものとする。
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第15条(条例第29条第3項、条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により家賃の減免を行う場合の基準は次表のとおりとする。
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 第1号に該当する場合 | |
イ 生活保護法による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
ロ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の105を乗じて得た額以下の場合 | 免除 |
ハ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額を超え基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 収入の20分の1に相当する額までの減額 |
ニ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額を超え基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合 | 収入の10分の1に相当する額までの減額 |
ホ 収入が減少し、認定されている収入に応じる条例第13条の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 | 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき条例第13条に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額 |
2 第2号に該当する場合 | 町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ又はニの場合に準じて計算した額までの減額 |
入居者又は同居の親族が病気により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 |
3 第3号に該当する場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のロ、ハ又はニの場合に準じて計算した額までの減額 |
災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 |
4 第4号に該当する場合 | 前記1から3までの場合に準じて町長が定める額までの減額 |
備考 「収入」とは、入居者の世帯の収入をいう。 |
2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、1年を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
4 第1項の規定に該当することにより家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、当別町営住宅家賃(敷金)減免申請書(
別記第19号様式)により申請しなければならない。
5 第2項の規定に該当することにより家賃又は敷金の徴収の猶予を受けようとする者は、当別町営住宅家賃(敷金)徴収猶予申請書(
別記第20号様式)により申請しなければならない。
6 条例第17条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前5項の規定を準用する。
(家賃及び敷金の納付)
第11条 家賃及び敷金は、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(日割計算)
第12条 条例第16条第4項の規定に基づく、日割計算による家賃は、月の家賃をその月の日数で除した額に入居日数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)とする。
(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)
第13条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住居以外の用途に使用しようとする者は、当別町営住宅居住の用以外の用途使用承認申請書(
別記第21号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当別町営住宅の用以外の用途使用承認通知(
別記第22号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造をともなうとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)
第14条 条例第26条の規定により町営住宅を模様替え、増築し、又は工作物を設置しようとする者は、当別町営住宅模様替え・増築承認申請書(
別記第23号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当別町営住宅模様替え・増築承認通知(
別記第24号様式)により承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(収入超過者等に対する認定等)
第15条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、当別町営住宅収入超過者認定通知(
別記第25号様式)によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第9条第1項に規定する通知は要しない。
2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、当別町営住宅高額所得者認定通知(
別記第26号様式)によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第9条第1項に規定する通知は要しない。
3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第9条第2項及び第3項の規定を準用する。
(条例第31条第2項に規定する町長が定める額)
第16条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。
(町営住宅建替事業の施行にともなう新たに整備される町営住宅への入居の申出)
第17条 条例第36条の規定により新たに整備された町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅の建替による新たな住宅への入居希望申出書(
別記第27号様式)により申し出なければならない。
(社会福祉事業での使用手続)
第18条 条例第42条の規定により町長の許可を得ようとする社会福祉法人等は、当別町営住宅使用許可申請書(
別記第28号様式)により申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請を受理したときは、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては理由を示して許可しない旨を、当別町営住宅使用許可(不許可)通知(
別記第29号様式)により当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(社会福祉事業での使用料)
第19条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第20条 条例第51条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第21条 条例第53条第1項に規定する町営住宅監理員は、町営住宅管理事務を所管する職員をもってこれに充て、同条第3項に規定する町営住宅管理人は、各団地ごとに入居者のうちから適当な者を委嘱する。
(町営住宅監理員の職務)
第22条 町営住宅監理員は、条例第53条に定めるもののほか次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 家賃納入の督励に関すること。
(3) 町営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申請又は届出の受理及び申達に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における町営住宅の検査及び引継ぎに関すること。
(6) 不正入居の防止に関すること。
(7) 許可のない模様替、増築、用途変更及び工作物設置の防止に関すること。
(8) 町営住宅及び共同施設の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(9) その他町長の指示する事項に関すること。
(町営住宅管理人の職務)
第23条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指示に従い、直接その団地内の住宅及び共同施設を管理するものとする。
2 町営住宅管理人に対して、1戸当り月額50円の割合による事務費を支給するものとする。
(住宅検査の証票)
第24条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅実施検査証(
別記第30号様式)によるものとする。
(敷地の目的外使用)
第25条 条例第55条に規定する規則で定める使用の許可は、次のとおりとする。
2 敷地の目的外使用を許可することができる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に規定する精神障害者地域援助事業
(2) 精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第4項に規定する精神薄弱者地域援助事業
3 敷地の目的外使用を許可することができる事業主体は、次の各号に掲げる事業主体とする。
(1) 地方公共団体
(2) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(4) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3項に規定する公益法人
(長期間不使用の申出)
第26条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、当別町営住宅長期不使用届(
別記第31号様式)により町長に申し出なければならない。
(同居者の異動の届出)
第27条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、当別町営住宅同居者異動届(
別記第32号様式)により町長に届け出なければならない。この場合において、第4条の規定は適用しない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
(退去の届出及び敷金の還付)
第28条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する10日前までに当別町営住宅退去届(
別記第33号様式)により退去する旨を町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町営住宅管理人に当該住宅の検査をさせるものとする。
3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第16条第5項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。
(町営住宅の設置の場所、戸数等)
第29条 条例第2条第1項に規定する町営住宅の設置の場所、戸数等は
別表のとおりとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の当別町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は平成9年6月30日から適用する。ただし、平成10年3月31日までの間は、新規則第4条、第6条、第8条から第17条まで、第32条及び第34条の規定は適用せず、改正前の当別町営住宅管理条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条、第8条、第10条から第15条まで、第18条から第25条までの規定は、なおその効力を有する。
2 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。
3 新規則第25条の規定に基づく入居者選考委員会は、旧規則による入居者選考委員をこの新規則に基づき委嘱したものとみなす。なお、委員の任期は、旧規則に基づいて委嘱した委員の残任期間とする。
附 則(平成12年10月10日規則第32号)
この規則は、平成12年10月11日から施行する。
附 則(平成13年4月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月5日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の当別町営住宅管理条例施行規則第3条第2項第1号の規定の条件を具備する者は、改正後の当別町営住宅管理条例施行規則第3条第2項第1号の条件を具備する者とみなす。
附 則(平成20年10月1日規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月10日規則第41号)
この規則は、平成28年8月11日から施行する。
附 則(平成30年11月11日規則第30号)
この規則は、平成30年11月12日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月6日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第44号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第29条関係)
第1種町営住宅 簡易耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 (戸) | 備考 |
昭和40年度 | 末広団地 | 末広 | 8 | 平家建 |
昭和41年度 | 末広団地 | 末広 | 10 | 〃 |
昭和46年度 | 東町団地 | 東町 | 14 | 〃 |
昭和46年度 | 東町団地 | 東町 | 6 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 6 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 2 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 8 | 2階建 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 4 | 〃 |
昭和48年度 | 東町団地 | 東町 | 16 | 平家建 |
昭和48年度 | 東町団地 | 東町 | 6 | 〃 |
昭和53年度 | 北栄団地 | 北栄町 | 10 | 〃 |
昭和54年度 | 北栄団地 | 北栄町 | 10 | 〃 |
昭和57年度 | 北栄団地 | 北栄町 | 4 | 〃 |
第1種町営住宅 中層耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 (戸) | 備考 |
平成6年度 | 春日団地 | 春日町 | 6 | 3階建 |
平成6年度 | 春日団地 | 春日町 | 6 | 3階建 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 8 | 4階建 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 8 | 4階建 |
第2種町営住宅 簡易耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 (戸) | 備考 |
昭和39年度 | 末広団地 | 末広 | 4 | 平家建 |
昭和40年度 | 末広団地 | 末広 | 10 | 〃 |
昭和41年度 | 末広団地 | 末広 | 10 | 〃 |
昭和46年度 | 東町団地 | 東町 | 12 | 〃 |
昭和46年度 | 東町団地 | 東町 | 4 | 〃 |
昭和46年度 | 春日団地 | 春日町 | 24 | 〃 |
昭和46年度 | 春日団地 | 春日町 | 8 | 〃 |
昭和46年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 12 | 〃 |
昭和46年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 〃 |
昭和47年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 6 | 〃 |
昭和47年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 2 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 4 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 2 | 〃 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 8 | 2階建 |
昭和47年度 | 東町団地 | 東町 | 4 | 〃 |
昭和48年度 | 東町団地 | 東町 | 12 | 平家建 |
昭和48年度 | 東町団地 | 東町 | 4 | 〃 |
昭和48年度 | みずほ団地 | 太美町 | 6 | 〃 |
昭和48年度 | みずほ団地 | 太美町 | 2 | 〃 |
昭和53年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 〃 |
昭和54年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 〃 |
昭和56年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 〃 |
昭和62年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 2階建 |
昭和63年度 | 樺戸団地 | 樺戸町 | 4 | 〃 |
第2種町営住宅 中層耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 (戸) | 備考 |
平成5年度 | 春日団地 | 春日町 | 2 | 3階建 |
平成5年度 | 春日団地 | 春日町 | 6 | 〃 |
平成5年度 | 春日団地 | 春日町 | 9 | 〃 |
平成5年度 | 春日団地 | 春日町 | 2 | 〃 |
平成6年度 | 春日団地 | 春日町 | 6 | 〃 |
平成6年度 | 春日団地 | 春日町 | 6 | 〃 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 2 | 4階建 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 8 | 〃 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 12 | 〃 |
平成7年度 | 春日団地 | 春日町 | 3 | 〃 |
中層耐火構造
建設年度 | 名称 | 位置 | 戸数 (戸) | 備考 |
平成8年度 | 春日団地 | 春日町 | 16 | 4階建 |
平成8年度 | 春日団地 | 春日町 | 16 | 〃 |
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第3条関係)
別記第4号様式(第3条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
別記第6号様式(第3条関係)
別記第7号様式(第3条関係)
別記第8号様式(第4条関係)
別記第9号様式(第4条関係)
別記第10号様式(第5条関係)
別記第11号様式(第5条関係)
別記第12号様式(第6条関係)
別記第13号様式(第6条関係)
別記第14号様式(第8条関係)
別記第15号様式(第9条関係)
別記第16号様式(第9条関係)
別記第17号様式(第9条関係・更正する場合)
別記第18号様式(第9条関係)
別記第19号様式(第10条関係)
別記第19号様式の1(第10条関係)
別記第20号様式(第10条関係)
別記第20号様式の1(第10条関係)
別記第21号様式(第13条関係)
別記第22号様式(第13条関係)
別記第23号様式(第14条関係)
別記第24号様式(第14条関係)
別記第25号様式(第15条関係)
別記第26号様式(第15条関係)
別記第27号様式(第17条関係)
別記第28号様式(第18条関係)
別記第29号様式(第18条関係)
別記第30号様式(第24条関係)
別記第31号様式(第26条関係)
別記第32号様式(第27条関係)
別記第33号様式(第28条関係)