○当別町住民基本台帳事務取扱規則
平成24年9月28日規則第28号
当別町住民基本台帳事務取扱規則
当別町住民基本台帳事務取扱規則(平成18年当別町規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき取り扱う事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 住民基本台帳法をいう。
(2) 令 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)をいう。
(3) 規則 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)をいう。
(4) 住民票省令 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)をいう。
(5) 戸籍の附票省令 戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省、自治省令第1号)をいう。
(6) 配偶者暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び第28条の2に規定する暴力をいう。
(7) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。
(8) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。
(9) 支援措置 配偶者暴力、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為等の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付の制度を不当に利用して、被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図るための措置をいう。
(住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する書類)
第3条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に供する書類は、法第11条第1項及び令第14条の規定に基づいて作成する書類(以下「閲覧用名簿」という。)とする。
2 閲覧用名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
3 閲覧用名簿の改製は、毎年3回を原則とし、改製の時期は、概ね2月、6月及び10月とする。
(国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧)
第4条 閲覧を請求する国又は地方公共団体の機関は、住民基本台帳閲覧請求書(別記様式第1号)を閲覧をしようとする日(以下「閲覧日」という。)の10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別に認めた場合はこの限りでない。
(個人又は法人の申出による閲覧)
第5条 閲覧の申出をする個人又は法人は、町長に対し住民基本台帳閲覧申出書(別記様式第2号。以下「閲覧申出書」という。)及び誓約書(別記様式第3号)を閲覧日の10日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する閲覧申出書及び誓約書に加え、次の各号に掲げる書類のうち必要と認めるものの提出を求めることができる。
(1) 閲覧の申出事由に係る調査や案内等の内容が分かる書類
(2) 法人登記簿又は事業所概要
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえた法人及び事業者等の個人情報保護に係る対応がわかる資料
(4) 学術研究機関等の代表、委員会、学部長等による証明書
(5) 国若しくは地方公共団体の機関から委託を受けた者又は個人若しくは法人から委託を受けた者が閲覧の申出をする場合にあっては、当該委託の事実を明らかにする書類
(6) その他町長が必要と認める書類
3 法第11条の2第1項第3号に規定する居住関係の確認として町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集合住宅の管理組合又は所有者が管理業務を行うため当該集合住宅の居住者を確認する必要がある場合であって、他に手段がない場合
(2) 自己の住所地に第三者が法第52条第1項に規定する虚偽の届出により住所を設定しているおそれがあり、当該事実を確認しようとする場合であって、他に手段がない場合
4 町長は、第1項及び第2項に規定する書類を受理したときは、その内容を審査のうえ、閲覧の可否を決定し、当該個人又は法人の申出者に対し住民基本台帳閲覧承認(却下)通知書(別記様式第4号。以下「通知書」という。)を送付する。
5 閲覧用名簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、通知書を閲覧日に持参し、求めに応じこれを提示しなければならない。
(閲覧者が本人であることの確認書類)
第6条 住民票省令第2条第3項第1号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 住民票省令第2条第3項第2号に規定する回答書は、住民基本台帳閲覧の申出に係る閲覧者に関する照会書(別記様式第5号)とし、同号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第2に掲げる書類のうちいずれか1点又は別表第3に掲げる書類のうちいずれか3点以上とする。
(閲覧状況の公表)
第7条 法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定による閲覧状況の公表は、毎年5月1日(当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する町の休日に当たる場合はその翌日)から30日間、当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)の例により公表するものとする。
(閲覧の日時及び制限)
第8条 町長は、休日条例第1条第1項に規定する町の休日及びその翌日は、閲覧させることができない。
2 町長が閲覧させることができる時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
3 前項に掲げる閲覧時間における閲覧者の定員は、それぞれ1人とする。
4 町長は、前3項の規定について特別に必要があると認める場合は、変更することができる。
(本人等の住民票の写し等の交付の請求に係る提出書類)
第9条 住民票省令第4条第1項に規定する町長が適当と認める書類は、住民票交付請求書(別記様式第6号)とする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることの確認書類等)
第10条 住民票省令第5条第1号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 住民票省令第5条第2号に規定する町長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 別表第2に掲げる書類のうちいずれか2点提示し、又は提出する方法
3 住民票省令第5条第2号に規定する現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の町長が適当と認める方法は、当該請求の任に当たっている者の同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の出生の年月日等をいう。)について、口頭で陳述させること等により当該請求の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法とする。
(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることの確認書類)
第11条 住民票省令第9条第2号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出に係る提出書類)
第12条 住民票省令第10条第1項に規定する町長が適当と認める書類は、住民票交付請求書とする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
(本人等以外の者の住民票の写し等の交付の申出につき申出の任に当たっている者の確認書類等)
第13条 住民票省令第11条第1号イに規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 住民票省令第11条第1号ロに規定する町長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法は、第10条第2項に掲げる方法とする。
3 住民票省令第11条第1号ロに規定する現に申出の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の町長が適当と認める方法は、第10条第3項に掲げる方法とする。
4 住民票省令第11条第3号ロに規定する町長が適当と認める書類は、同号ロの法人の主たる事務所の所在地の記載のある社員証、登記簿謄本、登記事項証明書又は官公署が発行した許可証の写し等とする。
(住民票の写しの交付の特例の請求に係る提出書類等)
第14条 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付を受けようとする者は、広域交付住民票請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第4条第2項に規定する町長が適当と認めるものは、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
(本人等の戸籍の附票の写しの交付の請求に係る提出書類)
第15条 戸籍の附票省令第1条第1項に規定する町長が適当と認める書類は、戸籍証明書等請求書(別記様式第8号)とする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
(本人等の戸籍の附票の写しの交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることの確認書類等)
第16条 戸籍の附票省令第2条第1号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 戸籍の附票省令第2条第2号に規定する町長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法は、第10条第2項の規定を準用する。
3 戸籍の附票省令第2条第2号に規定する現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の町長が適当と認める方法は、第10条第3項の規定を準用する。
(国又は地方公共団体の機関の戸籍の附票の写しの交付の請求につき請求の任に当たっている者が本人であることの確認書類)
第17条 戸籍の附票省令第6条第2号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
(本人等以外の者の戸籍の附票の写しの交付の申出に係る提出書類)
第18条 戸籍の附票省令第7条第1項に規定する町長が適当と認める書類は、戸籍証明書等請求書とする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
(本人等以外の者の戸籍の附票の写しの交付の申出につき申出の任に当たっている者の確認書類等)
第19条 戸籍の附票省令第8条第1号イに規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 戸籍の附票省令第8条第1号ロに規定する町長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法は、第10条第2項の規定を準用する。
3 戸籍の附票省令第8条第1号ロに規定する現に申出の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法その他の町長が適当と認める方法は、第10条第3項の規定を準用する。
4 戸籍の附票省令第8条第3号ロに規定する町長が適当と認める書類は、第13条第4項の規定を準用する。
(住民異動届の受理)
第20条 法第22条第1項、法第23条、法第24条及び法第25条の規定による届出は、住民異動届(別記様式第9号)によるものとする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
(現に届出の任に当たっている者が本人であることの確認書類等)
第21条 規則第8条第1号に規定する町長が適当と認める書類は、別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点とする。
2 規則第8条第2号に規定する町長が適当と認める書類を提示し、又は提出する方法は、第10条第2項の規定を準用する。
3 規則第8条第2号に規定する同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の町長が適当と認める方法は、住民異動届受理通知書(別記様式第10号)を送付する方法とする。この場合において、転入届、転居届及び転出届にあっては、当該転入者等の異動前住所に、世帯変更届にあっては、変更前の世帯主に通知するものとする。
(支援措置の申出)
第22条 町が備える住民基本台帳に記録され、又は町が作成する戸籍の附票に記録されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者は、町長に対し支援措置の実施を求める申出(以下「支援措置の申出」という。)をすることができる。
(1) 配偶者暴力による被害を受け、かつ、更なる配偶者暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのある者
(2) ストーカー行為等による被害を受け、かつ、更に反復してストーカー行為等による被害を受けるおそれのある者
(3) 児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、特に生命若しくは身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれのある者
2 支援措置の申出を行う者(以下「支援措置申出者」という。)は、町長に対し支援措置申出書(別記様式第11号。以下「申出書」という。)を提出しなければならない。
3 支援措置の申出は、次に掲げるいずれかの者の意見を明らかにして行うものとする。
(1) 配偶者暴力防止法第3条第1項及び同条第2項に規定する施設の長
(2) 配偶者暴力防止法第8条の2に規定する被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとされる者
(3) ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとされる者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)
(5) その他町長が適当と認めた者
4 町長は、支援措置申出者に対し裁判所の発行する保護命令決定書又は警察が発行する警告等実施書面等のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
5 町長は、支援措置申出者の保護のため特別に必要があると認めた場合は、第3項各号に掲げる者に対し電話等により意見を聴取し、迅速に手続きを進めることができる。
(支援措置申出者が本人であることの確認書類等)
第23条 町長は、次に掲げる方法により支援措置申出者が本人であることを確認するものとする。
(1) 別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点提示し、又は提出する方法
(2) 前号によることができない場合、別表第2に掲げる書類のうちいずれか2点提示し、又は提出する方法
(4) 前各号によることができない場合、支援措置申出者の同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の出生の年月日等をいう。)について、口頭で陳述させること等により当該申出の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法
2 支援措置の申出を代理人により行おうとする者は、委任状(別記様式第12号)により町長にその旨を届け出なければならない。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。
3 児童相談所長又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4に規定する里親若しくは同法第7条に規定する児童福祉施設の長(以下「児童相談所長等」という。)は、前条第1項第3号に規定する者の代理人になることができるものとする。この場合において、町長は、児童相談所長等の出頭を求め、当該児童の監護等をしている事実を確認できる書類を提示させなければならない。
4 第1項の規定は、支援措置の申出を代理人により行う場合について準用する。
(支援措置の決定)
第24条 町長は、支援措置の実施を決定したときは、支援措置申出者に支援措置決定通知書(別記様式第13号)を送付するものとする。
(支援措置の内容)
第25条 町長は、支援措置申出者及び支援措置申出者と同一の住所を有する者であって支援措置申出者が支援措置の実施を求めた者(以下「支援対象者」という。)に対して、次の各号に定めるところにより支援措置を実施するものとする。
(1) 閲覧の請求及び申出(以下「請求等」という。)を受理したときは、町長が特別に認めたものを除き、支援対象者を除く請求等であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外又は抹消した閲覧用名簿を閲覧に供する。
(2) 支援対象者に係る住民票(消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写しの交付について、次のように取り扱うものとする。
ア 加害者が判明しており、加害者から請求等がなされた場合は、不当な目的があるものとして請求等を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。
イ 町長が特別に認めた場合を除き、支援対象者本人の代理人若しくは使者又は郵便等による請求等を拒否する。
(支援措置の期間)
第26条 支援措置の期間は、支援措置の実施を決定した日から起算して1年とする。
(支援措置の延長)
第27条 支援措置申出者は、町長に対し当該支援措置の期間が満了する日(以下「期間満了日」という。)の1月前から支援措置の延長の申出をすることができる。
2 町長は、期間満了日の1月前に当該支援措置申出者に支援措置終了予告通知書(別記様式第14号)を送付するものとする。
3 支援措置の延長の申出、支援措置申出者の本人確認並びに支援措置の決定、内容及び期間は、第22条から前条までの規定を準用する。
(申出書の内容の変更)
第28条 支援措置申出者は、申出書の内容に変更があったときは、町長に対し申出書を提出することができる。この場合において、支援措置申出者の本人確認等は、第23条の規定を準用する。
2 町長は、前項の規定による申出書の内容の変更を認めたときは、支援措置申出者に支援措置決定通知書を送付するものとする。
(支援措置の終了)
第29条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。
(1) 第26条(第27条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過し、かつ、第27条第1項の規定による支援措置の延長の申出がないとき。
(2) 支援措置申出者から支援措置終了申出書(別記様式第15号)の提出があったとき。
(3) その他町長が当該支援措置を実施する必要がないと認めたとき。
2 支援措置申出者は、前項第2号の規定による申出を行う場合、町長に第23条第1項に掲げる方法により、支援措置申出者本人であることを明らかにしなければならない。
3 町長は、第1項の規定により支援措置の終了を決定したときは、支援措置終了通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。
(他の市区町村長との連携)
第30条 町長は、支援措置申出者が他の市区町村における支援を併せて希望する場合は、申出書の写し(延長及び変更を含む)を当該市区町村長に送付しなければならない。
2 町長は、他の市区町村長が支援措置を決定した者の支援措置申出書等の送付を受けたときは、この規則に基づく支援措置の申出がなされたものとして取り扱うものとする。
(住民票コードの変更請求に係る提出書類)
第31条 住民票コードの記載の変更請求を行う者(以下「変更請求者」という。)は、町長に対し住民票コード記載変更請求書(別記様式第17号)を提出するものとする。
(変更請求者が本人であることの確認書類)
第32条 規則第9条の2第1号に規定する町長が適当と認めるものは、次に掲げる方法とする。
(1) 別表第1に掲げる書類のうちいずれか1点提示し、又は提出する方法
(2) 前号によることができない場合、別表第2に掲げる書類のうちいずれか2点提示し、又は提出する方法
2 規則第9条の2第2号に規定する町長が適当と認める書類は、住民票コード記載変更請求に係る照会書(別記様式第18号)とする。
3 町長は、法第30条の4第4項の規定により住民票コードを変更した場合は、変更請求者に対し住民票コード通知票(別記様式第19号)を送付するものとする。
(住民票コード通知票の再交付)
第33条 住民票コード通知票の再交付を請求する者(以下「再交付請求者」という。)は、住民票コード通知票再交付請求書(別記様式第20号)を提出するものとする。
2 再交付請求者が本人であることの確認は、第23条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「支援措置申出者」とあるのは「再交付請求者」と、同項第4号中「申出」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
3 町長は、住民票コードの再交付を認めるときは、再交付請求者に対し住民票コード通知票を送付するものとする。
附 則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規則第36号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第39条の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条、第21条、第23条、第27条、第28条、第32条、第33条関係)
個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書及び合格証明書で本人の写真を貼り付けたもの
別表第2(第6条、第10条、第13条、第16条、第19条、第21条、第23条、第27条、第28条、第32条、第33条関係)
国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書又はその他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
別表第3(第6条、第10条、第13条、第16条、第19条、第21条、第23条、第27条、第28条、第32条、第33条関係)
学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国、地方公共団体の機関が発行した資格証明書(別表第1に掲げる書類を除く。)で、写真を貼り付けたもの若しくは金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)第2条に規定する金融機関等が、同法第3条に規定する預貯金契約の締結等の取引において発行した預貯金通帳その他の当該取引に係る書類又はその他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
別記様式第1号(第4条関係)
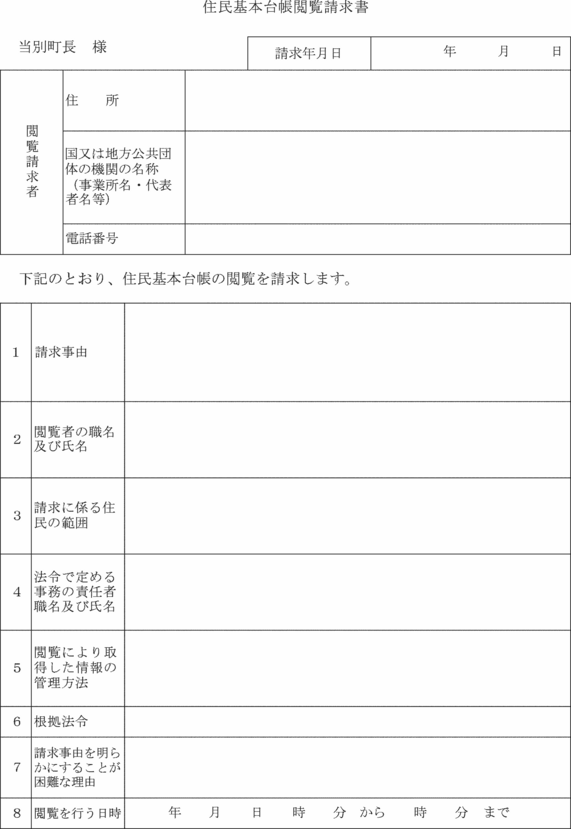
別記様式第2号(第5条関係)
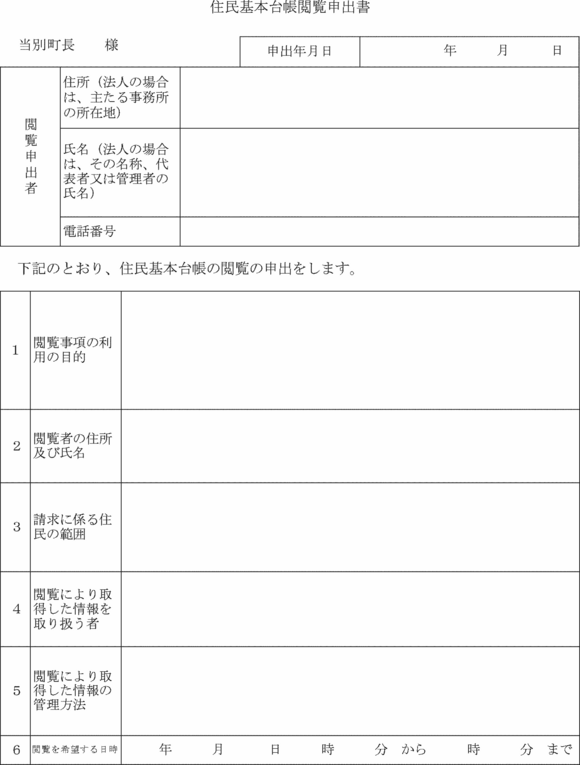
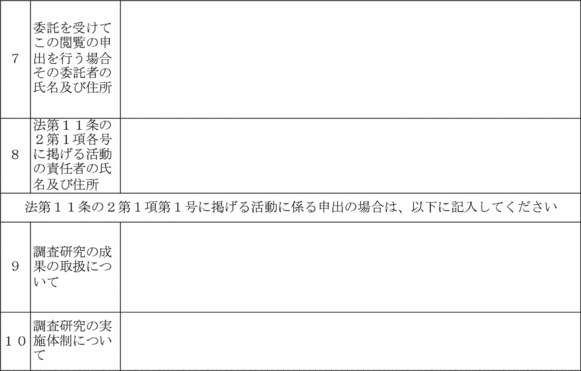
別記様式第3号(第5条関係)
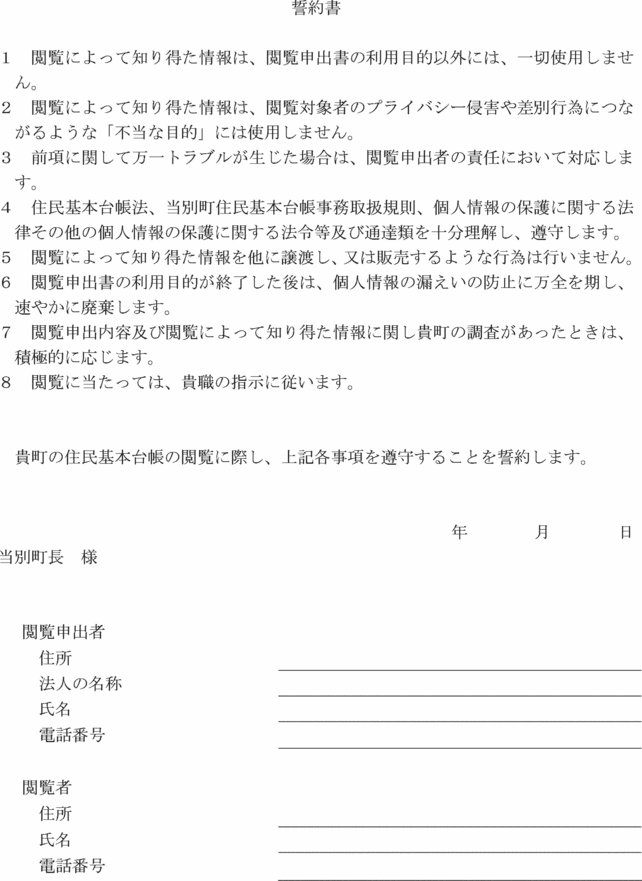
別記様式第4号(第5条関係)
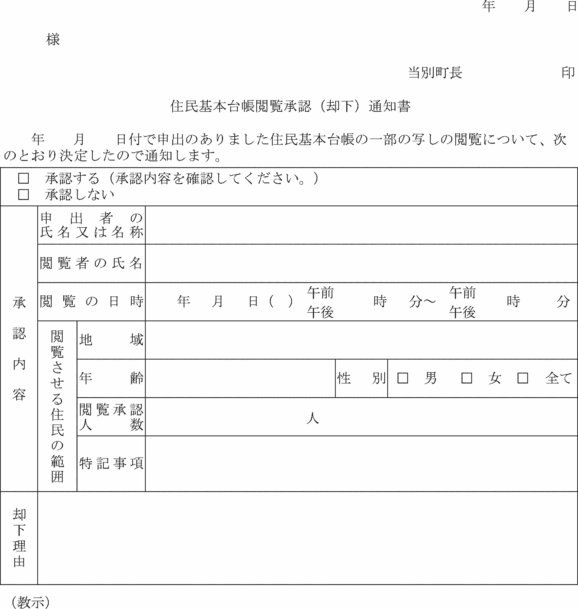
別記様式第5号(第6条関係)
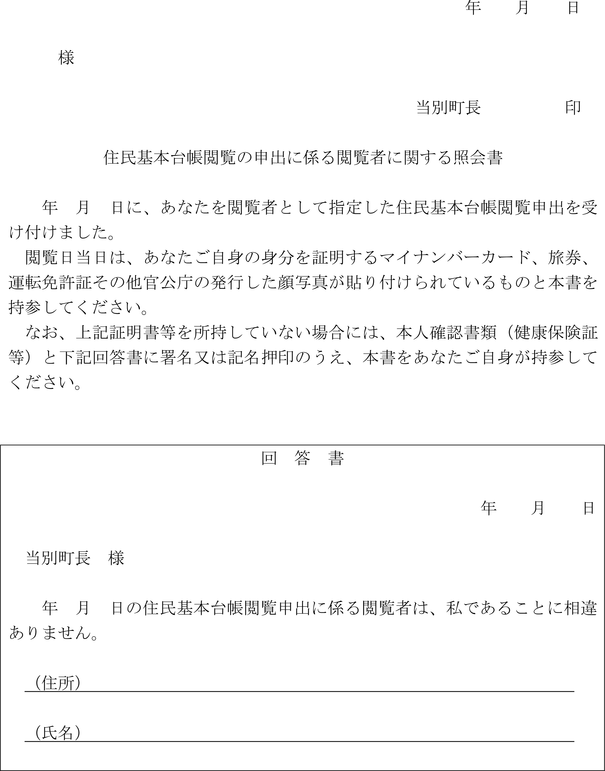
別記様式第6号(第9条、第12条関係)
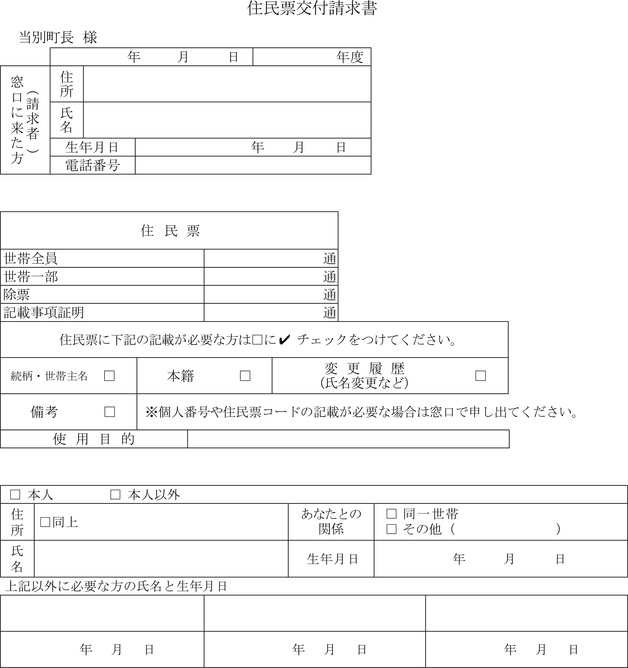
別記様式第7号(第14条関係)
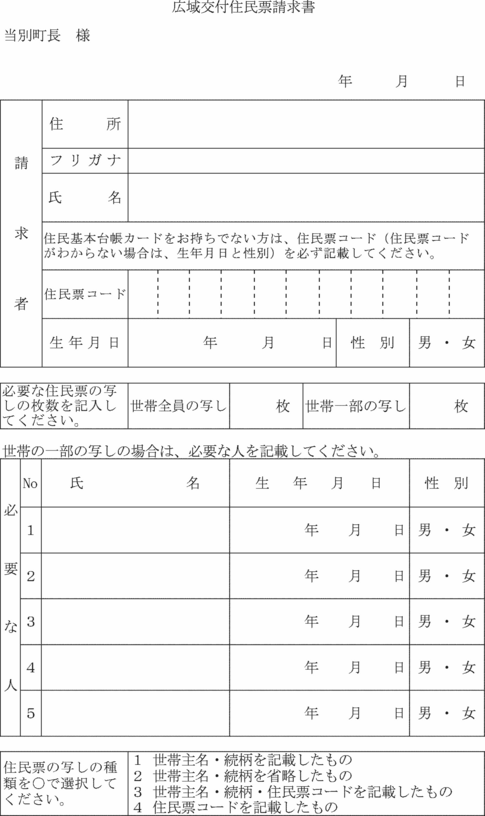
別記様式第8号(第15条、第18条関係)
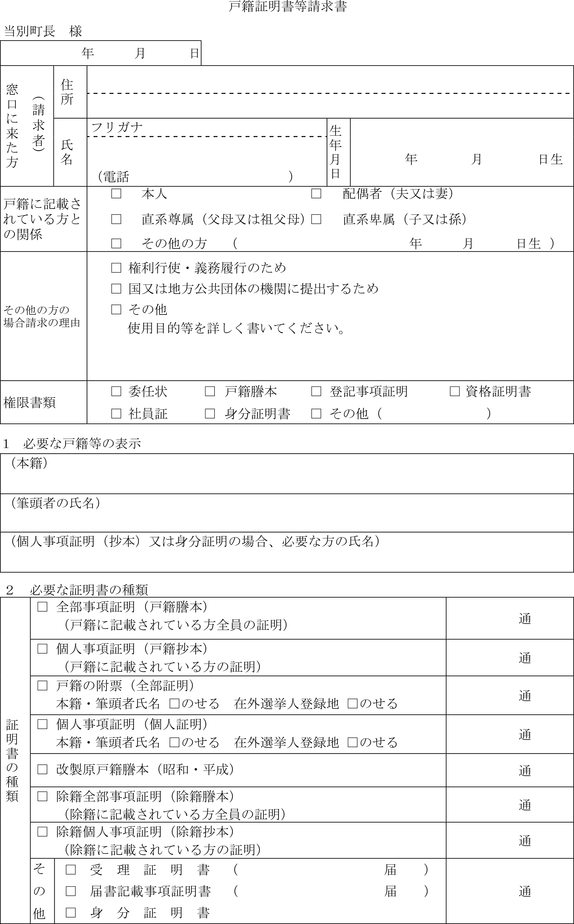
別記様式第9号(第20条関係)
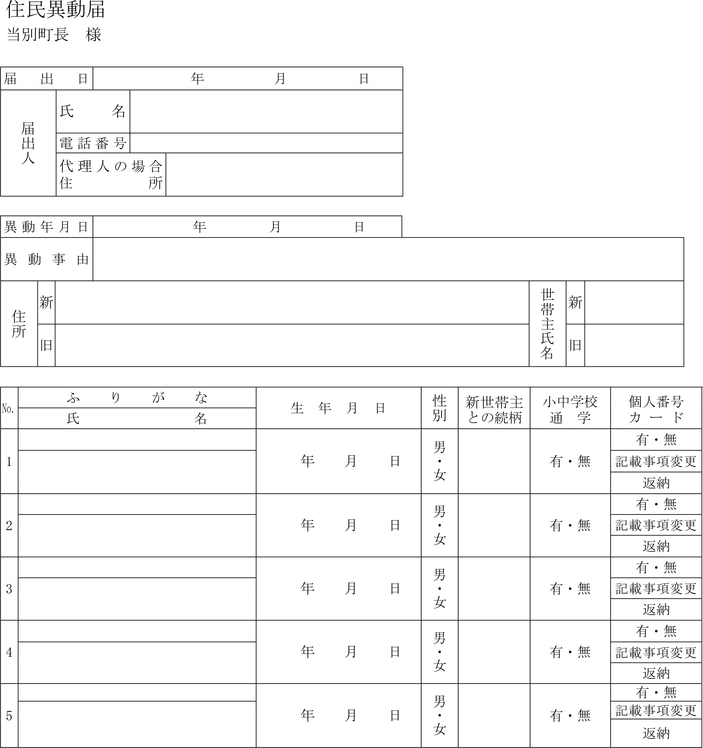
別記様式第10号(第21条関係)
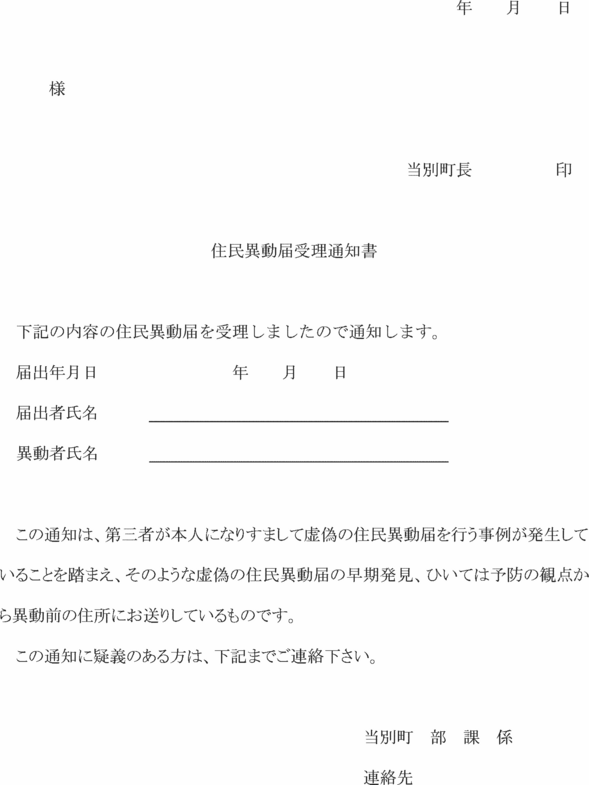
別記様式第11号(第22条、第27条、第28条、第30条関係)
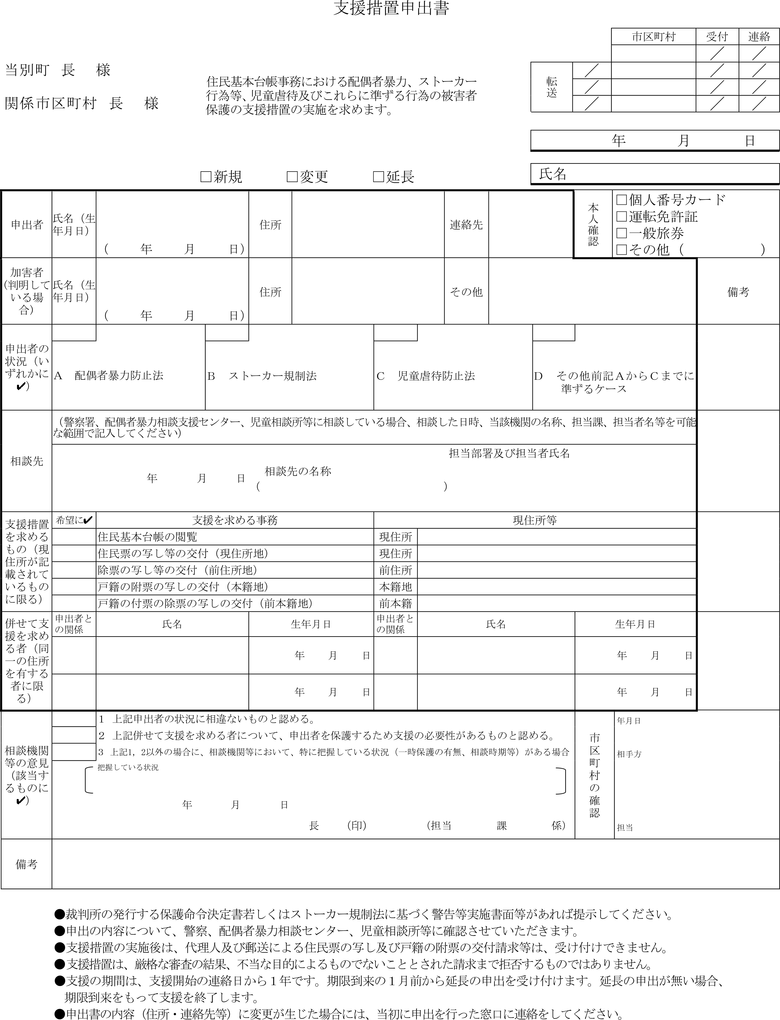
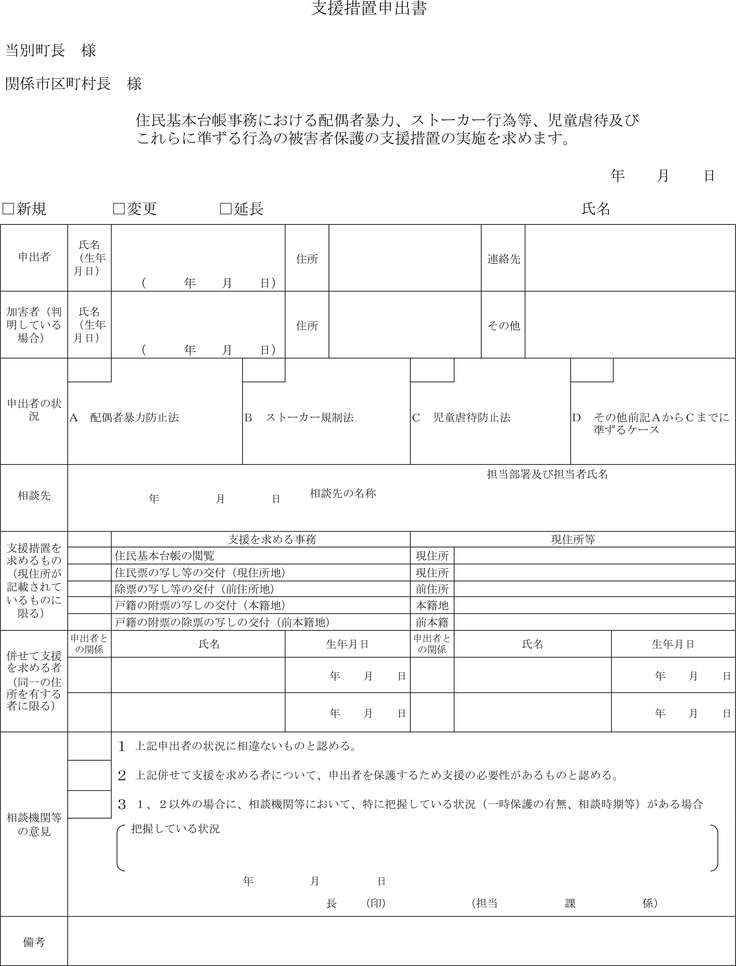
別記様式第12号(第23条関係)
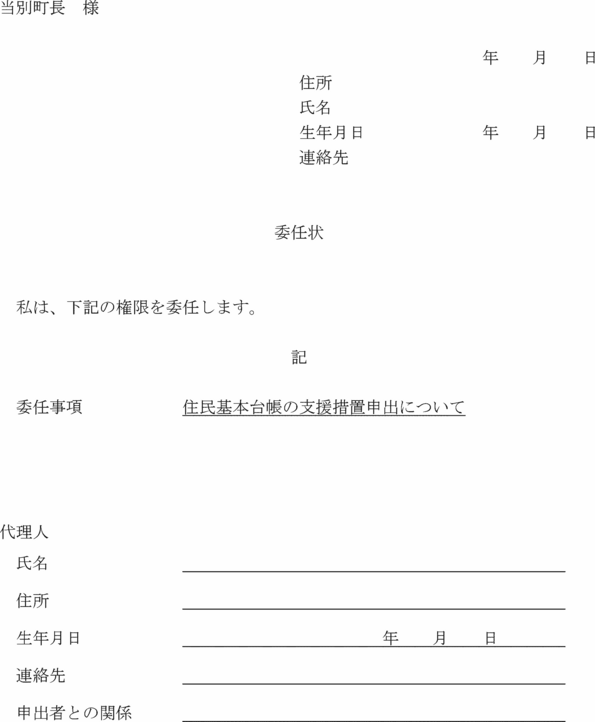
別記様式第13号(第24条、第27条、第28条関係)
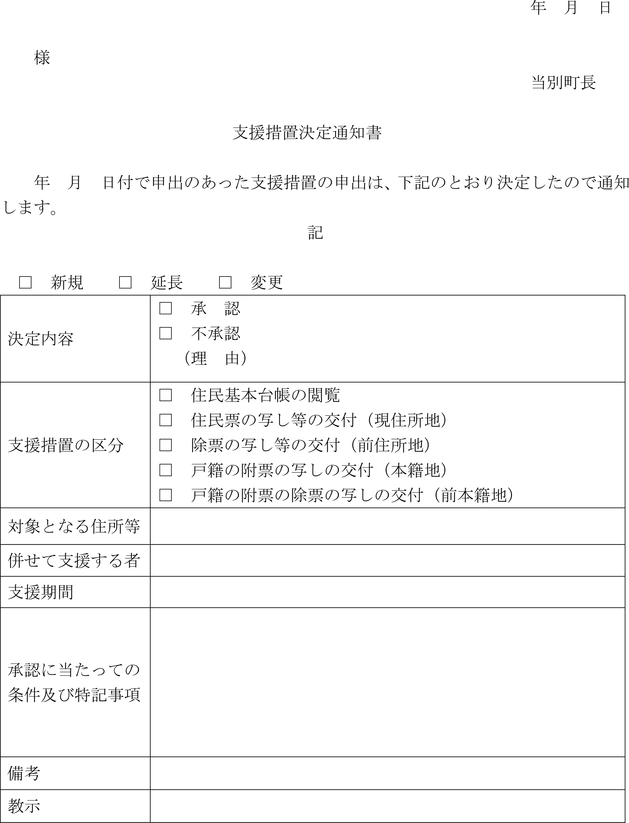
別記様式第14号(第27条関係)
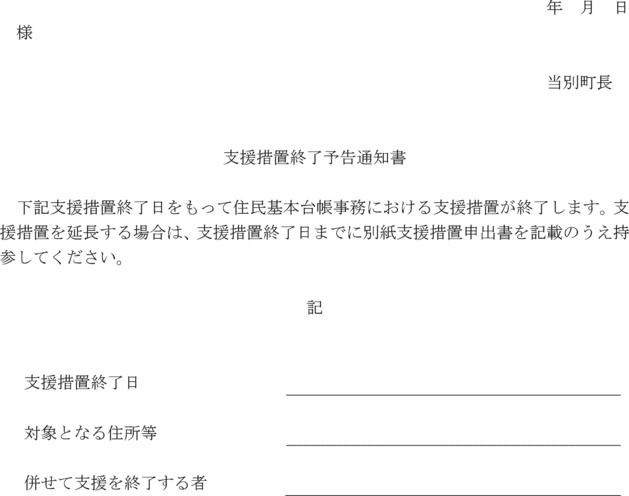
別記様式第15号(第29条関係)
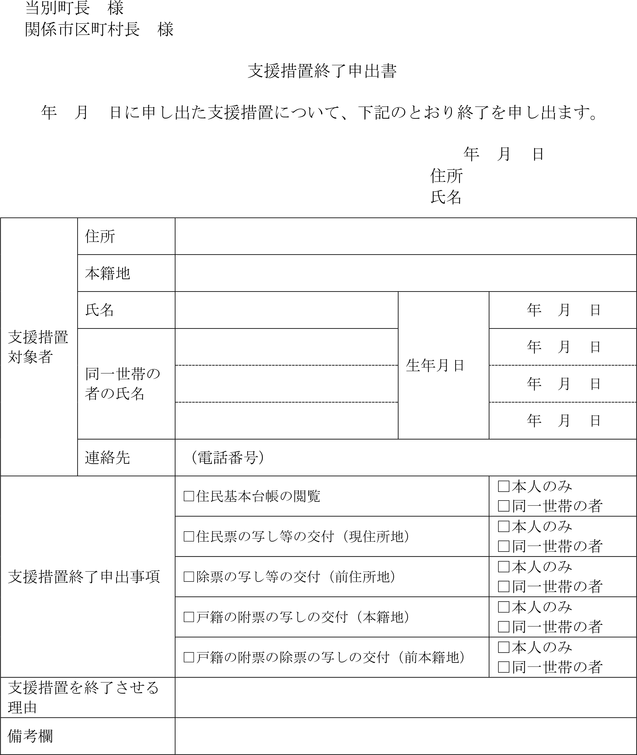
別記様式第16号(第29条関係)
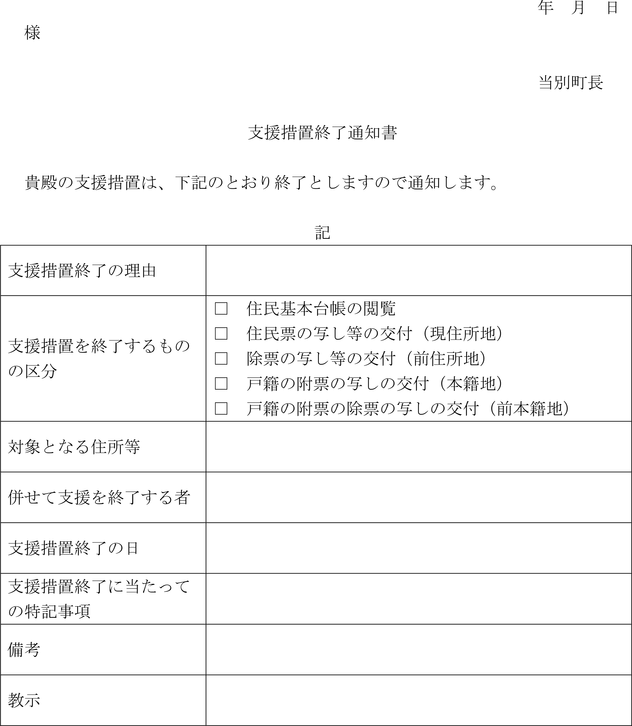
別記様式第17号(第31条関係)
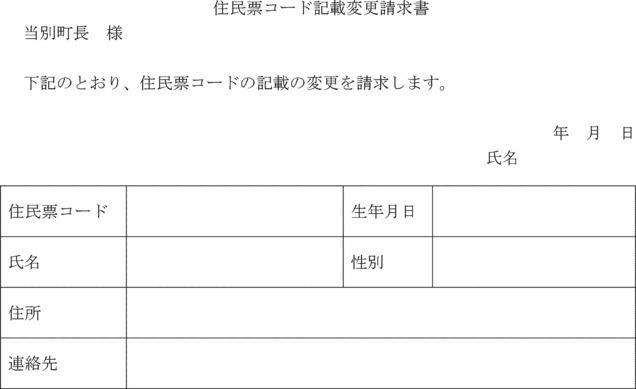
別記様式第18号(第32条関係)
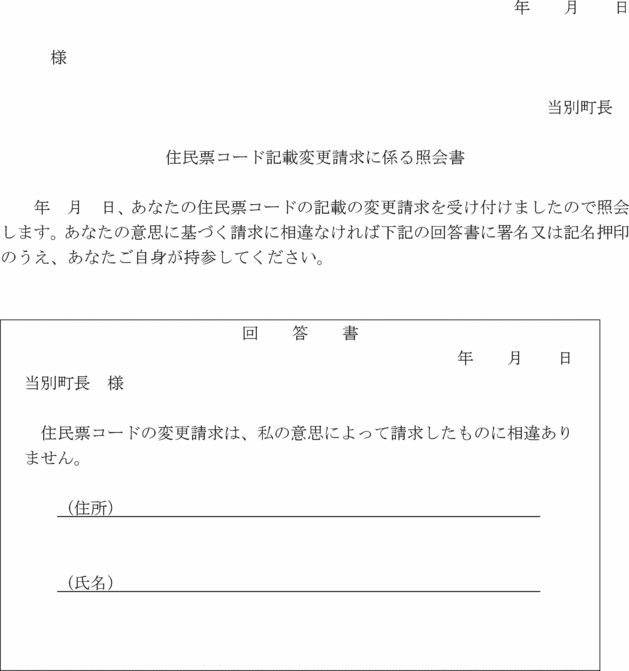
別記様式第19号(第32条及び第33条関係)
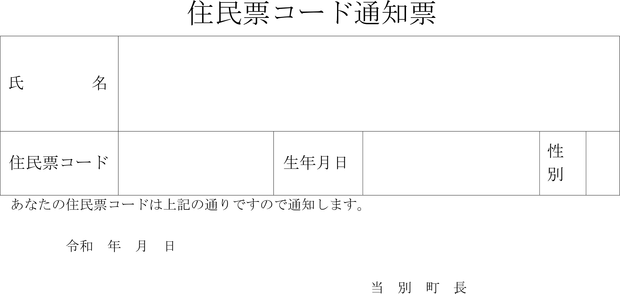
別記様式第20号(第33条関係)
