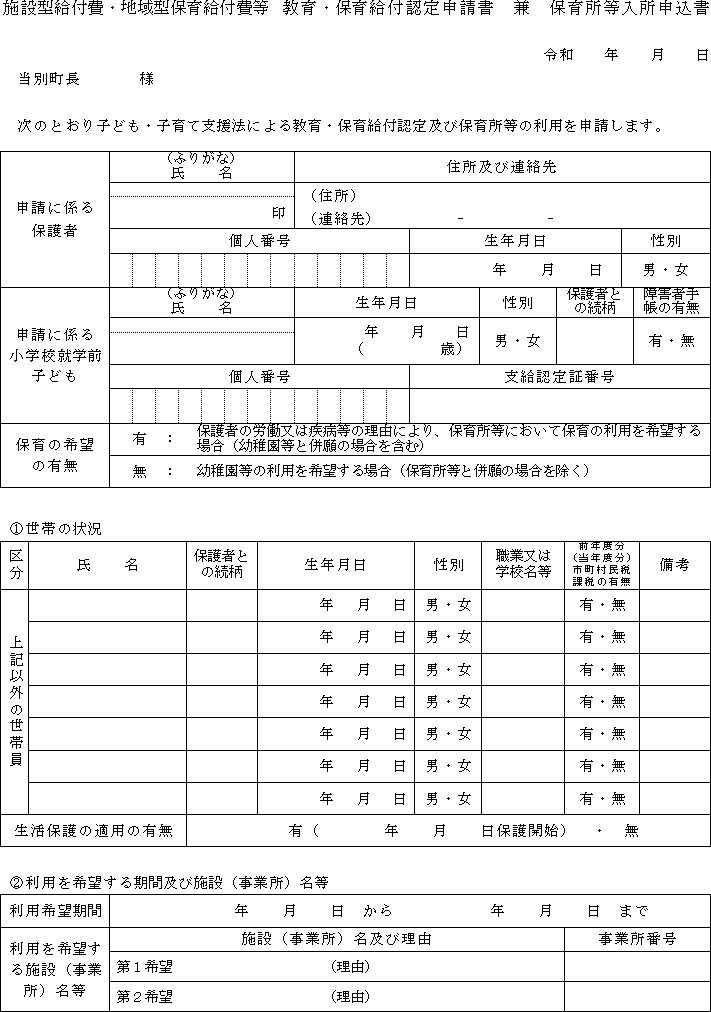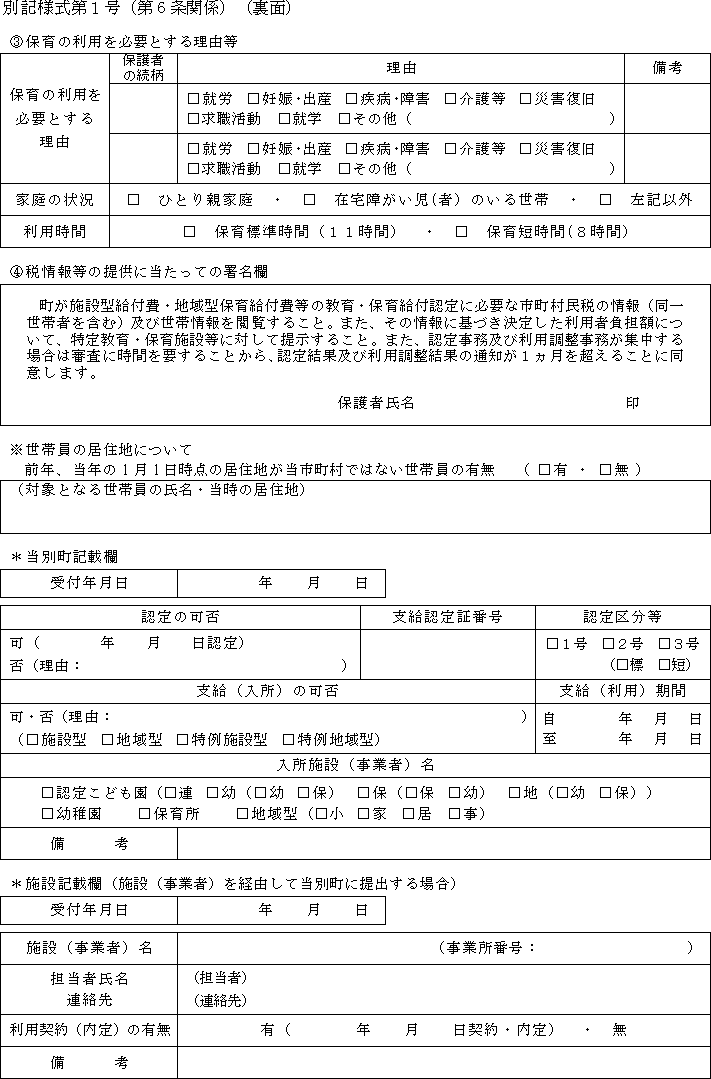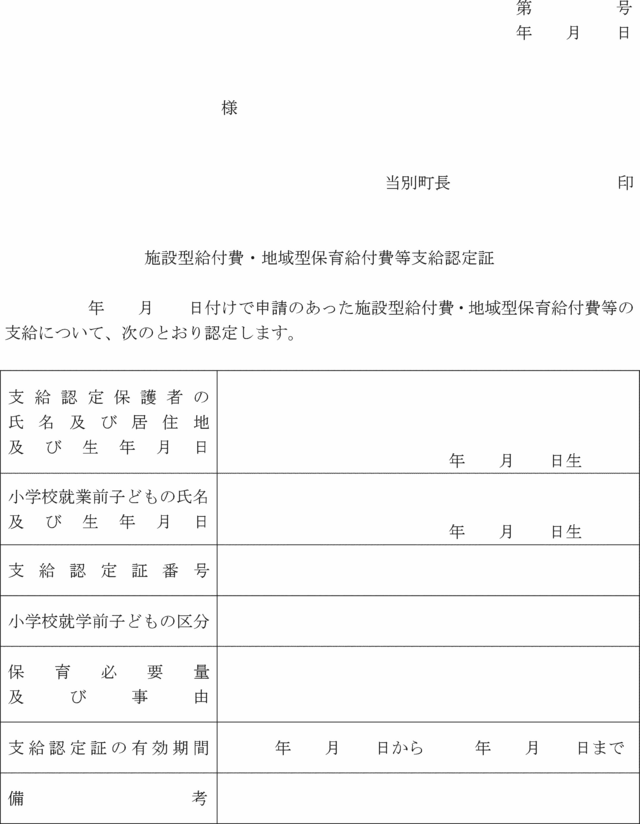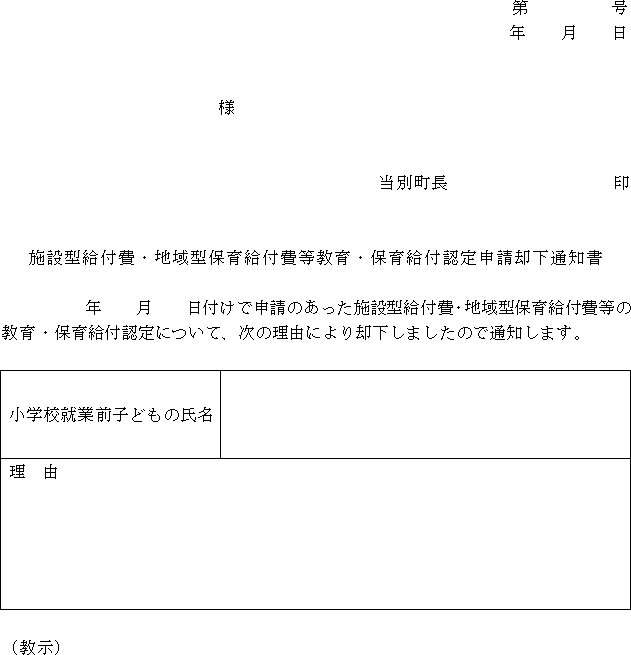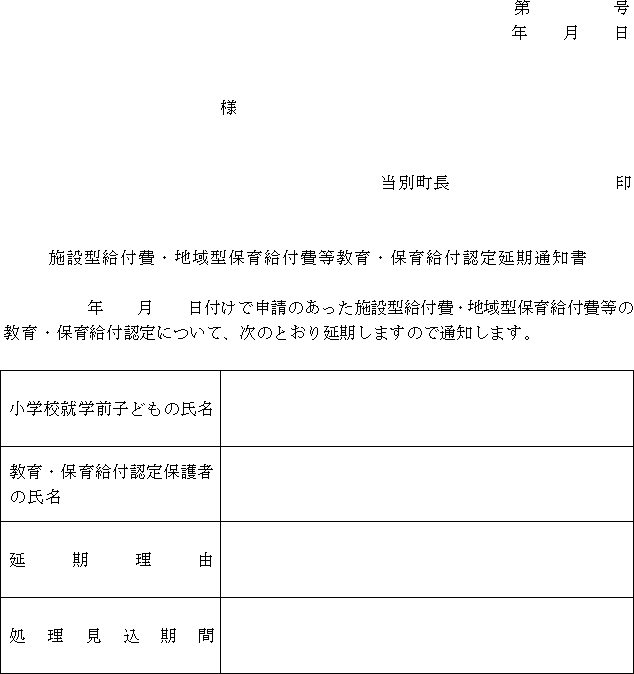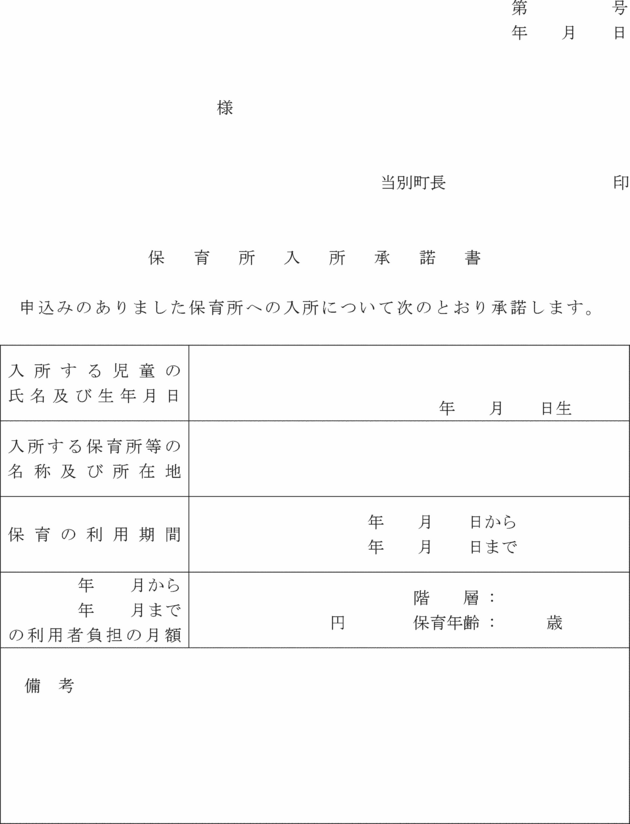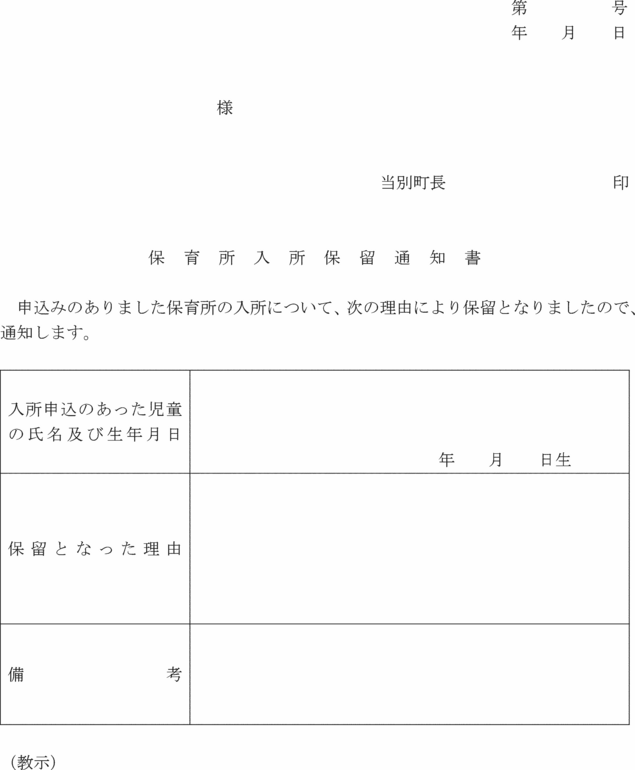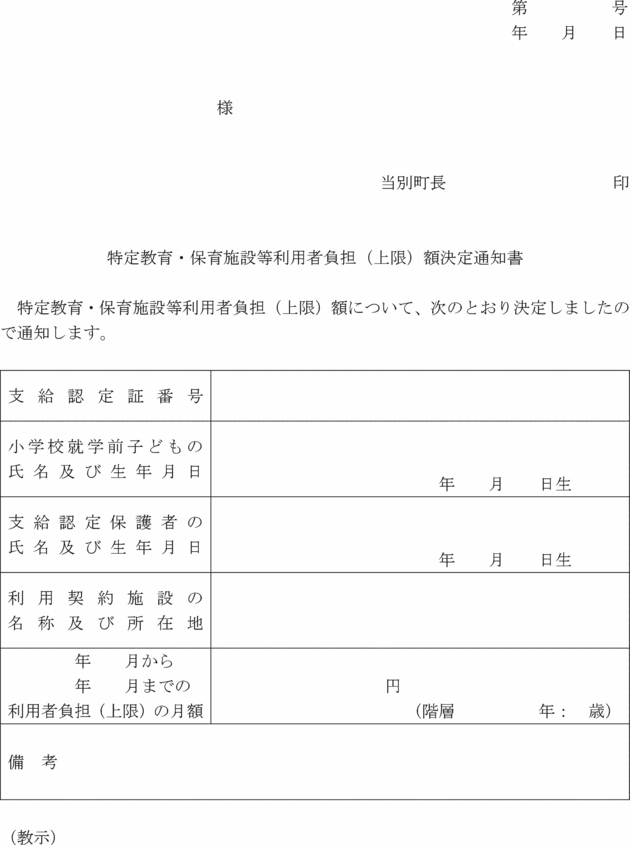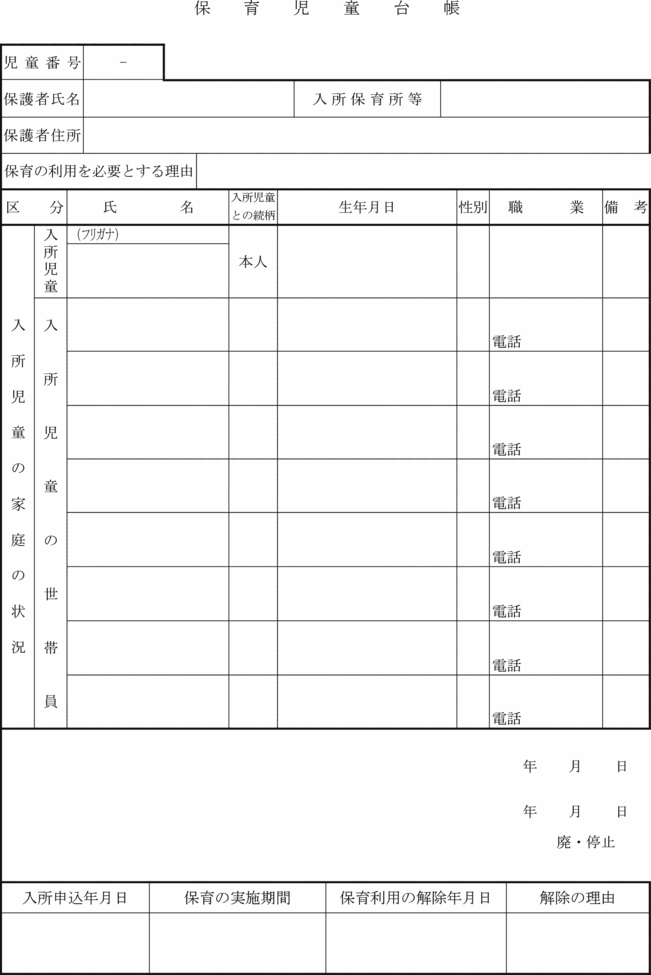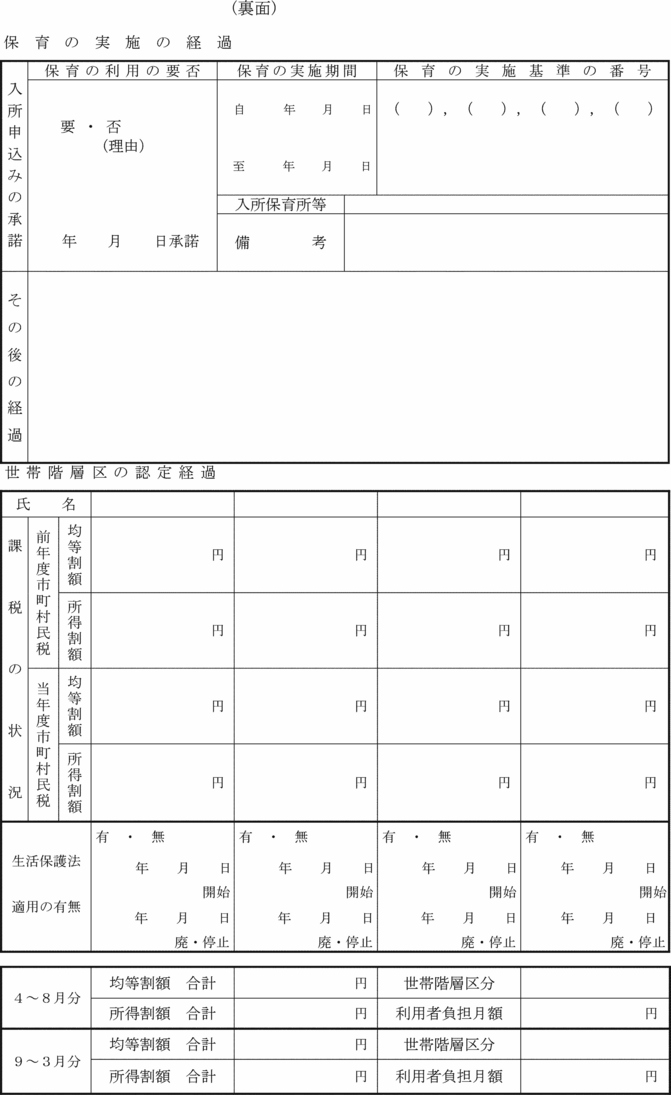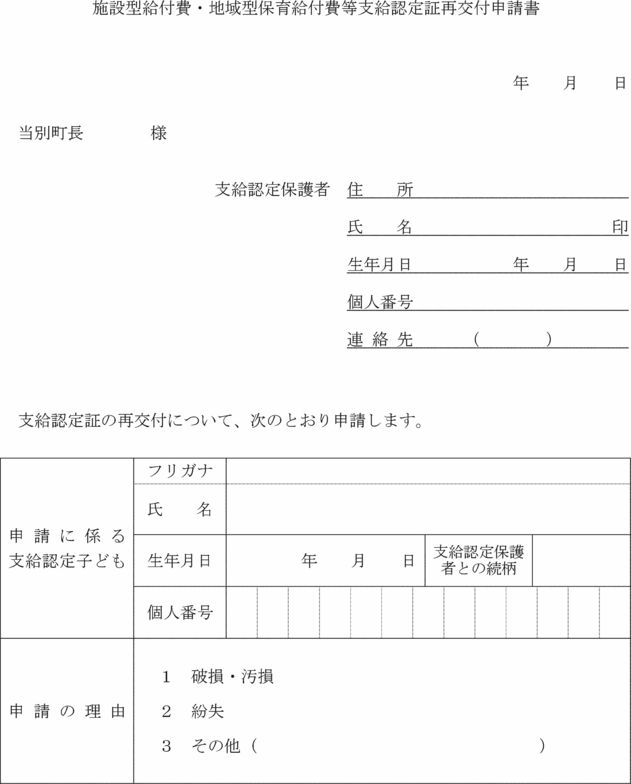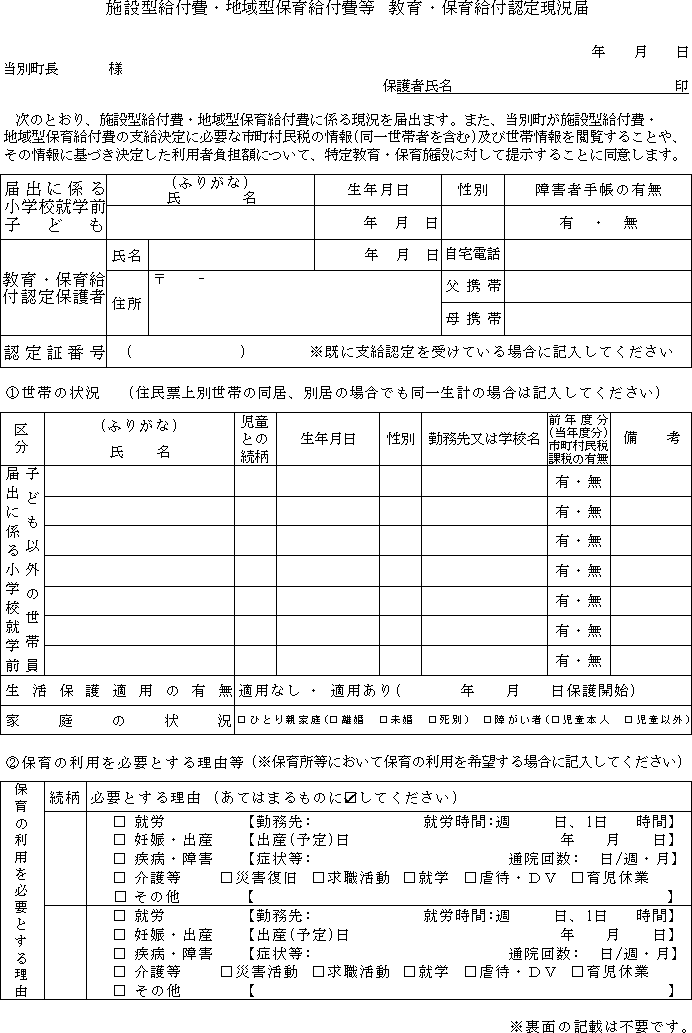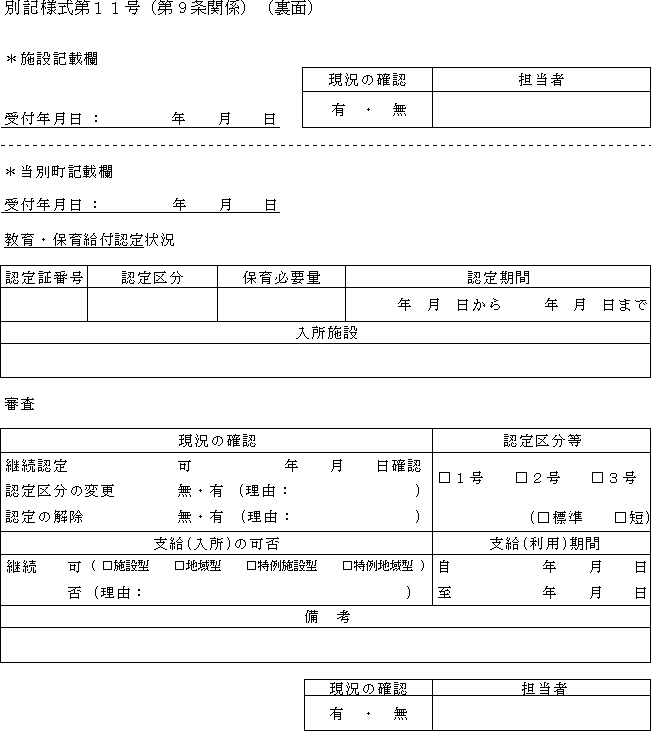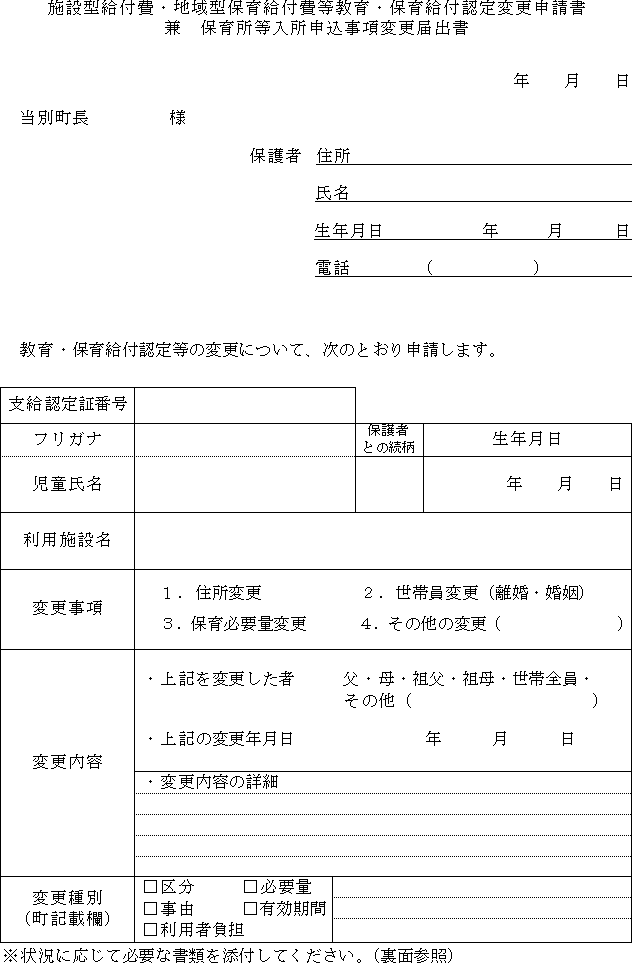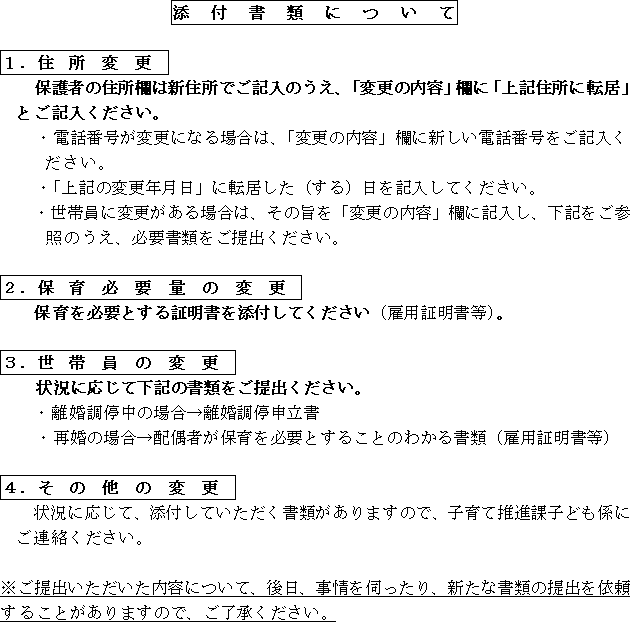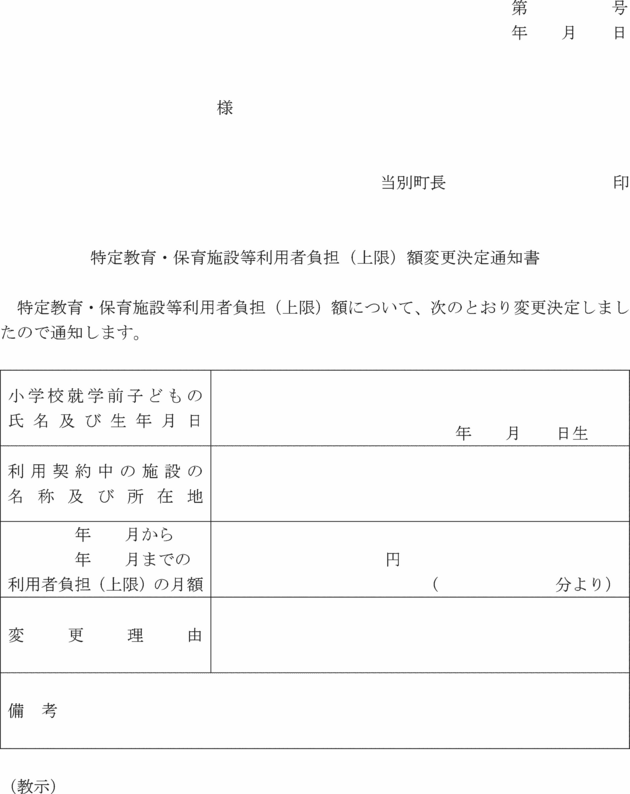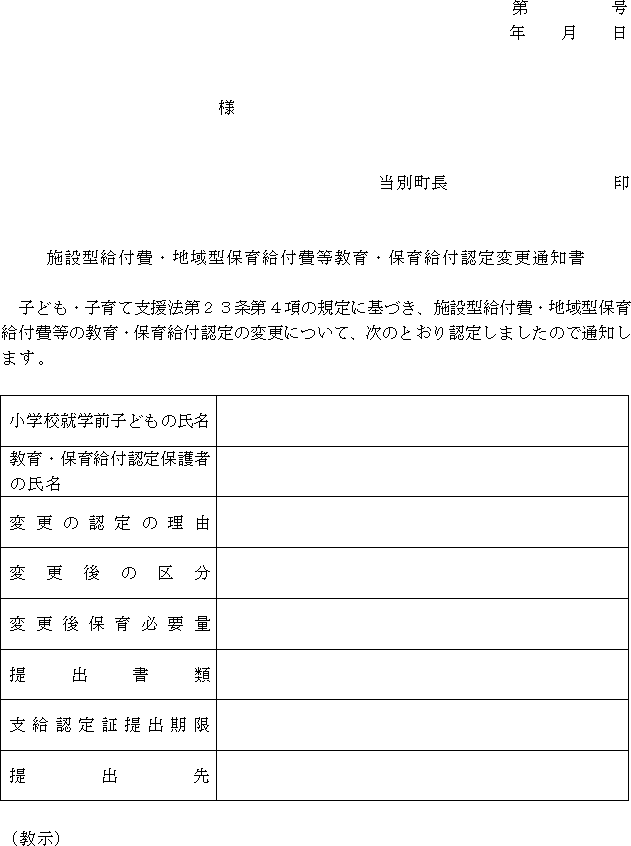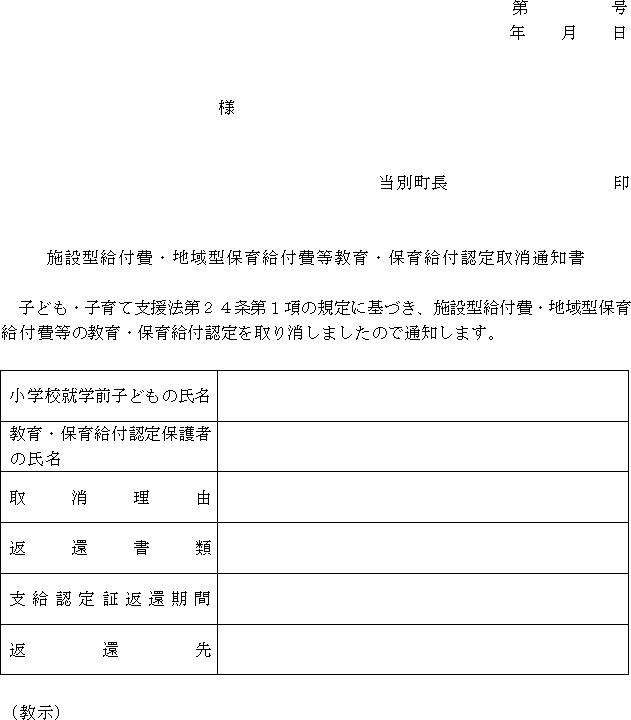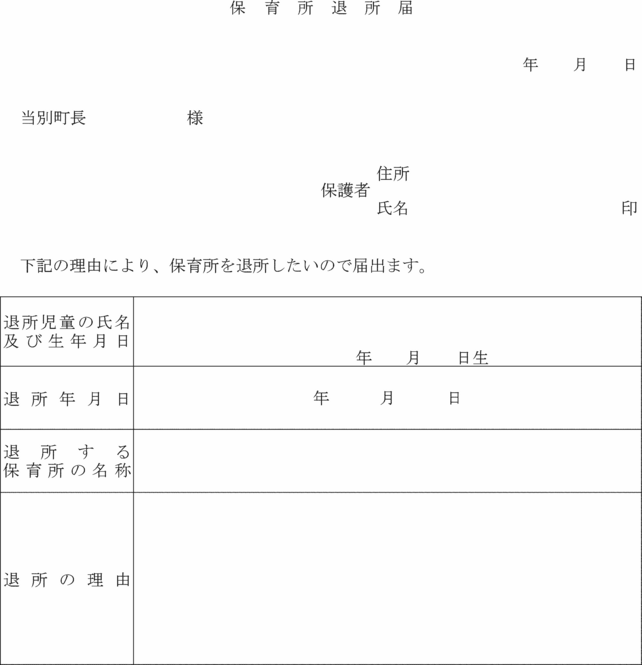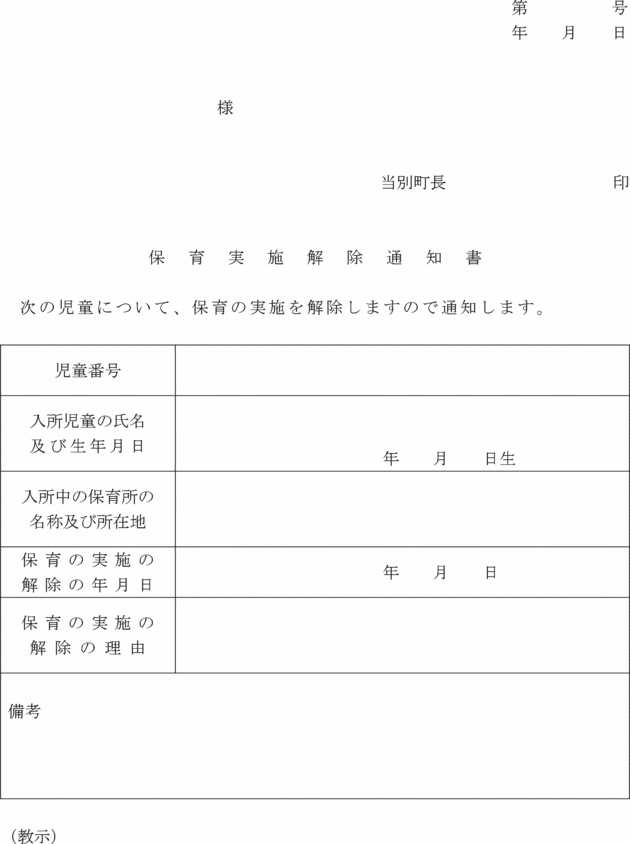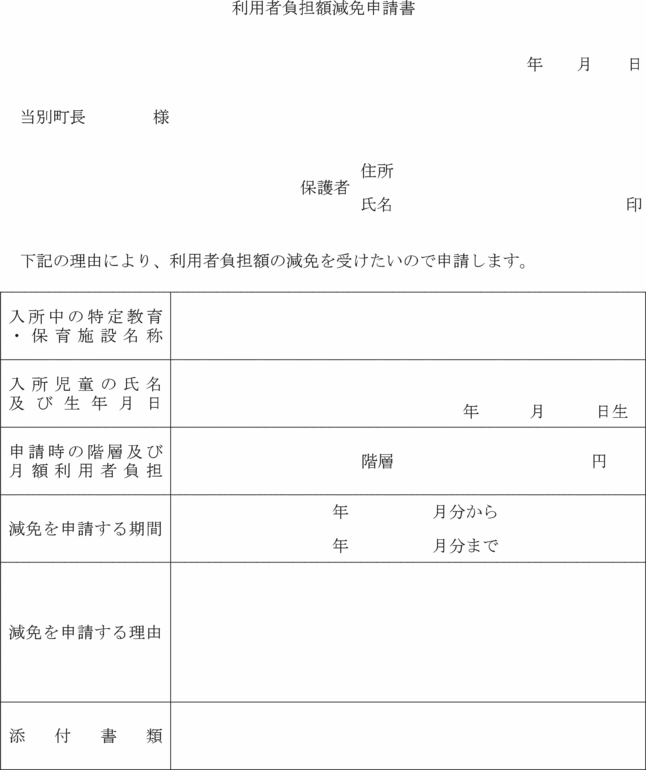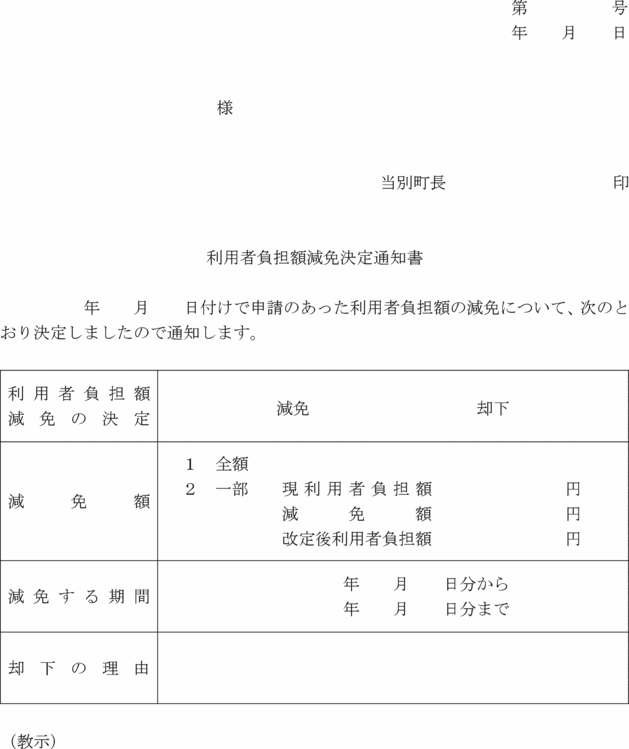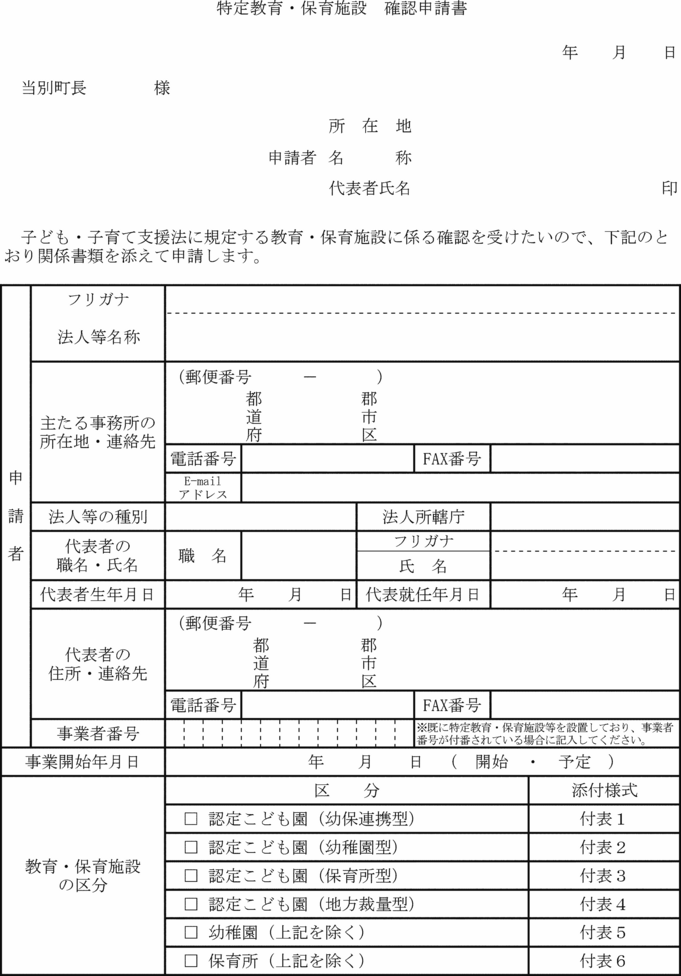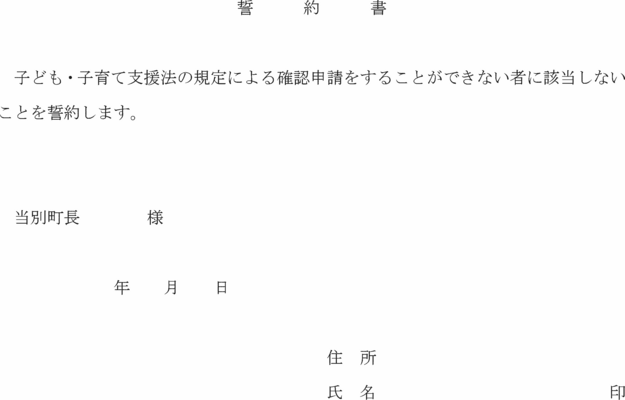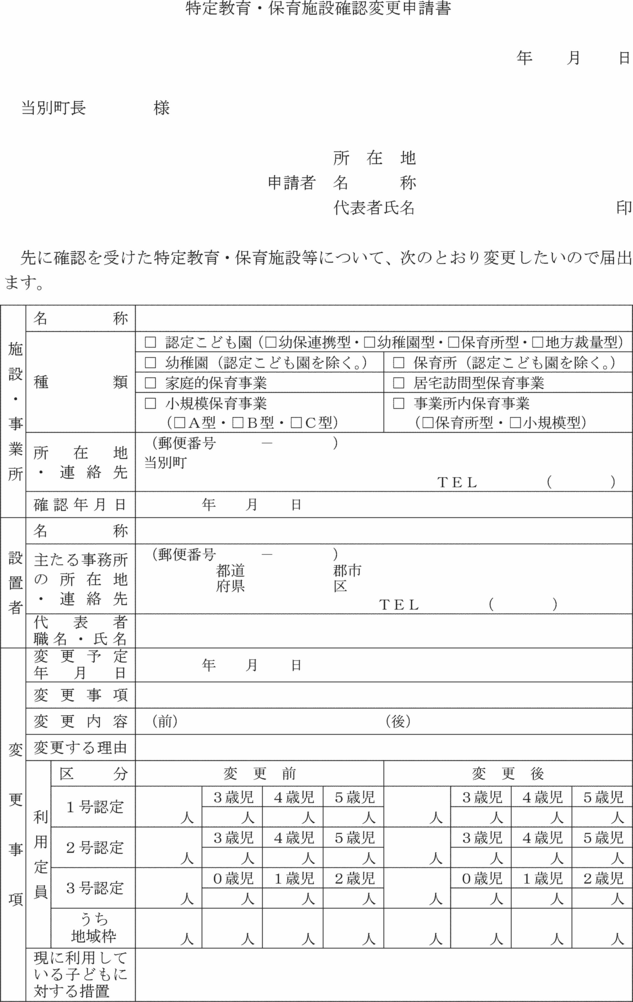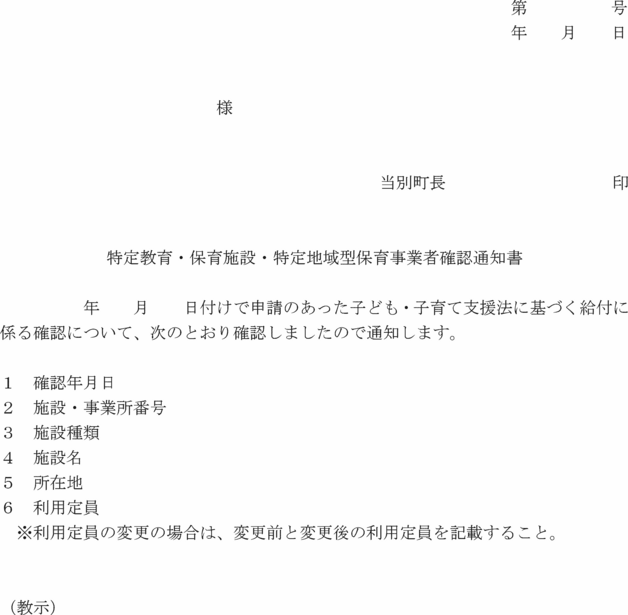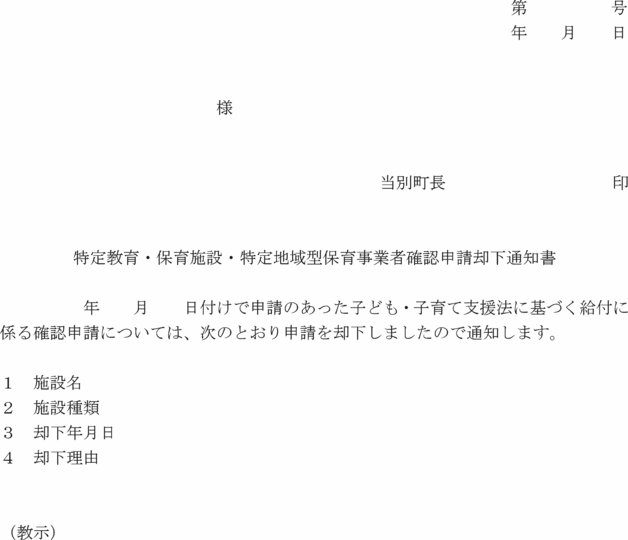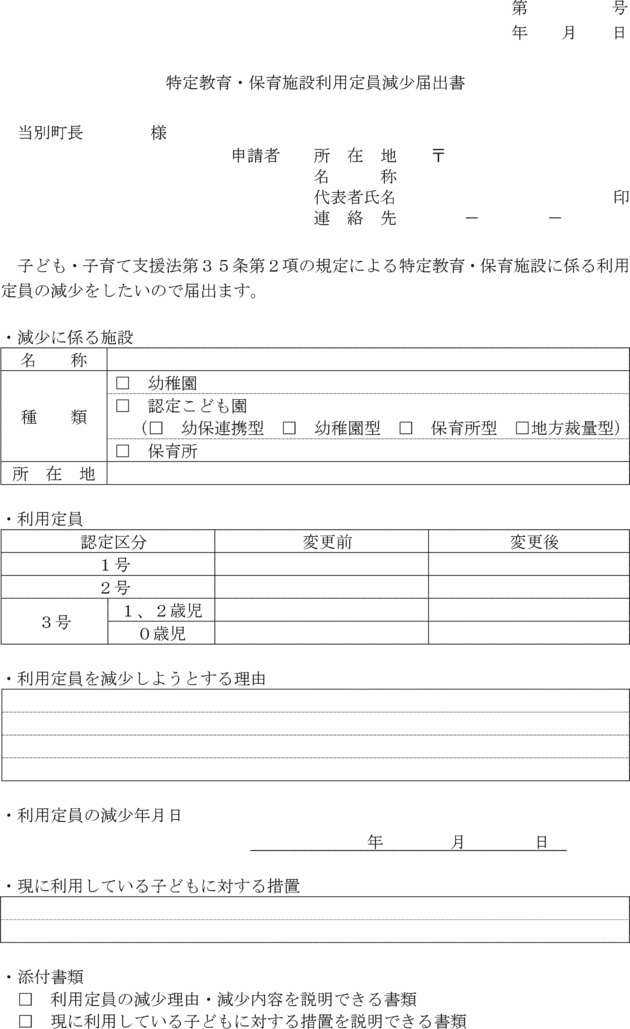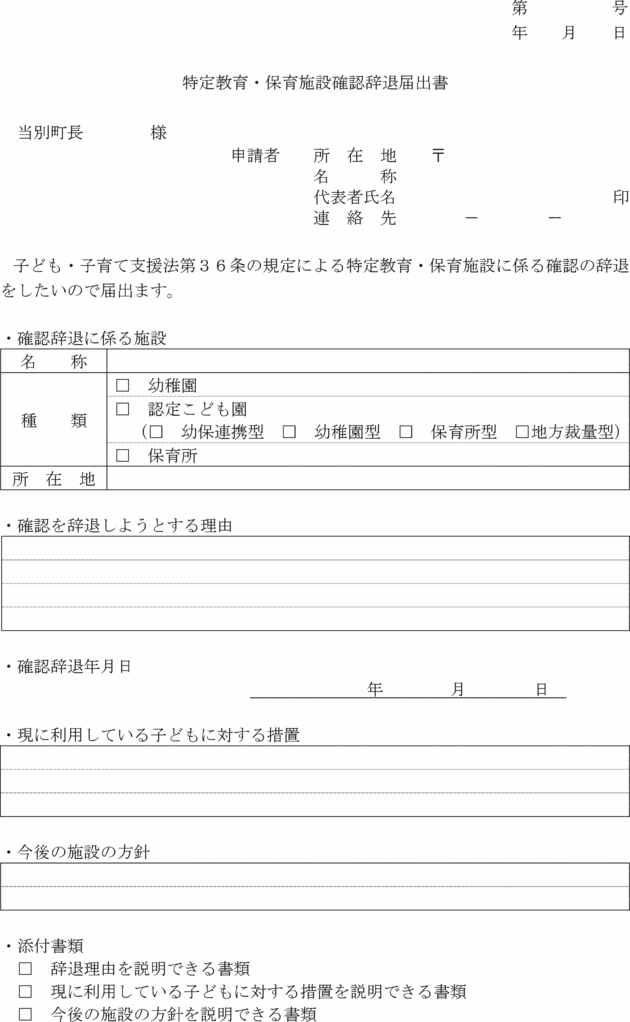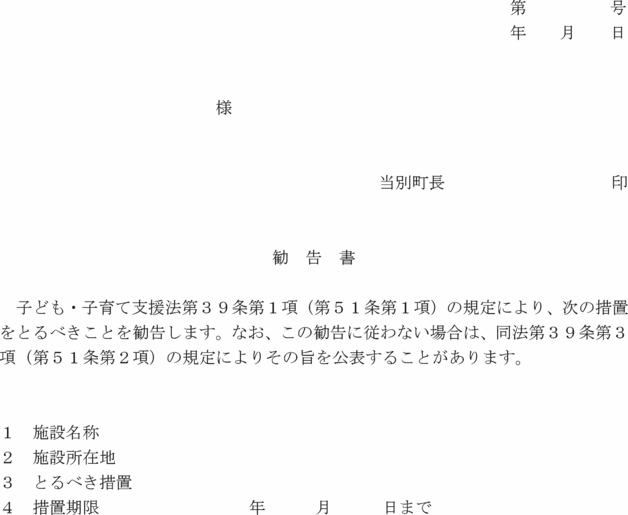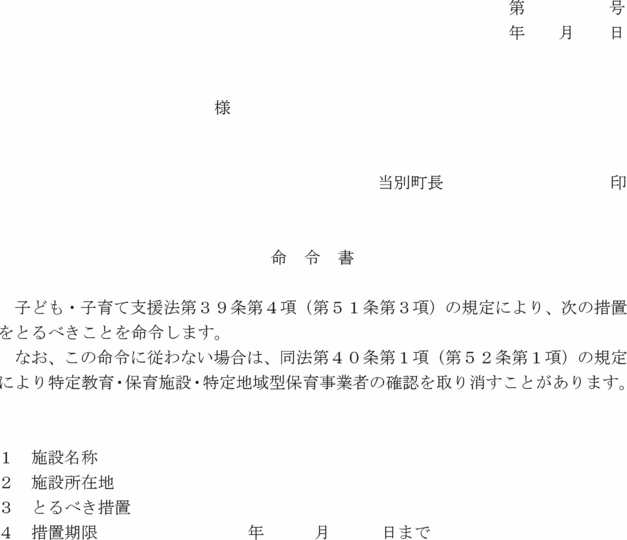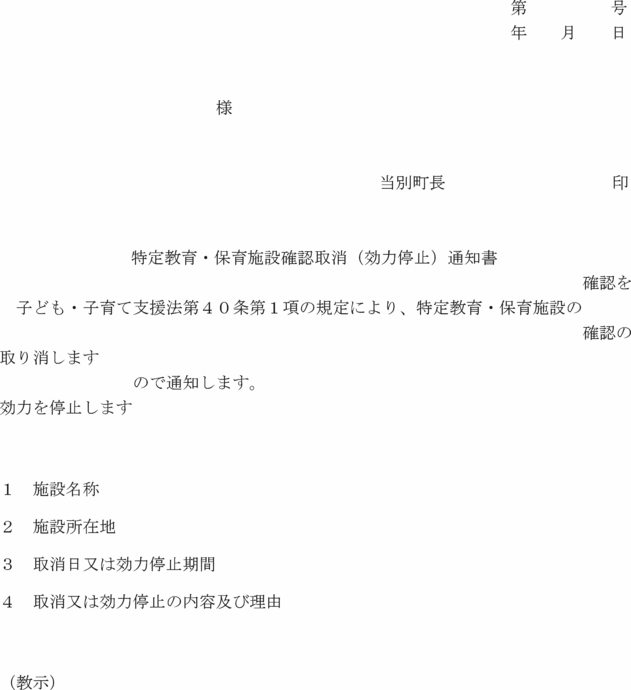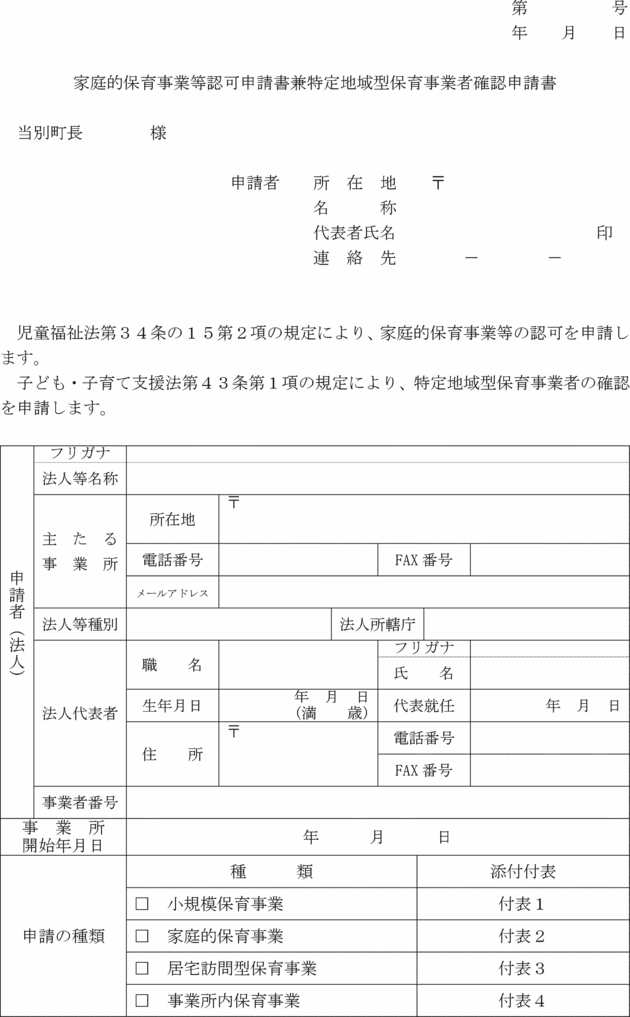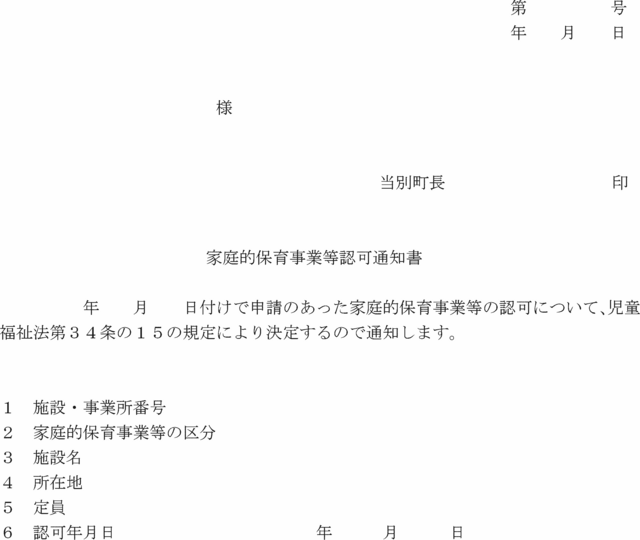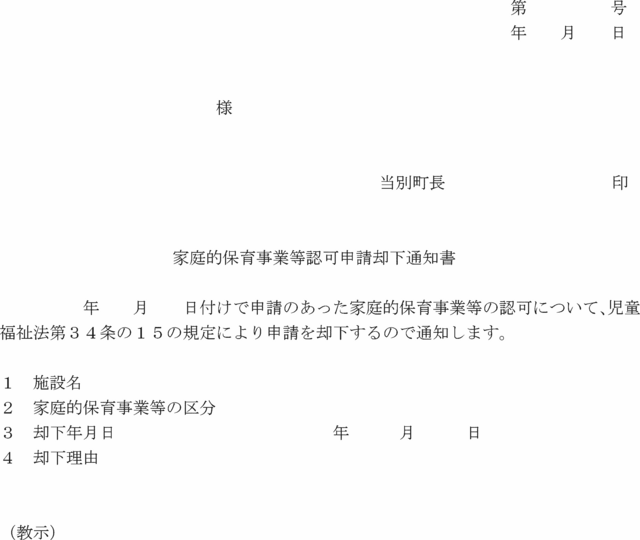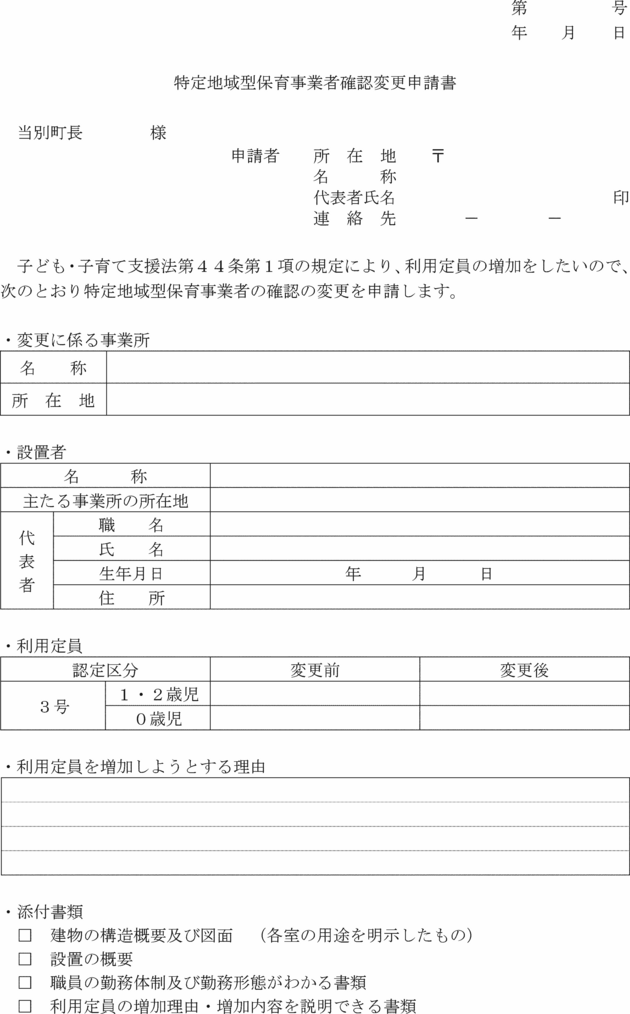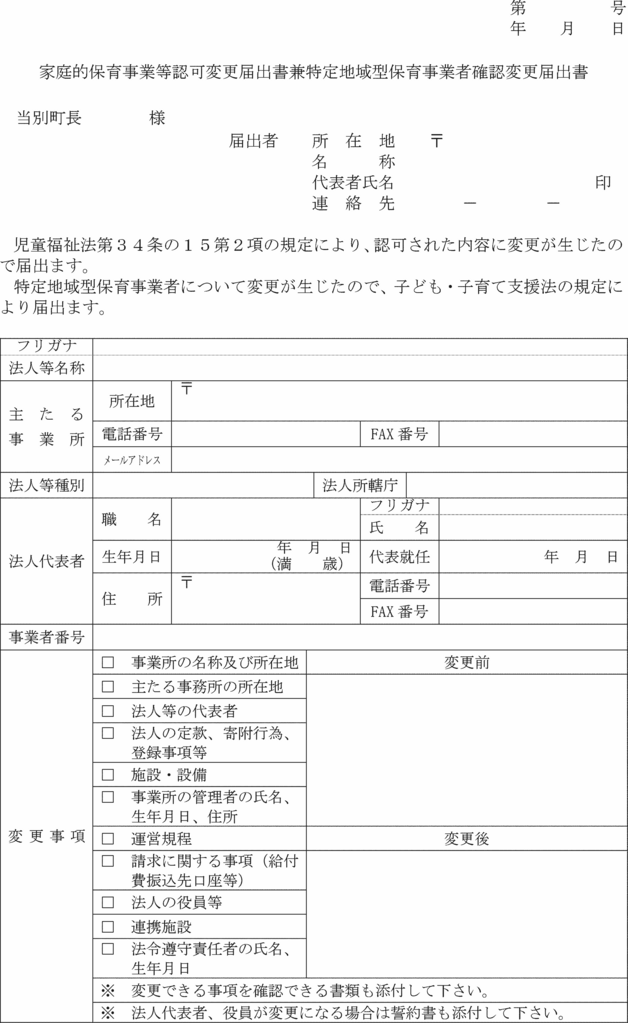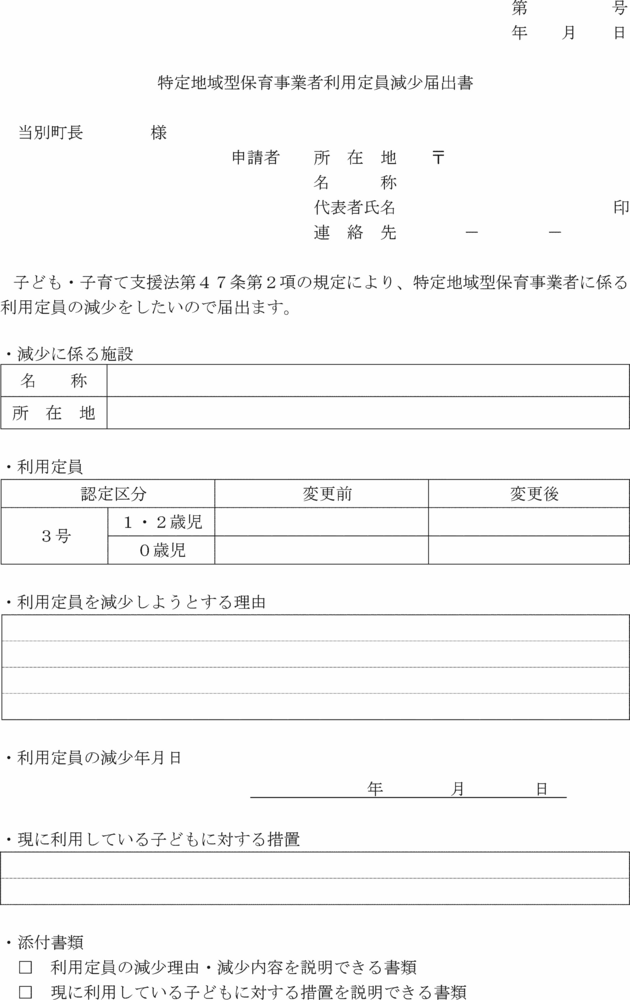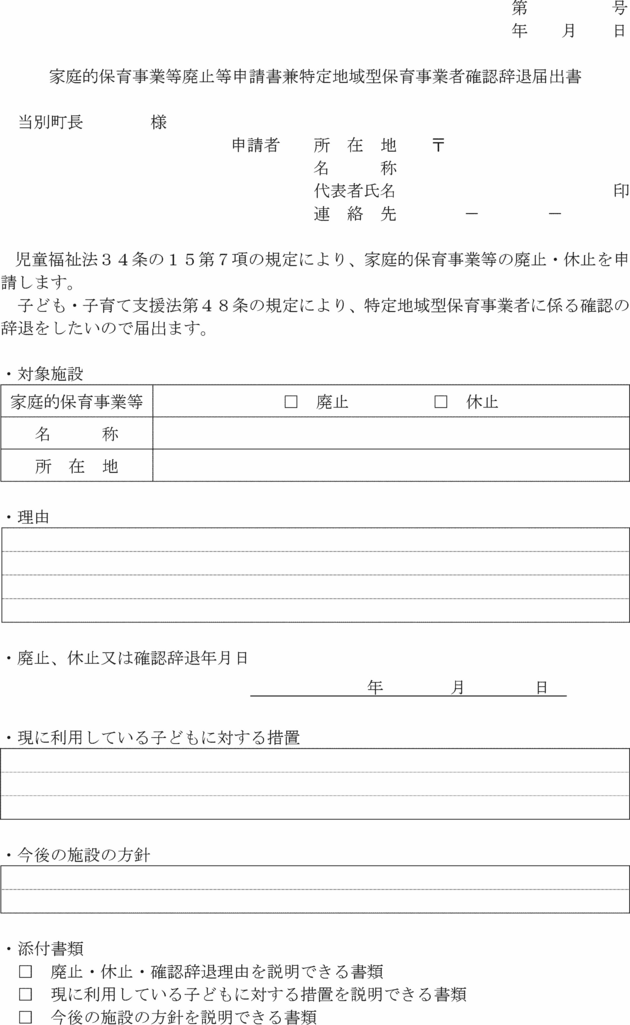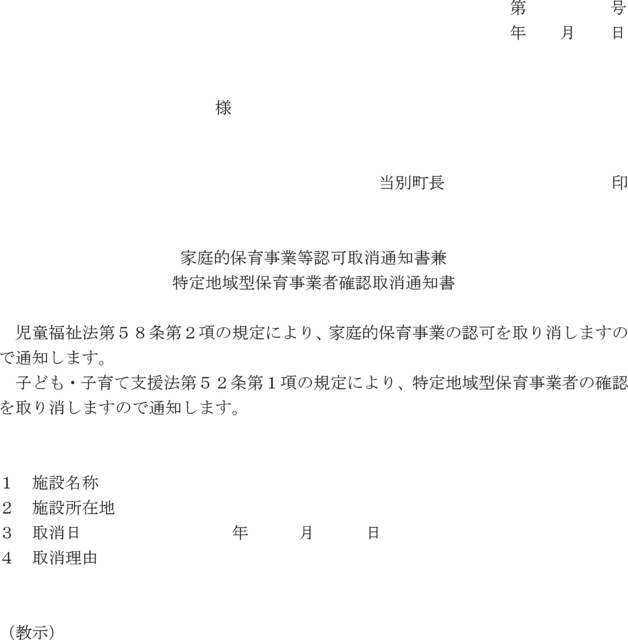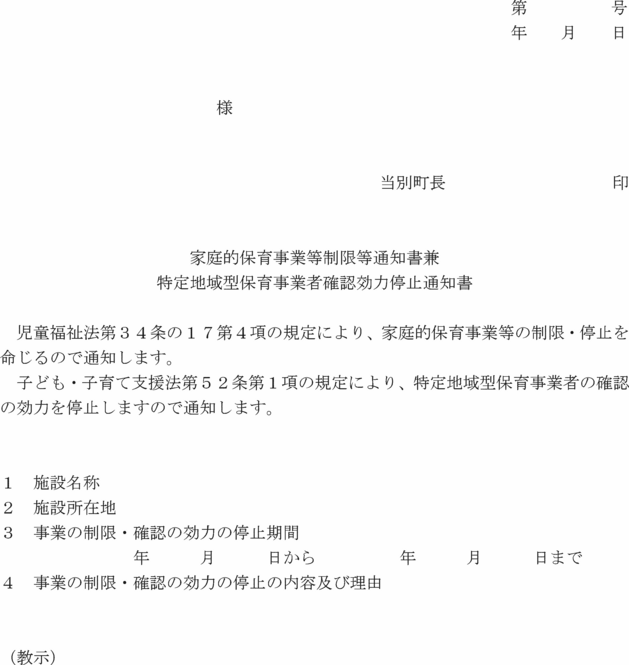○当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則
平成27年3月30日規則第49号
当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則
当別町保育の実施に関する条例施行規則(平成21年当別町規則第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 教育・保育給付認定等(第3条―第17条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(第18条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、
当別町保育に関する条例(平成26年条例第27号。以下「保育条例」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他の支援法及び児童福祉法の規定により制定された法令及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、支援法及び児童福祉法並びにこれらに基づき制定された法令及び条例において使用する用語の例による。
2 前項に規定するもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 1号認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち同法第19条第1号に該当するものをいう。
(2) 2号認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち同法第19条第2号に該当するものをいう。
(3) 3号認定子ども 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち同法第19条第3号に該当するものをいう。
第2章 教育・保育給付認定等
(保育の認定に必要な労働時間)
(優先利用の事由)
第4条 保育条例第7条の規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。
(利用者負担の額)
第5条 支援法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(支援法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する市町村が定める額及び
保育条例第9条に規定する利用者負担の額として規則で定める額(以下「利用者負担額」という。)は、
別表1及び
別表2に定めるとおりとする。
(教育・保育給付認定申請及び保育所の入所申込みに係る手続)
第6条 保育条例第3条の規定による保育の認定を受けようとする者又は保育所の入所の申込みをしようとする者(保育の認定の申請及び保育所の入所の申込みを同時に行う者を含む。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書(
別記様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、支援法第20条第3項の規定により認定するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(
別記様式第2号。以下「支給認定証」という。)を交付し、申込書を提出した者に対し通知しなければならない。
3 町長は、支援法第20条第5項の規定により教育・保育給付認定の申請を却下するときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(
別記様式第3号)により、申込書を提出した者に対し、その理由を付し、通知しなければならない。
4 町長は、支援法第20条第6項の規定により教育・保育給付認定の申請に対する処分を延期しようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定延期通知書(
別記様式第4号)により、申込書を提出した者に対し通知しなければならない。ただし、同条第1項の申請に係る事務が特定の時期に集中し審査に時間を要する場合であって、当該申請をした者に対し一律に延期する旨を通知するときは、町長が別に定める様式によることができる。
第7条 町長は、児童福祉法第24条第3項の規定による利用の調整を行ったときは、利用調整結果通知書(
別記様式第5号)により教育・保育給付認定保護者(支援法第20条第4項に規定するものをいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に、それぞれ通知しなければならない。
2 町長は、保育所の入所を適当と認めるときは、保育所入所承諾書(
別記様式第6号)により、保育所の入所を不適当と認めるときは、保育所入所保留通知書(
別記様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該保育所に通知しなければならない。
3 町長は、第6条第2項の通知をするときは、特定教育・保育施設等利用者負担(上限)額決定通知書(
別記様式第8号)により教育・保育給付認定保護者に利用者負担額又は利用者負担上限額(以下「利用者負担額等」という。)を通知するとともに、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、それぞれ利用者負担額等を通知しなければならない。
4 町長は、保育所に入所する児童について、保育児童台帳(
別記様式第9号)を作成しなければならない。
(支給認定証の再交付の申請)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、支援法施行規則第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請を行うときは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(
別記様式第10号)を町長に提出するものとする。
(現況の届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、支援法第22条の規定による届け出をしようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(
別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(教育・保育給付認定の変更の申請)
第10条 教育・保育給付認定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼保育所等入所申込事項変更届出書(
別記様式第12号)を提出しなければならない。
(1) 支援法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の申請をするとき。
(2) 支援法施行規則第15条第1項の規定により申請内容の変更の届け出をするとき。
2 町長は、支援法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の申請があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、教育・保育給付認定証を交付し、当該申請をした者に対し通知しなければならない。
3 町長は、第7条第3項により現に決定した利用者負担額等を変更するときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、特定教育・保育施設等利用者負担(上限)額変更決定通知書(
別記様式第13号)により、利用者負担額等を通知するとともに、当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に対し、それぞれ利用者負担額等を通知しなければならない。
(職権による支給認定の変更)
第11条 町長は、支援法第23条第4項の規定に基づき職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(
別記様式第14号)により、教育・保育給付認定保護者に対し通知しなければならない。
(支給認定の取消)
第12条 町長は、
保育条例第8条の規定により教育・保育給付認定の取消しを行うときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(
別記様式第15号)により、教育・保育給付認定保護者に対し通知しなければならない。
(保育所の退所)
第13条 保育所を利用している児童の保護者は、当該児童を保育所から退所させようとするときは、保育所退所届(
別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、
保育条例第6条の規定に該当することとなった児童を保育所から退所させることができる。
3 町長は、前2項に該当することとなった児童を保育所から退所させるときは、保育実施解除通知書(
別記様式第17号)により、当該児童の保護者に対し通知しなければならない。
(利用者負担額等の算定等)
第14条 利用者負担額等は、次の各号に掲げる月分をそれぞれ当該各号で定める年度の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する個人の市町村民税をいう。以下同じ。)により算定する。
(1) 各年度の4月分から8月分まで 当該年度の前年度の市町村民税
(2) 各年度の9月分から3月分まで 当該年度の市町村民税
2 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の世帯に属する教育・保育給付認定子ども(1号認定子どもに限る。)の利用者負担額等は、市町村民税非課税世帯と同様とする。
(1) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童福祉法第6条の4第2項に規定する養育里親
(3) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、情緒障害短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長
3 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(2号認定子ども及び3号認定子どもに限る。)の利用者負担額等は、無料とする。
(1) 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に該当する教育・保育給付認定保護者の世帯に属するもの
(2) 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)のうち第2子以降に該当するもの
4 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合の月の利用者負担額等については、次項に定める日数を基礎として日割りによって計算した額とし、その算定した額に端数が生じたときは、10円未満を切り捨てるものとする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受けた場合
(2) 月の途中において特定教育・保育等をやめた場合
5 前項に規定する事由が生じた月において日割りにより利用者負担額等を計算する場合の基礎とする日数は、次の各号に掲げる支給認定保護者に係る支給認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。
(1) 1号認定子ども 20日
(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 25日
6 第10条第1項の届出により利用者負担額等に変更が生じる場合は、当該届出の事実が発生した日の属する月の翌月から利用者負担額等を変更するものとする。ただし、住民税の課税状況に変更があった場合は、当該年度の初日(年度途中に入所した場合においては入所日)に遡って変更するものとする。
7 町長は、利用者負担額等を決定するために必要な住民税の課税情報等の提出がない場合は、その前年度の住民税の課税情報により暫定的に利用者負担額等を決定するものとする。
8 町長は、前項の利用者負担額等決定後において、引き続き当該課税情報等の提出がない場合は、当該児童の属する学齢における最高額を利用者負担額等として決定することができる。
(利用者負担額等の減免)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別な事由により、前条第1項、第2項及び第4項の規定による利用者負担額等を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であると認めたときは、当該利用者負担額等を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(5) 利用児童が疾病等により、保育を利用できない日が連続して10日以上あること。
2 前項の規定により利用者負担額等の減免を受けようとする者は、利用者負担(上限)額減免申請書(
別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定したときは、申請者に対して利用者負担(上限)額減免決定通知書(
別記様式第19号)により通知するものとする。
(督促及び滞納処分)
第16条 町長は、第14条第9項の期限までに利用者負担額を納付しない教育・保育給付認定保護者があるときは、これを督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までに当該督促に係る利用者負担額を完納しないときは、児童福祉法第56条第7項、第8項又は支援法附則第6条第7項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(申請、届出等の手続)
第17条 第6条から第15条までに規定する申請、届出等の手続は、児童が現に利用し、又は利用しようとしている特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者を経由することができる。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(特定教育・保育施設の確認申請)
第18条 支援法第31条第1項の規定により確認の申請をしようとする教育・保育施設の設置者(以下「設置者」という。)は、特定教育・保育施設確認申請書(
別記様式第20号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に当たっては、支援法施行規則第29条第15号の規定により誓約書(
別記様式第21号)を提出しなければならない。
2 特定教育・保育施設の設置者は、支援法第32条第1項の規定により利用定員を増加するために確認の変更を申請するときは、特定教育・保育施設確認変更申請書(
別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、支援法第31条第1項の規定により確認をするとき又は支援法第32条第2項若しくは第3項の規定により確認の変更をするときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認通知書(
別記様式第23号)により、当該特定教育・保育施設の設置者に対し通知しなければならない。
4 町長は、支援法第31条第1項の規定による確認申請を却下するとき又は支援法第32条第2項の規定による確認の変更申請を却下するときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請却下通知書(
別記様式第24号)により、当該教育・保育施設の設置者に対し、その理由を付し、通知しなければならない。
(特定教育・保育施設に係る変更の届出等)
第19条 特定教育・保育施設の設置者は、次の各号のいずれかの事項に変更が生じたときは、特定教育・保育施設確認事項変更届出書(
別記様式第25号)を当該変更の生じた日から10日までに町長に届け出なければならない。この場合において、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴う届出は、支援法施行規則第33条第2項の規定により誓約書を添付しなければならない。
(1) 施設の名称及び設置の場所
(2) 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 確認に係る設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項又は条例等
(4) 建物の構造概要及び図面並びに設備の概要
(5) 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 運営規程
(7) 施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 支援法第55条第2項第1号の規定による業務管理体制の整備に関する事項
2 特定教育・保育施設の設置者は、支援法第35条第2項の規定により当該利用定員の減少をしようとするときは、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(
別記様式第26号)をその利用定員の減少の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
(特定教育・保育施設に係る確認の辞退)
第20条 特定教育・保育施設の設置者は、支援法第36条の規定により当該特定教育・保育の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届出書(
別記様式第27号)を確認を辞退しようとする日の3月前までに町長に届け出なければならない。
(特定教育・保育施設に係る勧告及び命令)
第21条 町長は、支援法第39条第1項の規定により特定教育・保育施設の設置者に対し勧告をするときは、勧告書(
別記様式第28号)を当該特定教育・保育施設の設置者に対し交付しなければならない。
2 町長は、支援法第39条第4項の規定により同条第1項の勧告に従わない特定教育・保育施設の設置者に対し命令をするときは、命令書(
別記様式第29号)を当該特定教育・保育施設の設置者に対し交付しなければならない。
(特定教育・保育施設に係る確認の取消し等)
第22条 町長は、支援法第40条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認の取り消し又は全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消(効力停止)通知書(
別記様式第30号)により、当該特定教育・保育施設の設置者に対し通知しなければならない。
(家庭的保育事業等の認可申請及び特定地域型保育事業者の確認申請)
第23条 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可の申請又は支援法第43条第1項の規定による確認の申請をしようとする者(認可の申請及び確認の申請を同時に行う者を含む。)は、家庭的保育事業等認可申請書兼特定地域型保育事業者確認申請書(
別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に当たっては、支援法施行規則第39条第15号の規定による誓約書を添付しなければならない。
2 町長は、児童福祉法第34条の15第5項本文の規定により家庭的保育事業等を認可するときは、家庭的保育事業等認可通知書(
別記様式第32号)により、当該認可の申請をした者に対し通知しなければならない。
3 町長は、児童福祉法第34条の15第6項の規定により認可の申請を却下するときは、家庭的保育事業等認可申請却下通知書(
別記様式第33号)により、当該認可の申請を行った者に対し、その理由を付し、通知しなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、支援法第44条第1項の規定により利用定員を増加するために確認の変更を申請するときは、特定地域型保育事業者確認変更申請書(
別記様式第34号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、支援法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認をするとき又は支援法第44条第1項の規定による利用定員を増加するための確認の変更をするときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認通知書により、当該地域型保育事業を行う者に対し通知しなければならない。
6 町長は、支援法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認申請を却下するとき又は支援法第44条第1項の規定による利用定員を増加するための確認変更の申請を却下するときは、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請却下通知書により、当該申請をした者に対し、その理由を付し、通知しなければならない。
(特定地域型保育事業者に係る変更の届出等)
第24条 特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者でない家庭的保育事業者等は、次の各号のいずれかの事項に変更が生じたときは、家庭的保育事業等認可変更届出書兼特定地域型保育事業者確認変更届出書(
別記様式第35号)を当該変更の生じた日から10日までに町長に届け出なければならない。この場合において、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴う届出は、支援法施行規則第41条第2項の規定により誓約書を添付しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 当該確認に係る事業に関する申請者の定款、寄附行為及び登記事項又は条例等
(4) 事業所の平面図及び設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(6) 運営規程
(7) 地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 連携施設又は連携する障害児入所施設の名称
(10) 支援法第55条第2項第1号の規定による業務管理体制の整備に関する事項
2 特定地域型保育事業者は、支援法第47条第2項の規定により当該特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときは、特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(
別記様式第36号)をその利用定員の減少の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
(事業の廃止及び確認の辞退)
第25条 特定地域型保育事業者又は特定地域型保育事業者でない家庭的保育事業者等は、児童福祉法第34条の15第7項の規定により家庭的保育事業等の廃止若しくは休止の申請又は支援法第48条の規定により特定地域型保育事業者の確認を辞退しようとするときは、家庭的保育事業等廃止等申請書兼特定地域型保育事業者確認辞退届出書(
別記様式第37号)を当該廃止若しくは休止又は辞退しようとする日の3月前までに町長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者に係る勧告及び命令)
第26条 町長は、支援法第51条第1項の規定により特定地域型保育事業者に対し勧告をするときは、勧告書を当該特定地域型保育事業者に対し交付しなければならない。
2 町長は、支援法第51条第1項の勧告に従わない特定地域型保育事業者に対し同条第3項の規定により命令をするときは、命令書を当該特定地域型保育事業者に対し交付しなければならない。
(認可及び確認の取消等)
第27条 町長は、児童福祉法第58条第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を取り消すとき又は支援法第52条第1項の規定により特定地域型保育事業の確認を取り消すときは、家庭的保育事業等認可取消通知書兼特定地域型保育事業者確認取消通知書(
別記様式第38号)により、当該家庭的保育事業者等又は特定地域型保育事業者に対し通知しなければならない。
2 町長は、児童福祉法第34条の17第4項の規定により家庭的保育事業等の制限若しくは停止を命じるとき又は支援法第52条第1項の規定により特定地域型保育事業の確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、家庭的保育事業等制限等通知書兼特定地域型保育事業者確認効力停止通知書(
別記様式第39号)により、当該家庭的保育事業者等又は特定地域型保育事業者に対し通知しなければならない。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後に係る支援法及び児童福祉法並びにこれらの規定により制定された法令及び条例の施行に当たり必要な行為のうちこの規則の規定を適用する必要があるものは、施行日前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定については、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた処分、手続き、その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第23号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
1号認定
各月の初日において教育を受ける支給認定子どもが属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) |
一般世帯 | ひとり親世帯等又は在宅障がい児(者)のいる世帯 |
1 | 生活保護世帯 | 0円 | | 0円 | |
2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | | 0円 | |
3 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 | 0円 | | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 | 0円 | | 一般世帯額と同額 |
5 | 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 | 0円 | |
別表2(第5条関係)
2・3号認定
各月の初日において保育を受ける支給認定子どもが属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) |
保育標準時間 | 保育短時間 |
一般世帯 | ひとり親世帯等又は在宅障がい児(者)のいる世帯 | 一般世帯 | ひとり親世帯等又は在宅障がい児(者)のいる世帯 |
3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳 | 4歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 |
A | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C1 | 均等割の額のみの世帯 | 17,900円 | 0円 | 0円 | 8,450円 | 0円 | 17,500円 | 0円 | 0円 | 8,250円 | 0円 |
C2 | 市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯 | 38,400円未満 | 18,500円 | 0円 | 0円 | 8,750円 | 0円 | 18,100円 | 0円 | 0円 | 8,550円 | 0円 |
C3 | 38,400円以上 48,600円未満 | 19,500円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 19,100円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 0円 |
C4 | 48,600円以上 64,100円未満 | 21,600円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 21,200円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 0円 |
C5 | 64,100円以上 77,101円未満 | 24,400円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 23,900円 | 0円 | 0円 | 8,800円 | 0円 |
C6 | 77,101円以上 80,500円未満 | 24,400円 | 0円 | 0円 | 一般世帯額と同額 | 23,900円 | 0円 | 0円 | 一般世帯額と同額 |
C7 | 80,500円以上 97,000円未満 | 28,000円 | 0円 | 0円 | 27,500円 | 0円 | 0円 |
C8 | 97,000円以上 118,500円未満 | 32,300円 | 0円 | 0円 | 31,700円 | 0円 | 0円 |
C9 | 118,500円以上 142,500円未満 | 36,200円 | 0円 | 0円 | 35,500円 | 0円 | 0円 |
C10 | 142,500円以上 169,000円未満 | 40,000円 | 0円 | 0円 | 39,300円 | 0円 | 0円 |
C11 | 169,000円以上 198,600円未満 | 48,300円 | 0円 | 0円 | 47,400円 | 0円 | 0円 |
C12 | 198,600円以上 230,800円未満 | 52,100円 | 0円 | 0円 | 51,200円 | 0円 | 0円 |
C13 | 230,800円以上 264,400円未満 | 55,900円 | 0円 | 0円 | 54,900円 | 0円 | 0円 |
C14 | 264,400円以上 301,000円未満 | 60,300円 | 0円 | 0円 | 59,200円 | 0円 | 0円 |
C15 | 301,000円以上 | 74,400円 | 0円 | 0円 | 73,100円 | 0円 | 0円 |
別記様式第1号(第6条関係)
別記様式第2号(第6条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第7条関係)
別記様式第9号(第7条関係)
別記様式第10号(第6条関係)
別記様式第11号(第9条関係)
別記様式第12号(第10条関係)
別記様式第13号(第10条関係)
別記様式第14号(第11条関係)
別記様式第15号(第12条関係)
別記様式第16号(第13条関係)
別記様式第17号(第13条関係)
別記様式第18号(第15条関係)
別記様式第19号(第15条関係)
別記様式第20号(第18条関係)
別記様式第21号(第18条関係)
別記様式第22号(第18条関係)
別記様式第23号(第18条関係)
別記様式第24号(第18条関係)
別記様式第25号(第19条関係)
別記様式第26号(第19条関係)
別記様式第27号(第20条関係)
別記様式第28号(第21条関係)
別記様式第29号(第21条関係)
別記様式第30号(第22条関係)
別記様式第31号(第23条関係)
別記様式第32号(第23条関係)
別記様式第33号(第23条関係)
別記様式第34号(第23条関係)
別記様式第35号(第24条関係)
別記様式第36号(第24条関係)
別記様式第37号(第25条関係)
別記様式第38号(第27条関係)
別記様式第39号(第27条関係)