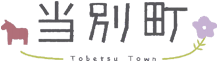平成29年度保健事業実施計画(データヘルス計画)
平成29年度基本方針
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針及び当別町特定健康診査等実施計画(第2期)に基づき、予防を重視した生活習慣病予防対策を推進し、糖尿病等の生活習慣病の予防、ひいては病気の重症化を予防し、健康寿命の延伸と医療費の適正化を図ります。
また、平成26年度に策定した保健事業実施計画(データヘルス計画)に基づき、健診・医療等の情報を活用し、Pdcaサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の推進を図ります。
※Pdcaサイクル…事業を継続的に改善するため、Plan(計画)-Do(実施)-Check(評価)-Act(改善)の段階を繰り返すこと
これまで経過
平成20年度から始まった特定健康診査、特定保健指導は10年目を迎え、第2期当別町特定健康診査等実施計画の評価年となります。また、とうべつ健康プラン21(第2次)の中間見直しの年でもあり整合性を図り策定する必要があります。
特定健康診査受診率は、平成29年度目標を60%としておりますが、平成27年度受診率は54.2%(目標57.0%)と伸び悩んでおり、40歳~64歳代の受診率が低いことや、新規受診率が低いこと、生活習慣病治療者の受診率が低いことが課題となっています。
特定保健指導率では、平成27年度実施率が61.1%(目標58.0%)となり、平成29年度目標としている60%を達成しています。
また、平成21年度からは特定保健指導以外の保健指導も実施し、発症予防及び重症化予防の支援を行ってきました。
一方、町の医療・介護及び健診の分析から、医療費が高額で要介護者の主要な原因疾患の一つになっているものが「虚血性心疾患」であることが明らかとなり、そこで虚血性心疾患のリスク因子となる動脈硬化性血管疾患への発症予防・重症化予防対策を実施していきます。(平成27年3月作成データヘルス計画より)
保健事業
基本方針に基づき、次の保健事業を実施します。
1.特定健康診査受診率向上対策
特定健診受診率60.0%の目標を目指して取り組みます。
| 事業区分 | 実施内容 |
|---|
1)継続受診促進事業 | 【対象者】3,718人
・特定健康診査対象者全員
・特定健康診査の受診歴がある人 【内容】
(1)特定健康診査受診券を対象者全員に発送
・4月末に一斉発送する。
但し、昨年度巡回ドック、国保ドック、バス送迎検診を受診した方は受診時期に合わせて発送。
(2)受診時期に合わせた受診勧奨
・前年度、巡回ドック及び人間ドック受診者への受診勧奨(受診票等の送付)
・前年度、「特定健康診査に係る同意書兼情報提供書」を利用者への受診勧奨
・前年度医療機関で個別に健診受診者へ、昨年度の受診月を過ぎた時期での受診勧奨
(3)体制の整備
・集団健診の時期に合わせた重点受診勧奨(8月・10月)の設定、勧奨時間の延長
・健診実施日の充実(がん検診と同日健診(とうべつ総合健診 日曜日開催)の実施)
・二次元バーコード等の申込方法の簡素化
(4)受診への動機づけ
・レセプト情報を活用し、生活習慣病の治療をしている方へ治療中データを送付し、受診の実施
・受診者が、継続受診につながるよう、保健指導の充実を図る
・国保被保険者証交付・更新時の周知 |
2)特定健診未受診者対策 | 【対象者】1,745人
・40歳新規対象者
・新規国保加入者
・町内・町外生活習慣病治療者
・無医療者
・不定期受診者 【内容】
(1)個別勧奨の充実
・個別通知及び電話や訪問による受診勧奨の実施
・国保新規加入手続きの際に健診案内の配布
・科学的根拠に基づいた受診勧奨リーフレットの送付
・がん検診との同時受診のすすめ
・健康マイレージ事業の導入
(2)町内医療機関との連携
・特定健康診査に係る同意書兼情報提供書の利用による受診勧奨
(3)関係機関へのアプローチ
・職域との連携による受診勧奨
・地区の保健推進員と担当保健師の共同による受診勧奨
・広報による周知や健康福祉出前講座の実施 |
2.特定健康診査受診者フォローアップ事業
糖尿病等の生活習慣病の予防に着目し、特定保健指導実施率60.0%達成に向けた取り組みを行います。
また、有病状態にある要治療者のうち、重症化する可能性のある人に、保健指導を実施します。
虚血性心疾患の原因となる動脈硬化性血管疾患への発病予防・重症化予防の視点で支援します。
| 事業区分 | 実施内容 |
|---|
1)特定保健指導事業 | 【対象者】182人(積極的支援44人 動機付け支援138人)
・特定保健指導対象者 【内容】
(1)結果説明会の実施
・全員へ結果説明会を案内
・未利用者へ電話による利用勧奨を行い、家庭訪問・来所等で保健指導を実施
(2)医療機関と連携した保健指導
・人間ドックの特定保健指導対象者へ医療機関と連携しタイムリーに保健指導を行う
(3)発症予防のための予備群対策(健診結果に基づく保健指導の徹底)
・特定保健指導対象者への科学的根拠に基づいた保健指導の実施。
(4)運動サポート教室の実施
・内臓脂肪を減少に結びつくよう、積極的支援・動機づけ支援に該当になった方、BMI25以上の方を対象に、10月31日~12月12日を重点期間を設け、週に1度夜間に実施する |
2)特定保健指導未利用者対策事業 | 【対象者】86人(積極的支援6人、動機付け支援80人)
・平成28年度までに特定保健指導対象となった方で、特定保健指導未利用者 【内容】
(1)保健指導の利用勧奨や家庭訪問等による保健指導の実施
・未利用者へ電話等などで保健指導のメリットを伝え、利用しやすい方法で、保健指導を実施
(2)受診時期に合わせた保健指導の実施
・健診受診後の行動変容の気持ちが高まる時期を逃さず、タイムリーに保健指導を行う
(3)保健指導利用への動機づけの強化
・冬期間の夜間に強化月間(7回コース)を設け、対象者を絞り保健指導の実施 |
| 3)受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨対策 | 【対象者】120人
・受診勧奨判定値を超えている者
・治療中断者(生活習慣病の治療をしている方でレセプトが3か月以上途切れている方等) 【内容】
(1)健診結果説明会の実施
結果説明会を案内。
未利用者へ電話による利用勧奨を行い、家庭訪問・来所等で保健指導を実施。
(2)保健指導資料の工夫
グラフを用いて、治療前後の検査データの変化を見える化。治療の効果や必要性について本人と確認する。
(3)セルフケアにつながる保健指導の実施
健康管理の一つとして、血圧自己測定や体重測定を促し。
必要時血圧計の貸し出し等を行い、自己管理できるよう促す。
(4)個々の遺伝や検査値にあわせた目標値の設定
検査値と生活習慣のつながりを確認し、必要時生活習慣改善を促す。
生活習慣改善での検査値の改善が難しい場合、医療機関受診を促す。 |
3.保健指導
医療費が高額で要介護者の主要な原因疾患のひとつが「虚血性心疾患」であり、これらの疾患を予防することで脳血管疾患や糖尿病性腎症への予防効果も期待できることから、重症ハイリスク者へ介入し、生活習慣改善に向けた支援を行います。
| 事業区分 | 実施内容 |
|---|
1)重症化予防事業 | 【対象者】97人
・治療中者を含め、虚血性心疾患や脳血管疾患、人工透析が必要な腎臓病を発症する恐れの高い方 【内容】
(1)健診結果説明会の実施。
全員へ結果説明会を案内。
未利用者への電話による利用勧奨を行い、家庭訪問・来所等で保健指導を実施。
(2)保健指導資料の工夫
グラフ等を用いて、健診データを見える化。本人と目標値を共有し、治療+生活改善を促す。
(3)医療機関との連携
医療機関通院者については、必要時医師連絡票を用いて医療機関連絡を行う。 |
4.早期介入保健指導事業
新規受診者のメタボリックシンドローム該当者及び予備群該当者が多く、特に40~50歳代男性の肥満者が多いことが町の課題です。健診結果を活用した健康管理を継続して行えるよう新規受診者へ保健指導を行います。
さらに、若年の特定健診未受診者が多い実態があり、若年から健診を習慣化できるよう受診勧奨・保健指導を行います。
| 事業区分 | 実施内容 |
|---|
1)生活習慣の一次予防に重点を置いた取り組み | 【対象者】
・特定健診の新規受診者、BMI25以上の必要者 50人 【内容】
(1)健診結果説明会の実施
結果説明会を案内。健診結果の見方や継続受診につながるよう保健指導を実施。
また、肥満が及ぼす影響について情報提供し、生活習慣改善を促す。
(2)運動サポート教室の実施 10回50人 |
2-1)若年者の健診 | 【対象者】18歳~39歳の職場などで健診を受ける機会のない方
(1)フレッシュ健診 20人
(2)人間ドック(若年) 20人 【内容】
(1)個別勧奨等個人に向けた勧奨
・乳幼児健診対象者の保護者に健診アンケートを実施し、内容に基づいた勧奨
・妊娠届出時に生活習慣病のハイリスクであった方、妊娠高血圧症候群であった方、子育て支援事業参加者に個別健診勧奨
・前年度健診受診者で今年度申込のない方へ健診勧奨
(2)集団・関係機関へのアプローチ
・幼稚園・保育所に健診ポスターの掲示 |
2-2)若年者への保健指導 | 【対象者】
・初回受診者、特定保健指導及び重症化予防対象者 14人 【内容】
(1)健診結果説明会の実施
若い世代から、生活習慣病に対する知識の普及を行い、健診を活用した健康管理を行えるよう保健指導を実施。 |
5.医療費適正化のための取り組み
重複・頻回等の受診歴を有する者の家庭を訪問し、健康状態や生活状況を把握するとともに、適正受診、健康の保持増進を図り、医療費の適正化に努めます。
また、医療費の自己負担額軽減や、国民健康保険財政の健全化のためジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及促進に取り組みます。
| 事業区分 | 実施内容 |
|---|
1)重複・頻回・多受診者への適切な受診指導 | 【対象者】
北海道国民健康保険団体連合会より提供される帳票を活用し、対象者を選定
・重複多受診者
・頻回受診者
・多受診者 【内容】
保健師による、医療の上手なかかり方、重複受診による弊害、薬に関する知識の普及、特定健診の受診勧奨、各種保健事業等の紹介と活用、その他対象者に必要なことについて訪問支援の実施。指導後レセプト等で概ね3か月以上継続して適切な受診が行われているか確認する。 |
| 2)医療費通知の送付 | 【対象者】
当別町国民健康保険で医療機関に受診をされた方 【内容】
年6回、偶数月に2か月分ずつ送付 |
3)ジェネリック医薬品(後発医薬品)の普及促進 | 【対象者】
先発医薬品を処方したレセプトで、後発医薬品を利用した時に200円以上の削減効果が望まれる40歳以上の被保険者 【内容】
(1)保険証更新の際にジェネリック利用シールの同封
(2)ジェネリック医薬品差額通知の郵送(年3回) |
6.特定健康診査等実施計画(第3期)・データヘルス計画(第2期)の策定
特定健康診査等実施計画(第2期)、データヘルス計画(第1期)の状況から町の実態を整理し、一体的に平成30年度からの6年計画を策定する。策定にあたっては、とうべつ健康プラン21(第2次)との整合性を図り策定します。