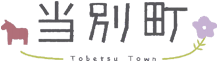本文
現代を活きるプラス 沖田昊聖さん
札幌北陵高校陸上部 沖田 昊聖 さん
インタビュー
7月28日から8月1日まで福岡市で行われた「第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会」の5000m競歩に出場した札幌北陵高校陸上部の沖田昊聖さんに話を伺いました。
姉と兄の競歩に憧れて
小学3年の頃、父に誘われて出場したマラソン大会がきっかけで走ることを始めました。その後、大会に出場したいという想いから、放課後に姉や兄と自宅周辺を走るなど練習に励みました。中学からは陸上部に所属し、1500mや3000mの中・長距離走に取り組み、高校では、姉や兄が競歩でインターハイに出場していたので、自分も競歩に挑戦したいと思い始めました。週末は競歩に熱い指導者がいる練習会に参加して専門的な指導を受け、平日は週末に学んだことの反復練習や改善点を常に探しながら練習しています。
競歩は、1.「両足が同時に地面から離れることなく歩くこと」2.「前脚は接地の瞬間から垂直の位置になるまで、真っ直ぐに伸びていなければならない」というルールがあり、歩型が悪いと失格になる難しさが魅力です。
昨日の自分よりも速く
高校1年の時は5000mを25分以内で歩くことを目標とし、練習では達成していたのですが、大会では緊張もあり、達成できませんでした。2年になってからは、前日の練習よりも速いペースで歩くことを意識することで、タイムが着実に縮まり、全道大会では3年生も出場する中で2位入賞し、インターハイに出場することができました。インターハイでは全道大会とは違い、見慣れない学校の横断幕があるなど、異様な雰囲気だったのと、会場全体の迫力に圧倒されたのを覚えています。
2つの大きな転換点
今年の4月に、肺に穴が開く気胸を発症しました。そのため、全道大会やインターハイはおろか、5月に行われる札幌支部予選すら出場できない可能性がある状況に陥りました。インターハイにもう一度出場したい想いから手術を受け、支部予選に何とか間に合いました。気胸の影響で肺活量は大きく下がり、以前出来ていたことが困難になり、ストレスがかかりましたが、練習を重ねるとタイムも元の水準に近づき、全道大会では2位入賞し、インターハイへの切符を掴むことができました。
もう1つの転換点は今年の全道大会後に、指導者から勧められて厚底のシューズに変えたことです。厚底にすることで体の動作を自然に任せるような歩き方になって速度が上がり、歩くのが楽になりました。もちろん、最初は苦戦していましたが、徐々にコツを掴み、10000mの大会で、5000mの通過タイムが22分を切る自己ベストを出すことができ、自信につながりました。
5000m競歩と10km競歩の違い
僕は5000m競歩と10km競歩の2つの競技を経験したことがあります。2つの競技の主な違いは、5000m競歩はトラックで行われるのに対し、10km競歩は道路で行われることです。場所の違いがもたらす影響としては、1周の距離が400mのトラックだと1周が長く感じるのに対して、道路は1周が約1kmなのですが、それにも関わらずトラックの方が長く感じることです。不思議なことに、道路での競歩の方が時間が短く感じます。
大会後のリカバリ―
大会後に欠かさず行っていることは、レース終了後の栄養補給です。プロテインやご飯、うどんなどの炭水化物をしっかりと摂ることで、まずはエネルギーを補給し、疲労を防いでいます。
高校最後の大会と今後の目標
インターハイが行われた福岡市は、高温多湿で競技環境が北海道とは全く異なっていたので大変でした。そのため、目標にしていた自己ベストを切ることができなかったのは残念ですが、終盤にペースが落ちないという今までできていなかった部分の改善が出来たレースになったので、良い経験になりました。
大学に進んでも競歩は続けたいと考えています。まずは勉強を頑張って大学に入り、インカレに出場できるように頑張ります。

第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会に出場した時の様子(沖田さんはゼッケン番号28)