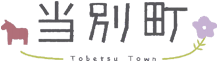本文
令和7年度予算編成の概要
令和7年度予算編成の概要
令和7年第1回当別町議会定例会において、令和7年度の予算編成の概要が町長から表明されましたのでお知らせします。

1 はじめに
令和7年第1回当別町議会定例会開会にあたり、新年度の「予算編成の概要」を申し上げます。
私の町長としての任期も、最後の年を迎えました。
私が町長に就任した3年半前は、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、終息の兆しが見えない状況でありましたが、町の課題の克服に向け6つの目標を定め、この目標を達成するための「4つのファースト」の実現に近づける様々な取り組みを職員をはじめ、町民の皆さんと一体となって進めてまいりました。
【チャイルド・ファースト】
まず「チャイルド・ファースト」では、令和4年度に町産木材をはじめとする道産木材を使用し、木質チップボイラーの導入による脱炭素型の一体型義務教育学校である「とうべつ学園」が開校しました。
また、ふるさと当別を知り、未来を考え、発信する力を育てる教科等横断的な学習「とうべつ未来学」を新たに実施しているほか、「AIドリル」の導入やICT支援員の配置等によるデジタル教育を実現し、町の教育環境の充実を図りました。幼児教育・保育では、ニーズに対応するため、園舎を建て替え、入園希望者の受入態勢を整備するとともに、保育士確保に向けた支援策を実施し、求められる保育環境の向上に努めてまいりました。
さらに、子ども医療費の助成対象の拡充や妊婦歯科健診事業、産後健康診査事業など、妊娠・出産・子育てと切れ目のない支援の実施のほか、子育て世帯向け住宅の整備や住宅購入に対する支援金、高等学校等の通学費支援を実施いたしました。
このように、子どもたちを育む新たな価値を感じる教育の場や環境の提供、そして何よりも当別町らしい特色のある教育内容が評価に結びついた結果、子育て世帯の移住が増加し、令和3年度からは転入者数が転出者数を上回る社会増に転じるなど、着実な成果があらわれました。
【ハートフル・ファースト】
次に「ハートフル・ファースト」では、令和4年3月に道内で20年ぶりとなる在来線新駅「ロイズタウン駅」の開業と令和5年8月に体験型施設「ロイズカカオ&チョコレートタウン」がグランドオープンしました。ロイズタウン駅の駅前広場では、賑わい創出事業として自動運転バスの実証運行やデジタル技術を活用したイベントを開催いたしました。このような取り組みにより、町内を訪れた外国人観光客数の伸び率が2年連続で全国1位という成果に結びつき、「新しいまちの顔」となる人を呼び込むエリアとして、PRおよび観光振興の促進が図られました。
長年の懸案事項でありました町内の医療提供体制においては、令和3年度に医療機関誘致条例を制定し、これまでに3つの医療機関の誘致が実現し、町内で不足していた診療科が新たに開業したことにより、専門分野の医師による診察や検査、治療を町内で受けることができ、医療提供体制の充実が図られました。このことは、子育て世帯をはじめ、多くの町民の安心感の醸成に繋がり、選ばれる町としての魅力を高める結果にも繋がったと感じています。
【クオリティ・ファースト】
次に「クオリティ・ファースト」では、農業を取り巻く情勢が厳しさを増すなか、農業に魅力を感じ、選ばれる職業となるよう柔軟に対応するため「第2期当別町農業10年ビジョン」として改訂し、デジタル技術の活用や6次産業化の推進など、時代に即した施策として位置付けました。
また、地域おこし協力隊を積極的に活用し、農業従事者の新たな担い手の確保にも努め、これまでに延べ4名の隊員を採用し、任期が終了した隊員については、町内の農業法人への新規就農に繋がっております。
このほか、当別町のフィールドに着目し、地域の素材を見出し、町の新たな価値創造に挑戦する人材が現れはじめているとともに、その機運も高まってきております。
再生可能エネルギーの分野においては、各学校や認定こども園、ロイズタウン駅の駅前広場に地中熱や木質バイオマスを活用する再生可能エネルギー設備の導入を図り、また、計画的な森林整備と森林の循環利用を促進し、さらに、令和4年度にはカーボンニュートラルの実現に向けたロードマップとなる「当別町ゼロカーボン推進計画」を策定し、「サスティナブル(持続可能)」な社会の実現に向けて推進してまいりました。
生活の質という点で、雪深い当別町においては、冬季間の除排雪が町民生活を左右します。降雪の状況は年々異なりますが、当別環境整備協同組合と協議を重ねシーズン毎に改善を加え今日の体制を築き、救急車両をはじめ、大型車両の走行にも支障のない道路状況の確保に繋がり、安全・安心に配慮した冬季間の生活環境を提供してまいりました。
【デジタル・ファースト】
最後に「デジタル・ファースト」では、令和4年度に「デジタル田園都市」の実現に向け、「当別町まち・ひと・しごと創生総合戦略(第2期)」を改訂し、「デジタル基盤の構築~デジタル田園都市「Tobetsu“DIGI”town」の創造~」を新たな戦略プランとして位置付け、この戦略プランを基に住民票等の「コンビニ交付サービス」や身近な場所で行政手続等の質問や相談を行うことができる「リモート相談窓口 」の整備のほか、先ほども申し上げました「デジタル教育」の推進などを実施してまいりました。特に自治体DXにおいては、「RPA」による業務の自動化、生成AIの活用による大幅な業務の効率化が図られたほか、インターネットで申請が可能な「電子申請システム」、電子マネー等に対応する「マルチ決済システム」の導入、ペーパーレス化やリモート接続環境の整備など、積極的な自治体DXを推進し、これらの環境を職員自らが最大限に活用することで、場所に制約されない多様な働き方などを実現してまいりました。
また、サツドラホールディングス株式会社との連携のもと、西当別支所が併設する「サツドラ当別太美店」が開設されました。この新たな取り組みにより、買い物拠点と行政窓口が一体となり、行政手続きの利便性の向上が図られ、コンバージェンスな時代にあって、デジタル技術による行政サービスの新たな提供の仕組みを構築するなかで利用者の負担軽減を図り、併せて事務の効率化に繋げることができました。
これまでの「4つのファースト」の実現に向けた取り組みにより、町の魅力や生活環境、利便性の向上が図られ、選ばれる町としての体制整備に繋がり、自然動態においては残念ながら自然減となっているものの、人口のピークであった平成11年以降、減少が続いていた社会動態では、令和3年度から社会増に転じ、着実な成果に結びついているものと実感しております。
しかしながら、医療大学の移転問題に直面し、現在、医療大学の移転後を見据えた連携の在り方について協議しており、また、令和6年度には町内経済の影響緩和と活性化に資する経済対策にも着手するなど、町の将来を見据えた「持続可能なまちづくり」に向けて、取り組みを進めております。
以上、これまでの取り組みについて、申し述べました。
これより、新年度における各分野の具体的な施策の展開について、総合戦略の各戦略プランに沿って、ご説明いたしますが、新年度の予算編成にあたっては、町を取り巻く状況、とりわけ地域が抱える課題の大きさに鑑み、課題解決へと導くために必要な予算の確保を念頭に行っております。
2 施策の展開
戦略プラン1 『産業力の強化』に係る施策の展開
初めに『産業力の強化~しごとの創生~』に係る施策の展開についてです。
「企業誘致推進プロジェクト」「商工業活性化プロジェクト」
まず「企業誘致推進プロジェクト」および「商工業活性化プロジェクト」ですが、企業立地に関する豊富な知識と実績、高い専門性を有する一般財団法人日本立地センターが実施する全国企業向けアンケート調査や企業立地関連団体へ情報提供を行う企業誘致サポート事業を活用し、医療大学跡地の利活用を含めたPR活動を行うとともに、関係機関が開催する企業誘致セミナーに積極的に参加し、新たな誘致対象となる企業の発掘に努めてまいります。
また、企業誘致に関する立地環境や優遇制度のほか、町内の居住環境や支援策等を新たに掲載するなど、企業誘致パンフレットをリニューアルし、併せて英語版パンフレットも作成し、情報発信力のより一層の強化を図ります。
さらに、医療大学の移転により、大学関係者の町内居住や消費が減少し、商工業者を取り巻く環境はこれまで以上に厳しくなることから、町内の民間アパートやマンションへの転居に対するインセンティブとして、当別町共通商品券を進呈し、町内アパートやマンションの空室と町内消費の減少に対する対策を講じてまいります。
加えて、商店主の高齢化等により、空き店舗が増え、賑わいが失われつつある商店街の活性化を図るため、空き店舗等を活用し、店舗・事務所を開設する方に対し、開設資金の一部を支援するなど、本町経済への影響緩和や活性化に向け、町独自の経済対策を引き続き、実施いたします。
そのほか、物価高騰等の影響を受けている事業者や消費者への支援と町内消費の活性化を図るため、商工会が取り組む「とうべつEZOCA」やキャッシュレス決済サービスを活用した町内消費活性化事業を支援いたします。
「農業10年ビジョン推進プロジェクト」
次に「農業10年ビジョン推進プロジェクト」ですが、冒頭でも述べましたが、令和6年6月に策定した「第2期当別町農業10年ビジョン」では、『儲かる農業』を目指し、農業に魅力を感じながら営農する意欲的な農業者が新たな取り組みにチャレンジできるよう生産性の向上を図る「スマート農業」や付加価値を創出する「6次産業化」などを重点施策に位置付けました。この重点施策を推進するため、花卉共選施設における自動選別機の導入実証や、生産、経営、流通のそれぞれのデータを蓄積し、AIによる分析を行う経営改善手法の実証など、農業のDXに取り組みます。
また、令和6年度に引き続き、地域おこし協力隊制度の活用や当別町農業総合支援センターと連携した担い手対策の一層の強化、6次産業化の研修会や商談会を開催し、農業者と飲食店や加工業者との連携を強化するとともに、新たに6次産業化に取り組む農業者に対し、施設や機械の導入支援を実施し、町の農産物を活用した新たなブランド品の創出に取り組みます。
「再生可能エネルギー利用プロジェクト」「林業振興によるエネルギーの地域循環プロジェクト」
次に「再生可能エネルギー利用プロジェクト」および「林業振興によるエネルギーの地域循環プロジェクト」ですが、当別町地球温暖化対策実行計画の目標である「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指し、令和5年度から環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、太陽光発電や木質バイオマス、地中熱利用などの再生可能エネルギー設備の導入支援を行ってまいりました。新年度においても、町民や事業者への設備導入の支援を継続して実施するとともに、公共施設への導入についても検討いたします。
また、令和6年度には「ごみの減量化」や「ごみの再資源化」を推進するため、「環境のために、一人ひとりができることを。」というテーマに「ゆるエコフェス」を開催いたしました。この取り組みは「知って・学んで・体験する」新しいエコイベントとして「リサイクル」、「リユース」などを楽しく学ぶことができる貴重な機会となったことから、引き続き、環境に取り組む町内外の企業との連携による当別町ならではの環境イベントを実施いたします。
林業の振興については、森林資源の循環利用を促進するため、林業事業者への林業機械の導入支援を継続するとともに、新規林道の作設、測量用ドローンとAIによる画像解析システムを活用したスマート林業を推進いたします。
「道の駅プロジェクト」
次に「道の駅プロジェクト」ですが、令和6年度に開業8年目を迎えた「道の駅とうべつ」は、株式会社tobeとの連携により交流人口が増加し、来場者数が令和6年12月時点で開業以来最高の100万人を突破し、町の魅力を発信する拠点として、道内でも有数の集客を誇る道の駅に成長いたしました。
新年度は、新規来場者の呼び込みと来場者の滞在時間を延ばす取り組みとして、ドッグランを新たに整備し、道の駅の売上の向上を図ります。
また、施設建設から8年が経過し、施設の老朽化や各種設備の更新時期を迎えることから、計画的な修繕整備を実施いたします。
戦略プラン2 「人を呼び込むまちの再生」に係る施策の展開
次に『人を呼び込むまちの再生~魅力の創生~』に係る施策の展開についてです。
「新しいまちの顔づくりプロジェクト」
まず「新しいまちの顔づくりプロジェクト」ですが、令和5年度からロイズタウン駅を中心に信号協調や路車協調といったシステム技術を取り入れた自動運転バスの実証運行をはじめ、賑わい創出事業を実施し、町のPRや周遊観光を推進してまいりました。
新年度では、社会実装に向けてより高度な自動運転レベルを目指し、ロイズタウン駅からロイズ工場間におけるレベル4での自動運転バスの実証運行を国土交通省の補助金等を活用し、実施いたします。
「駅周辺再開発プロジェクト」
次に「駅周辺再開発プロジェクト」ですが、新庁舎建設については、医療大学の移転など社会情勢の変化を受け、令和5年度の新庁舎建設検討委員会の協議結果に基づき、現庁舎の耐震化調査を実施した結果、耐震補強工事や老朽化改修工事に想定を上回る多額の費用が必要となることがわかりました。この調査結果を踏まえ、新庁舎建設検討委員会から「現庁舎の耐震化や老朽化対策ではなく、早急に新庁舎建設の議論に移行すべき」との見解が示されたことから、新年度では、新庁舎建設に向けて、建設場所や建設手法などの検討を進めてまいります。
また、町営住宅については、引き続き、末広団地の移転補償および解体を進めるほか、医療大学の移転により町内の民間アパートやマンションの空室の増加が予想されることから、建て替えを前提とした計画から民間アパート等の活用に向けた検討を進めてまいります。
「移住促進プロジェクト」
次に「移住促進プロジェクト」ですが、「住宅購入支援金」の要件について令和6年度から「中古住宅」を新たに対象としたことにより、新築住宅から中古住宅の購入に変化するニーズに対応することができました。新年度においても住宅市場の変化を的確に把握し、さらなる移住促進を目指してまいります。
また、令和6年度に公共交通機関を利用して高等学校等へ通学する生徒を対象に「通学費助成制度」を新たに創設しました。この制度は子育て世帯の負担軽減を図る支援制度の一つでありますので、新年度も継続して実施いたします。
加えて、「当別町は魅力があり、住みやすいまち」であることを首都圏や札幌圏を中心に効果的なプロモーションを実施し、当別町の認知度や知名度の向上を図り、関係人口および移住・定住人口の拡大に繋げてまいります。
公共交通活性化プロジェクト
次に「公共交通活性化プロジェクト」ですが、「ふれあいバス」については、4月から「青山線」の一部デマンド化による便数の確保と移動手段の維持を図り、「西当別道の駅線」については、観光客の移動手段としての利用など効率的な運行を図るため、路線を再編し、利用者のさらなる利便性の向上を図ります。
また、全国で運転手不足を起因とする路線の廃止や減便が相次いで発生するなど、公共交通を維持するためには運転手の確保が必要不可欠であることから、交通事業者の運転手確保に対し支援を行い、持続可能な公共交通の実現に努めてまいります。
観光資源の活用・創出プロジェクト
次に「観光資源の活用・創出プロジェクト」ですが、令和5年度には観光客入込客数が過去最高の162.5万人を記録したほか、訪日外国人観光客向け地図アプリ「ジャパントラベル・バイ・ナビタイム」のデータ分析では、前年同期と比較した町内を訪れた外国人数の伸び率は2年連続で全国1位となり、国内外を問わず多くの観光客が訪れるようになりました。この大きな流れを町内全域に波及させることが重要であることから、当別町観光協会と連携し、当別町の歴史の探求など当別町ならではの新たな観光コンテンツの造成や「当別町周遊観光バスツアー誘致助成制度」を活用したバスツアーの誘致、観光パンフレットの多言語化によるインバウンド対策を実施するほか、北海道観光機構などとの連携による町外での観光プロモーションを実施し、さらなる誘客の強化に繋げてまいります。
戦略プラン3 「未来を担う子どもの育成」に係る施策の展開
次に『未来を担う子どもの育成~ひとの創生~』に係る施策の展開についてです。
「小中一貫教育推進プロジェクト」
まず「小中一貫教育推進プロジェクト」ですが、新年度の当別町教育推進計画では「一人ひとりの学力向上」と「子どもの未来保障」を重点目標として位置付け、これまで実践してきました「GIGAスクール構想」を踏まえ、さらに進化したICT教育環境を整備し、その環境を最大限に活用する「NEXT GIGA(ネクスト ギガ)」へ移行し、主体的・対話的で深い学びの授業改革を推進するとともに、不登校児童生徒への支援として、場所やスタイルを選ばない学習環境の充実を図ります。
また、学習環境の改善を図るため、令和6年度から着工しております「とうべつ学園のエアコン設置工事」をはじめ、西当別小学校および西当別中学校のトイレの洋式化、西当別小学校の教室改修、とうべつ学園水泳プールのろ過装置の更新など、教育施設の環境改善も進めてまいります。
加えて、社会情勢等の影響により物価が高騰していることから、学校給食に対する物価高騰対策を行い、子どもたちに必要な量や栄養バランスを維持した給食の提供に努めます。
「子育て世帯応援プロジェクト」
次に「子育て世帯応援プロジェクト」ですが、安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、乳児の1か月児健診の支援を行うほか、産後ケア事業においては、従来の宿泊型と訪問型に加え、新たに通所型を導入し、サービスの拡充を図ります。
また、現在、策定中の「第3期子ども・子育て支援事業計画」等を包含する「当別町こども計画(とうべつこどもHIRARI計画)」では、「全てのこどもが未来を拓き、幸せを感じて豊かに暮らせるまち 当別」を基本理念とし、この基本理念を実現するため5つの基本目標を定めております。新年度では、基本目標に沿った主要施策を展開し、基本理念の実現を目指してまいります。
さらに、子どもをはじめとした住民のレクリエーションの場である公園遊具の整備・充実を目指し、町外からの来場者も多い「あいあい公園」の複合遊具を更新し、「憩いの場」としての公園機能の再生を図ります。
戦略プラン4 「住み続けたいまちの形成」に係る施策の展開
次に『住み続けたいまちの形成~まちの創生~』に係る施策の展開についてです。
「災害に強いまちづくりプロジェクト(雪対策)」
まず雪対策ですが、これまでも、「新たな雪堆積場の開設」や「除雪情報管理システムの整備」など、除排雪作業の効率化を図ってまいりましたが、物価高騰による除雪機械の高騰、労働力不足など課題は山積しております。新年度では、除排雪事業者への貸与機械として、ロータリー除雪車を1台購入し、さらなる除排雪体制の強化を図ります。
また、道路および河川の改修では、「治水橋」の長寿命化修繕工事、町道十六線の改修を行うほか、近年増加する集中豪雨や局所的な大雨による水害から住民を守るため、トヨベリ川の浚渫工事を実施いたします。
「災害に強いまちづくりプロジェクト(防災)」
次に、防災についてですが、当別町地域防災計画による防災体制を基盤として、災害時に迅速かつ適切な救援活動や支援物資の供給ができるよう、国や北海道、警察、消防など関係機関と緊密な連携を図るとともに、災害時に必要となる備蓄品を計画的に整備し、災害対策の強化に努めてまいります。
また、町民や自主防災組織に対し、親子防災キャンプをはじめとした各種訓練や出前講座、専門家による防災セミナーを実施し、災害時に必要な知識や技術の習得を支援します。
「地域・在宅医療確保対策プロジェクト」
次に「地域・在宅医療確保対策プロジェクト」ですが、2025年は団塊の世代の全員が75歳以上の後期高齢者となり、介護の需要が急増する「2025年問題」が懸念されており、これまで以上に介護人材の確保が急務となるため、令和6年度から町内介護事業者と人材確保について意見交換会を実施してまいりました。この意見交換会を踏まえ、新たに人材紹介料に関する経費や広告宣伝費に関する経費の一部の助成を行い、介護人材確保に向けた支援に取り組みます。
「地域福祉推進プロジェクト」
次に「地域福祉推進プロジェクト」ですが、医療大学、地域包括支援センター、町の3者が協働で実施している「フレイル予防教室」については、この4月で4年目を迎え、年々知名度が上がり参加者も増加しており、高齢者の身体活動や社会参加の機会づくりとしての成果があらわれてきていることから、引き続き、高齢者の健康や生活支援に取り組み、「人生100年時代を支えるまち」の実現を目指してまいります。
また、新年度より帯状疱疹ワクチンの予防接種が定期接種の対象となることから、ワクチン接種費用に対する助成を行い、接種者の負担軽減を図ります。
さらに、就労訓練を行っている障がいのある方に対して、事業所までの交通費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ることで、継続した就労機会の確保による社会参加を促します。
なお、「総合保健福祉センターゆとろ」におきましては、快適な利用環境を整備するため、機械設備の更新を行います。
戦略プラン5 「デジタル基盤の構築」に係る施策の展開
最後に、『デジタル基盤の構築~デジタル田園都市「Tobetsu”DIGI”town」の創造~』に係る施策の展開についてです。
「自治体DXの推進」
「総合戦略を進めるデジタル基盤構築プロジェクト」として、庁内会議や議会などでの資料のペーパーレス化や「文書管理システム」、「RPA」、「チャットGPT」を始めとする生成AI等の積極的な活用と「電子申請システム」や「施設予約サービス」といった住民との接点となる手続きの両面においてDXを推進し、効率的な行政運営を図ります。特に生成AIについては、「マイクロソフト365Copilot(コパイロット)」などの導入にあたり、生成AIの活用に優れた職員を「生成AIエバンジェリスト」として任命し、実際の業務での実践を基に、本格導入に向けた検証を進めてまいります。
また、令和6年度に開設いたしました西当別支所における「ワンストップ窓口」の効果等を検証し、更なる住民サービスの向上に繋がる全庁的な「書かないワンストップ窓口」について検討を進めてまいります。
さらに、町公式ホームページの情報検索機能に生成AIを新たに活用し、自然言語による質問や回答が可能となるほか、音声による照会や外国語による検索にも対応し、必要な情報の入手を容易にいたします。
おわりに
以上、新年度に取り組む施策の概要について、それぞれご説明いたしました。
新年度は、医療大学の移転に伴う影響が生じる始まりの年と認識しており、この影響の緩和と経済活性化に向けた取り組みを柱に予算編成を行いました。
また、新年度には、平成27年に策定しました人口ビジョンの改訂を行い、令和9年度を始期とする新たな総合計画・総合戦略の策定に取り組んでまいります。
町内では、町の未来を創造し、新たな経済機会の創出や持続可能なまちの実現に向けたイベントの開催について、若い世代を中心とする団体よりご提案をいただいているところですが、冒頭、申しましたように、就任時は疫病の蔓延により、開拓150年の諸行事が中止に追い込まれ、大きな節目を共にすることができない時期でもありました。この度の医療大学移転問題を契機に、町の将来に対する危機意識が、若者を中心に共通認識されるようになり、各団体の周年事業と重なることも関連し、町の未来に対する責任世代としての自覚の発露とした提案と受け止めております。
私の残された任期はわずかですが、町全体が一丸となり、この直面する課題に対し、真摯に取り組んでいく意気込みと合意を住民の間に造成することが重要と考え、若者を後押しして共に進むことが、持続可能なまちの創造へと繋がるものと考えております。
おわりに
今、日本の地域社会は、少子高齢化・過疎化から抜け出せない状況が続いています。「適疎」という言葉が語られるようになり、「賑やかな過疎」を目指す地域も出てきました。
これからの地域創造は、縮んでいく地域全体の変化を受け入れつつ、町の機能を維持して適度な(効率的な)地域に作り変えていく努力、新たな町の価値を認め合い、創造していく取り組みが求められるようになりつつあります。
つまり、これからの地域は、賑やかな過疎創造を受け入れつつ、地域振興を図っていく「サスティナブル」から「リジェネラティブ」へ、「防ぎ、持続させること」から「防ぎ、再生させること」への転換を果たしていくことが重要になると思慮いたします。
地域の状況や仕組みを改善してクオリティを維持し、人々がWell-beingを感じ、より幸福になれるよう取り組んでいくための課題解決を進める、そういう町づくりの方向が求められております。
当別町が抱える目の前の課題を見つめ、地域社会が進む方向を見極め、多角的に複眼対応の政策実現で、「都会とは違う豊かさ、Well-being」を感じることのできる「ふるさとづくり」が求められていると強く感じています。
最後になりますが、新年度につきましても、残された任期、町職員とともに正面から課題に向き合い、全力で町政執行に取り組むことをお約束するとともに、議会議員の皆さま方には、今後とも各施策へのご協力を賜りますよう切にお願い申し上げ、令和7年度の予算編成の概要説明といたします。