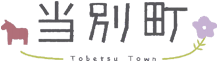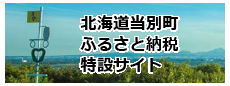本文
令和6年10月からの児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月分から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われました。
まだ手続きを行っていない方は、令和7年3月31日までに申請手続きをお願いいたします(令和6年10月分から遡って支給します)。
なお、令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
児童手当制度の拡充について
児童手当制度の拡充についてのこども家庭のページはこちらです。
児童手当制度のご案内(こども家庭庁)
制度改正(拡充)の内容
(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円円から月30,000円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
|
主な変更 |
改正(拡充)前 <令和6年9月分まで> |
改正(拡充)後 <令和6年10月分から> |
|---|---|---|
|
支給対象 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
|
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
|
手当月額 |
●3歳未満 一律 : 15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 : 10,000円 第3子以降 : 15,000円 ●中学生 一律 :10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律 : 5,000円(特例給付) ●所得上限限度額以上 : 支給なし |
●3歳未満 第1子 ・第 2子 :15,000円 第3子以降 : 30,000円 ●3歳~高校生年代 第1子 ・第 2子 :10,000円 第3子以降 : 30,000円 |
|
支給月 |
3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 10月分~1月分 ⇒ 2月 2月分~5月分 ⇒ 6月 6月分~9月分 ⇒ 10月 |
6回(偶数月) (各前月までの2ヶ月分を支払) 10・11月分 ⇒ 12月 12・ 1月分 ⇒ 2月 2・ 3月分 ⇒ 4月 4・ 5月分 ⇒ 6月 6・ 7月分 ⇒ 8月 8・ 9月分 ⇒ 10月 |
|
多子加算の算定対象 (カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 + 児童手当受給者に生計費の負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子 |
(例)21歳、16歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→ 21歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が当別町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
制度改正による申請について
申請が必要な方
以下のアからウに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
新規の「児童手当認定請求書 [PDFファイル/346KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/121KB]」も記載し提出してください。
イ 所得上限限度額超過で児童手当(特例給付)の支給対象外である方
新規の「児童手当認定請求書 [PDFファイル/346KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/121KB]」も記載し提出してください。
ウ 児童手当を受給中で、別世帯の高校生年代の児童を養育している方
「児童手当額改定請求書 [PDFファイル/184KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/121KB]」も記載し提出してください。
エ 令和6年度で受給資格が消滅して、本改正により新たに受給資格が発生する方
所得超過等により令和6年度で受給資格が消滅した方は「児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用) [PDFファイル/92KB]」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/121KB]」も記載し提出してください。
各様式の記入例
・児童手当認定請求書(記入例) [PDFファイル/586KB]
・児童手当額改定請求書(記入例) [PDFファイル/380KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) [PDFファイル/158KB]
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も受給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。町からの新制度の認定通知等は行いません。
カ 所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満で特例給付を受けている方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。町より新制度の認定通知書等をお送りします。
キ 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育し、現在、高校生年代の児童が同一世帯である方
原則として、令和6年10月分から申請不要で高校生年代の児童を支給対象児童として認定します。町より新制度の通知書をお送りします。
申請の手続き要否確認フロー
手続き要否確認フロー [PDFファイル/139KB]も参考にご覧ください。
制度改正分の受付期限
最終期限 令和7年3月31日(月曜日)(必着)
※最終期限を過ぎた場合は、令和6年1 0月分に遡及しての手当の支給・多子加算の適用はできません(手当の支給・多子加算の適用は、認定請求書(額改定請求書)や確認書を町で受付した月の翌月分 からとなります)。
制度改正分の申請方法
下記いずれかの方法で、手続書類の提出をお願いします。
| 手続方法 | 手続先 |
|---|---|
| 窓口 | 当別町総合保健福祉センターゆとろ 福祉係(当別町西町32番地2) |
| 郵送 |
<送付先> |
よくある質問
Q1.中学生の子の分の児童手当(又は5,000円の特例給付)をもらっています。他にもう1人、町外の高校に通い、学校の寮に住んでいる高校生がいます。何か手続きは必要ですか?
A.15歳以下のお子さんについて現在児童手当(又は5,000円の特例給付)が支給されている方で、高校生年代の子の住民票が当別町にあり、児童手当受給者である親と同世帯の場合には、原則手続は不要で増額します。当別町に住民票がない高校生年代の子については、児童手当認定請求書 [PDFファイル/346KB]の提出が必要ですので、ご申請ください。
Q2.手当を申請する受給者は、父母のどちらでも良いですか?
A.制度の改正により所得制限は撤廃されますが、引き続き原則として生計中心者が受給者となりますので、所得の高い方を受給者として申請してください。
Q3.公務員として働いていますが、提出先や問い合わせは役場で良いですか?
A.公務員の方の提出やお問い合わせは、ご自身のお勤め先となります。お勤め先へご確認ください。
Q4.申請期限を過ぎてしまった場合は、どうしたら良いですか?
A.期限を過ぎた場合でも認定請求書は提出してください。期限を過ぎてしまうと振込が遅れる場合があります。また、令和7年3月31日(月曜日)までに申請を行わない場合は、受給できなくなる月が発生する可能性があります。
Q5.振込はいつですか?
A.初回は令和6年12月です。以降は、2か月ごと偶数月(原則7日)にお支払いします。
記載内容や提出書類に不備があると審査ができずに、振込が遅くなる場合があります。提出前に記載内容や必要書類等を今一度ご確認のうえ、書類を提出してください。
Q6.今後転出予定だが、申請する必要はあるか?
A.令和6年9月末までに転出される場合は、当別町での申請は不要となります。転出先の市区町村での手続きが必要となりますので、転出先の市区町村で、必要なお手続きをご確認ください。
ただし、令和6年10月以降に転出される場合は、当別町でのお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
Q7.大学生年代の子がいますが、どういった場合に手続きが必要ですか?
A.大学生年代の子について監護に相当する世話等をし、生計費の負担をしている場合で、0歳から大学生年代の子を含めて子が3人以上となる場合は、お手続きが必要となります。
Q8.「監護」とはどういった場合のことを指しますか?
A.ここでいう「監護」とは、身の回りの世話をすること、教育についての決定を行うことなどを言います。単身赴任などで同居していない場合でも、上記の事実があれば、監護関係があるということになります。
Q9.「生計費の負担」とはどういった場合のことを指しますか?
A.ここでいう「生計費の負担」とは、同居であって子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親が負っている場合や、別居であって親が学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が考えられます。
Q10.拡充に伴う認定請求書を提出したが、その時の状況と変わった(子のみ転居した等)場合は、どうすれば良いですか?
A.変更となった旨の届出が必要となりますので、窓口にてお手続きください。