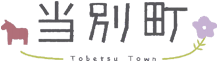本文
児童扶養手当制度について
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が定められた基準以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 1.父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 2.父または母が死亡した児童
- 3.父または母が重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 4.父または母の生死が明らかでない児童
- 5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 7.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 8.母が婚姻によらないで生まれた児童
- 9.父母ともに不明である児童
事実婚状態にある場合には支給されません。
◎必要書類
| 1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚日等の受給資格の発生事由がわかるもの) |
| 2. 印鑑(請求者と扶養義務者の氏名のもの) |
| 3. 請求者名義の預金通帳(道内に支店がある銀行のみ) |
|
4. 加入医療保険情報を確認できるもの(請求者と児童) ※保険者から交付された「資格情報のお知らせ」「資格確認書」 マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等 |
| 5. 年金手帳(「国民年金」または「厚生年金」) |
| 6. 個人番号が分かるもの(請求者、対象児童、扶養義務者のもの) |
マイナンバーを使用する場合、以下の7、8を提出する必要はありません。
|
7. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票 |
|
8. 請求者と扶養義務者の所得課税証明書 (請求年の1月1日に当別町に住民登録がない方のみ必要。前住所地の税務課から発行。) |
※このほか、「認定請求書・公的年金調書・養育費等に関する申告書・同居扶養義務者に関する調書・認定請求に係る生計及び家族等調書」の提出が必要です。
※また、家庭状況によって、申立書・証明書等を提出していただくこともあります。
注意)戸籍謄本について・・・戸籍事務が電算化(コンピュータ化)している場合、窓口にて戸籍を請求しても離婚日等が記載されていない場合があります。請求するときは離婚日等がわかるものまたは平成改製原戸籍と請求してください。
手当の額
| 区分 | 月額 |
| 児童1人のとき | 全部支給 46,690円 一部支給 46,680円~11,010円 |
|
児童2人目以降の加算額 |
全部支給 11,030円 |
※金額は物価変動等により改正されます。
年金との併給について
- 公的年金を受けている場合、児童扶養手当の金額が年金額を上回る場合のみ、差額分を受給することができます。
- 児童扶養手当の金額が年金額を下回る場合は、児童扶養手当を受けることはできません。
手当の支払
手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
支払日は11日ですが、11日が土・日・祝の場合は前日にさかのぼって支給されます。
年6回に分けて、1月、3月、5月、7月、9月、11月に前の2か月分を支払います。
-
児童扶養手当の所得による制限(令和6年11月分から改正)
所得とは
- 1年間(1月から12月)の収入額から、その収入を得るための経費を差し引いた額です。
- ※給与所得者であれば、源泉票の中の「給与所得控除後の金額」です。
いつの所得か
- 1月から9月に申請した場合・・・前々年の所得
- 10月から12月に申請した場合・・・前年の所得
- ※手当受給中の方は、毎年8月に前年の所得を確認し、11月分以降の手当額を決定します。
所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当が減額もしくは全額が支給停止になります。
【所得制限限度額表】
|
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者、扶養義務者 孤児等の養育者 |
|
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
690,000 |
2,080,000 |
2,360,000 |
|
1人 |
1,070,000 |
2,460,000 |
2,740,000 |
|
2人 |
1,450,000 |
2,840,000 |
3,120,000 |
|
3人 |
1,830,000 |
3,220,000 |
3,500,000 |
|
4人 |
2,210,000 |
3,600,000 |
3,880,000 |
|
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族です。