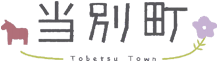本文
高額療養費・入院したときの食事代について(後期高齢者医療)
高額療養費・入院したときの食事代について(後期高齢者医療)
高額療養費
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
高額療養費の支給は、診療月の3~4ヵ月後に登録いただいた口座へ自動的に振込みとなりますが、口座登録のない方(初めて高額療養費が支給される方)は、最初の1回目は申請が必要になります。広域連合から申請書が送られてきますので、必要事項を記載の上、返信用封筒により送付してください。
【1ヵ月ごとの負担限度額】
| 区 分 | 負担割合 | 自己負担限度額 | ||
| 外来 〔個人単位〕 |
外来+入院 〔世帯単位〕 |
|||
| 現役並み所得者 | 現役3 (課税所得690万円以上) |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
|
| 現役2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 |
|||
| 現役1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 |
|||
| 一定以上所得者 | 一般2 | 2割 | 18,000円 【年間上限額 144,000円】 |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
| 一般 | 一般1 | 1割 | ||
| 住民税非課税世帯 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 15,000円 | |||
※多数該当とは、過去12ヵ月間に高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※年間上限額とは、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担限度額です。
【区分判定の仕方】
|
現役並み 3割 |
住民税の課税所得145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方 ただし、次に該当する場合は、申請し認定を受けると原則翌日1日から1割負担 または2割負担になります。 《同一世帯に被保険者が1人のみの場合》 ・被保険者本人の収入額が383万円未満のとき ・同一世帯にいる70歳から74歳までの方と被保険者本人の収入の合計額が 520万円未満のとき 《同一世帯に被保険者が2人以上いる場合》 ・被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき |
|
| 現役3 | 住民税の課税所得690万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方 | |
| 現役2 | 住民税の課税所得380万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方 | |
| 現役1 | 住民税の課税所得145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方 | |
|
一般以上 2割 |
一般2 |
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額」が ・被保険者が1人の世帯 → 200万円以上の方 ・被保険者が2人以上の世帯→ 合計320万円以上の方 |
| 1割 | 一般1 | 住民税課税世帯で一般2(2割)に該当しない方 |
|
区分2 |
住民税非課税世帯で区分1に該当しない方 | |
| 区分1 | 世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、次のいずれかに該当する方 ・世帯全員が所得0円かつ公的年金受給額80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給されている方 ・給与所得がある場合は、令和3年8月以降は給与所得金額から10万円を 控除して判定 |
|
限度額適用・標準負担額減額認定の申請
令和6年12月2日以降、新たに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は行いません。
マイナ保険証をご使用の方はマイナ保険証にて、医療機関で確認ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方は、申請に基づき、適用区分を記載した資格確認書を交付します。
※マイナ保険証については、「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご参照ください。
入院したときの食事代
入院中の食事代は、保険の資格情報を確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)の提示により1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当することを医療機関で確認できた場合は、下表のとおり食事代が減額されます。
| 現役並み所得者・一定以上所得者・一般 |
1食 510円(490円) |
||
| 住民税非課税世帯 |
区分2 |
過去12ヵ月間で90日までの入院 | 1食 240円(230円) |
| 過去12ヵ月間で入院91日目から(長期該当) | 1食 190円(180円) | ||
|
区分1 |
1食 110円 | ||
※令和7年3月31日までは()内の金額となります。
※長期該当は、「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けている期間における入院日数が対象となりますので、入院前には必ず限度額適用・標準負担額減額認定の申請してください。